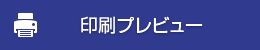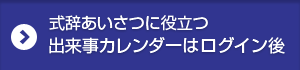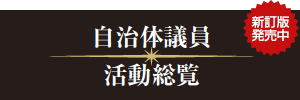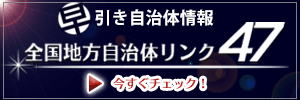主体的に政治に関わろうとしない若者が増えていくことは民主主義社会日本の将来の危機。
若年層の投票率が、他の世代に比べて低いことは近年始まったことではありませんし、日本に限った話でもありません。自らの生活は自分で賄うことができる状況だったり、年金を受け取ったり、医療機関にかかる等政治に頼ることが少ない若者の投票率が低いことは、ある程度仕方のないことかもしれません。
しかし、今の日本において若者が投票に行かない理由は、これまでと少し変わってきているように感じます。投票に行かない理由として「どうせ、数の少ない若者の意見は通らないから投票に行かない」という声を多く聞きます。少子高齢化の現状だからこそ出てきた、新しいタイプの選挙棄権理由です。若者世代は世代人口が少なく、いくら投票率が高くなっても、投票者数では高齢世代を超えることが難しい現状があります。そして、その結果、高齢者に配慮した予算配分や政策実施が行われる、いわゆる「シルバーデモクラシー」の状況になっていると近年盛んにいわれています。もちろん、投票に行く人が高齢者の方が多いからといって、常に高齢者を優遇した政治が行われているわけではありません。しかし、投票率が高く、接点も多い高齢者にどのように捉えられるかを念頭に置きながら政治が行われている面もあることは否定できません。
このまま若年層の投票率が低いままで、主体的に政治に関わろうとしない若者が増えていくことは、民主主義社会日本の将来の危機を招きます。人口減少社会という新たな状況を乗り越えていくためには、将来をつくり担う存在である若者が主体的に政治に参画する必要があります。民主主義は多様な存在が政治に参画することでその正当性を持ち、力を発揮しています。人口減少という社会の大きな転換期を乗り切るためにも、今こそ若者の投票率向上を目指す必要があります。
若者に、政治は自分たちの力でつくっていくことができるものであり、それが必要であることを感じてほしい。
では、若者の社会・政治への意識はどのようなものであるかを整理するために、いくつかのデータを紹介します。
「自国のために役立つと思うようなことをしたいですか?」──。この問いに対し、日本人の若者の54.5%は「はい」と肯定的に答えます。この調査は内閣府が昨夏に公開した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」⑴の1項目で、日本・韓国・アメリカ・英国・ドイツ・フランス・スウェーデンの13歳から29歳の若者に対し行われたものです。上記の問いに対して、肯定的に答えた割合は調査対象7か国の中で日本(54.5%)が、最も高い数字です。また、2015年の成人式の際にマクロミル社が新成人を対象に行った調査⑵によれば、約7割の新成人が自分たちの世代が“日本を変えていきたい”と思っているそうです。若者は日本の社会・将来を考えているし、何かやってやろうとも考えているという意識が見て取れます。
しかし、同時に両調査の他の項目からは、若者の社会・政治への不信感・無力感も伝わってきます。前述の内閣府の調査によると、「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」との問いに対して、肯定的に答えた日本人の割合はわずか30.2%と調査7か国の中で最も低い数字となります。国のために何かしたいと多くの若者が思っているにもかかわらず、自分の力では社会を変えられないと諦めてしまっている現状です。また、前述の新成人対象のアンケート(マクロミル社)によると、81%がこれからの日本の政治に「期待できない」と答え、91%が「国民年金は、将来、自分がもらえるか不安」と回答します。
「何かやりたいけれど、どうせ自分たちでは何もできやしない」と諦めている若者。政治への期待を持っていない若者。そんな彼らに、政治は自分たちの力でつくっていくことができるものであり、それが必要であることを感じてもらわなければなりません。そして、政治に携わる人は、若者に対してそう思わせるように働きかけなければなりません。
若者の投票率が低いことと、政治が若者を後回しにするようになったこと。このどちらが先に起こったのかを論ずることは、鶏が先か卵が先かを論ずることと同様で、現状の解決策とは全く関係ありません。若年層の投票率の低さに対して、問題意識を持っている各々が各々のできることを行い、問題の解決につなぐ必要があります。
その解決のタイミングとしては、4月に行われる統一地方選は大いなる好機です。国政選挙とはまた違う、街・地域の政治・議員を決める地方選挙。少し前置きが長くなりましたが、本稿ではこの選挙で若者を巻き込む方法を考えてみたいと思います。
どこか遠くて難しい政治である国政ではなく、まちづくりや生活の中で政策を語ることで見えるもの。
全地方選挙の最大の共通点は、「地域のことを考える選挙」ということです。自分が住んで暮らしている街のことを考える機会ともいえます。どこか遠い、そして難しい、安全保障やTPPといったことが政策の争点となる国政との大きな違いです。若者を選挙に巻き込むための1つ目の秘けつが、「地域」というキーワードの中にあると考えています。
2012年の衆議院選挙から3年連続で国政選挙が行われ、残念ながら、どれも投票率が低い結果となっています。若年層の投票率も同じく低い状況にあります(2014年衆議院選挙の世代別投票率はまだ公開されていませんが、おそらく低いと思われます)。これらの選挙の投票率の低下の原因はいろいろといわれています。民主党政権を経て政治全体への不信感が高まったことや、自民党の大勝が予想されており選挙に行くモチベーションが出なかったことなど、要因は様々あると思います。また、国政選挙だけでなく、多くの首長選挙・地方議会選挙でも低投票率が多く見られます。
この低投票率の状況を打破する鍵は、各地域の選挙・政治だと考えます。どこか遠くて難しい政治である国政ではなく、まちづくりや生活の中にあるのが特徴です。「政治について考える」というと拒否反応を示す若者であっても、「住んでいる街のことを考える」、あるいはさらに具体例に絞って、「〇〇駅前の再開発について考える」という切り口であれば、気軽にそして身近な話として受け入れるというケースを、若者と政治をつなげるためのNPO活動などの中で数多く経験してきました。
選挙を通じて、同様の経験を若者が積むためには、候補者がしっかりと地域に関した政策、又は地域の現状と目指す未来を有権者に伝える必要があります。政策を見ることで、街の情景が浮かんできたり、自分の生活の状況と重なり、有権者の関心は高まります。
また、政策を書く際に、自身の信条として、その選挙での政策決定範囲を超えたものについて言及することもあると思います。例えば、市議会議員選挙に立候補する際に、国政の範囲である外交安全保障について自身の思いを書くといった場合です。もちろん、自分が立候補をしている自治体が直接に関わることができる範囲の外にある政策分野であっても、重要な政策分野はいくらでもありますし、その分野への自分の意思表示をすることは大事です。しかし、その自治体が直接関わることができる政策分野とそうでないものは区別して発信する必要があります。少し言い方を変えると、政治信条と政策を有権者が混同して捉えることがないように分けて書く必要があるということです。
いずれにせよ、有権者が身近な街のことや、自分の生活のことを想起でき、他人事ではなく「自分事」として捉えることができる政策を掲げることが必要です。
世代が若い人ほど、投票に行く際にネット上の情報を参考にしている。
では、インターネット選挙運動の状況はどうなっているでしょう。2013年の参議院選挙よりインターネット選挙運動が解禁されました。これまでの論調を見ると、インターネット選挙運動の力が弱い、というような内容が多いと思われます。自分は、インターネット選挙解禁のための活動を行っていた身として、急にインターネット上での政策論争が盛り上がったり、ましてや投票率引上げの要因になったりするとは考えておらず、予想と近い状況だとは思っています。インターネットの解禁は大きな変化ではありますが、選挙運動のツールの選択肢の中に「インターネット」が入ってきたにすぎないともいえ、短期間で大きな変化が望めないのは当然です。
他方で、インターネット特有の面白い調査結果も出てきています。それは、「世代が若い人ほど、投票に行く際にネット上の情報を参考にしている」というものです。2013年の参議院選挙の際に共同通信と朝日新聞が行った出口調査から、明らかになりました。
まずは朝日新聞の調査結果をご紹介します。「年代別では20代が、『大いに』と『ある程度』を合わせて『参考にした』人が37%と最も多かった。30代は28%で、年代が高くなるにつれて減り、逆に『見ていない』『わからない』と答えた割合は年代が高くなるほど増える傾向にある」⑶。
続いて共同通信の調査結果では、「年代別に見ると、ネットの情報を参考にした割合が最も高かったのは20代で、23.9%だった。30代は17.9%、40代は12.6%と年代を追うごとに割合は下がり、70代以上ではわずか6.1%。ネットの利用度の違いとみられる世代間の差がくっきりと表れた」⑷。
以上の2つの調査により明白に分かるように、インターネットは若者ほど届きやすい選挙運動のツールなのです。このインターネットをいかに駆使するかが、若年層への働きかけのひとつの鍵となると思われます。今後インターネットを含めてIT技術はますます生活の中での重要度が増してくると考えられており、政治・選挙においても同様だと思われます。
多くの人が拡散をしたいと思える情報を発信することが鍵。
インターネットが既存の他の選挙運動のツールと違う点は、大きく4つあります。1つ目は時間を選ばないこと。一度情報を載せておけば、過去のものもいつでも閲覧することが可能です。2つ目は即座に伝わること。情報をインターネット上に載せさえすれば選挙区内はもちろん、世界中にすぐに情報を伝えることができます。3つ目は双方向でのコミュニケーション。これはインターネットの中でもSNSの普及により可能になりました。様々なツールを通じて一方的な発信受信ではなく、相互のやりとりを可能にしました。4つ目は情報が勝手に広がっていくこと。これもSNSの普及により実現しました。自分が発信した情報が勝手に世の中に広まっていく可能性を含んでいます。
1つ目の点は、インターネット選挙運動解禁前からも使用することができました。つまりは選挙期間前に政治活動の範囲ということで、選挙公約に類するものを掲げている候補者は多くおり、インターネット選挙運動解禁により特に変わるものではありません。とはいえ、前述したように、いかにまちに根差した政策を書き落とすかは重要なポイントです。
次に、残り3つの特性についてこれらを有効に活用し、若者に届ける方法を考えてみました。2つ目の情報の即時性。これに関しては、インターネット選挙運動解禁以後の多くの選挙において比較的多くの候補者が意識していたように思います。TwitterやFacebook上に、街頭演説の様子や次の街頭演説の場所の告知などを流すという行動報告的な使い方です。今まで知ることができなかった候補者の活動を、有権者は知ることができます。
次に、双方向性。街頭演説や街宣車からのアナウンスといった、一方的になりがちであったこれまでの選挙をがらりと変え、有権者を巻き込んだ双方向性のやりとりが実現します。候補者として、何かのテーマについて有権者に質問を投げかけてもよいでしょう。例えば、「私の主要政策は〇〇ですが、この点に関して皆さんの意見はいかがでしょう?」といった感じです。また、有権者が政治・社会に対してどのように思っているのかを聞き出す投稿方法もあります。「子育て世代の皆さんがお困りの点をお知らせください」といった感じです。もっと漠然と「市政への疑問点に関して何でも質問を受け付けます」といったシンプルなものでもいいです。双方向性のコミュニケーションを候補者側から仕掛けることで、有権者は自らの声を候補者が聞こうとしていることに、今までの選挙では感じることができなかった政治的有効感覚を持ちます。意見がある有権者であれば、意見を述べるでしょうし、意見を発信するほどではないとしても疑問点ぐらいはあるものです。
最後に、拡散性。Twitterのリツイート、Facebookのシェアといった機能によりインターネット上の情報は発信者の手を離れてどんどん広がっていきます。裏を返せば、いかに多くの人が拡散をしたいと思える情報を発信するかが鍵です。とはいえ、いくら拡散したとはいえ誰にでも到達するものではなく、情報はその中身によって到達する層が変わってきます。いかにサッカーの特ダネだとしても、野球ファンには重要な情報ではなく拡散させようという情報にはなりません。政治や選挙に関心が薄い若者に自分の発信を届けるには、自身の政策や理念を語るだけでは届きません。一見すると政治・選挙と関係のないような街の小ネタなどの方が意外に広がったりするものです。例えば、市内にある公園の花見スポットといった情報です。そして、その続き、又は次の発信で1人当たりの緑地面積の話題や、子育て世代が子どもを連れていくことができる公共の場所がどれぐらいあるかといったことに広げていけばいいのです。情報の拡散の最初は、候補者の直接のフォローワーです。彼らは政策の話や日々の活動の話などでも拡散してくれるでしょう。しかし、フォローワーのフォローワーがさらに拡散するかの基準は、フォローワーの基準とは異なります。政治の話だけでなく、街の情報を含めることにより、フォローワーのフォローワーもが拡散をしたがる情報になり広がっていきます。
政治家の皆さんに、統一地方選で考えてほしいこと。
若者の政治離れを食い止める鍵は、身近なまちの政治に関心を持ってもらうことです。そのためには地方選挙は重要です。まちについての政策をとことん落とし込み、まちに暮らす若者が、政治ではなく日々の生活に関わるものだと捉えるような政策をどのようにつくっていくか。そして、その政策をインターネットという若者への影響が高いツールでいかに広げていくか。この2つを統一地方選のタイミングでぜひ考えてみてください。
若者は社会のこと、まちのことを考えています。気にしています。その若者を政治側からの仕掛けで選挙にぜひ巻き込んでください。
⑴ 内閣府調査:平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査
⑵ マクロミル調査:2015年新成人に関する調査
⑶ 2013年7月21日朝日新聞記事
⑷ 2013年7月22日産経新聞記事