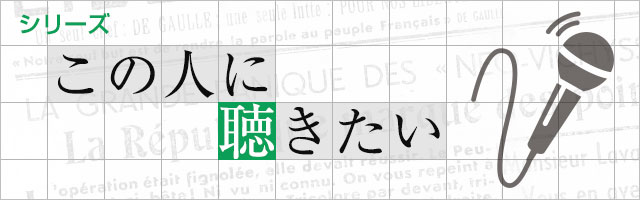議会と議会事務局こそが、車の両輪になれる
――事務局職員として、議会運営における議員のサポートなど、ご苦労はありましたか。
議会の運営には法律で規定されるようなルールはあまりないんですよ。地方自治法上にも何も規定はないので、あくまで前例の積み重ねによって成り立っている部分が大きい。いわば“文化”と表現した方がよいようなものです。各議会が、それぞれの文化を持ってやっているわけですが、同時に、文化を変えていくことだってあったっていいと思っています。
よく、首長と議会を車の両輪と表現しますが、そうではないと思います。首長と議会はやはり二元代表として緊張関係を持って対峙(たいじ)しなければならない。つまり、車の両輪のように同じ方向を向くわけにはいかないのです。一方、議員と議会事務局こそが両輪となる関係だと思います。議員には、そう、議員になろうというくらいなので、あふれるようなPASSION(情熱)がみなぎっている。そのような前に進みたいというエネルギーを発揮できるような体制を議会事務局側がサポートしていく関係が求められているのです。
――サポートの内容をもう少し伺ってもよいですか。
選挙で選ばれた議員と試験を受けて採用された職員との間には、やはり一定の壁が存在しています。両者がどこまで関わるかが問題なんですね。議案審議の過程で抜け漏れた論点はなかったかを事務局に確認するようなルールがあってもよいのかなと思います。審議(委員会)の前の論点整理や終わり際での議論の抜け漏れの確認などは、冷静に見られる議会事務局が担える部分でもありますね。
一方で、議会事務局の職員はやはり、選挙で選ばれた議員とは違います。表決権のある議員の持ち場で侵してはならない領域があることは確かです。議会事務局職員は、議会運営や議会改革をリードするような存在であってはならないと考えます。改革を進めるのは議員です。職員は、あくまでも議員が判断するための情報を出すような存在であるべきだと思います。
議会事務局で働くことは宝くじに当たるようなもの
――それでは、少し話題を変えますが、議会事務局の職員とはズバリどのような職種でしょうか。これまでのご経験の中で感じることを教えていただければと思います。
私はこの手の話の中ではいつもいうことなのですが、“議会事務局で働くことは宝くじに当たるようなもの”であると表現をしています。住民福祉の向上が行政職員としての最大の目的であるところ、まさにその部分にガッツリと関わって市民感覚で仕事ができる、議会はそんなところです。このような機会は、そう多くの職員には巡ってこないものなのです。だからこそ、議会事務局の職員には、議会に配置されたことに対して心意気を持って仕事に取り組んでほしいと思っています。
――議会はクリエイティブな仕事でしょうか。
役人はどうしても前例に縛られ、変化を好まない思考に陥ります。新しいことをするとその分の責任も伴うため、なかなか新しいことにチャレンジするような方向には向いていかないように思いますね。これに対して、議会基本条例が制定されて以降は特にですが、議会事務局は能動的に動き出してきたなと。いろいろと手さぐりでも新しいことに取り組んでいくことが重要です。
――議会改革が進む一方で、従来どおりの活動を続けているという議会も少なくないと思います。そんな議会の事務局職員に対してアドバイスをいただけますか。
議会改革が進み、また、ICT等の情報伝達技術も進み、以前に比べ情報がたくさん入るようになってきました。それまではなかなか分からなかった隣町の状況も見えてくるようになっています。こうしたことから、議会改革が進んでいないという議会の議員でも、感じているところは多いと私は思っています。議員自身も、これから様々な案件に取り組んでいかなければならないことを実感していると思います。ただし、どこからやっていいのか、迷う部分も多いのだと思います。そんなとき、議会事務局職員は先にお話ししたように、いろいろな情報を集めて議員に提示することですね。いろいろな選択肢が提示されることで、議会改革に向けてのハードルが乗り越えやすくなります。
また、人口減少が進んでいる中、必要に迫られている課題は増えています。大変なので手をつけたくないなという感覚には陥りますが、議会改革に取り組まないわけにはいかないという事実が突きつけられているのです。