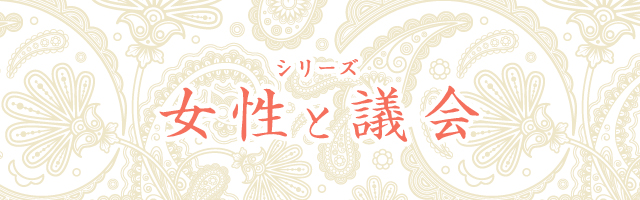調査結果からいえること
予想していたとはいえ、日常的にセクハラに直面している女性議員の多さが明らかになりました。私たちは、何ともやるせない思いでいっぱいになりました。特に1期目で女性が1人や2人の議会でのセクハラ被害が多いことから、「お前が来るところではないんだぞ」といった脅しを感じます。
議会の中で感じる、目に見えない男性たちの奇妙な共存ネットワーク、そこから女性議員ははじかれています。市民の負託を受けて、同じように選挙で当選してきたにもかかわらず、対等な同僚議員ではなく性的対象としての「女」という位置付けともいえます。だから、抱きついたり触ったりといった身体接触や「女のくせに」といった侮蔑発言などが、公然と容認されてしまっているのです。
そんな中、男性化することで、あるいは女性役割を積極的に担ってしまうことで、自分の居場所を見いだす女性議員もいます。しかし、女性議員が複数化していくことで、「私はわたし」との主張が存在感を持ってきます。これも、ただ女性議員が増えていくことでその存在感が得られるのではなく、一つひとつのセクハラ発言に対し、その場で抗議していく、あるいは、議会の中で男女平等施策を積極的に取り上げていくといった努力によって得られているものだということも、調査から読み取れました。
また、「何がセクハラか?」ということに関し、自らの性差別被害に対して感度の高い人は、他の人の性差別被害に対しても感度が高くなっている傾向が見られたことから、性差別の実例を可視化することの重要性にも改めて気づかされました。
そして、さらに重要なこととして、「被害者」でも「加害者」でもない「第三者」の存在が、セクハラ防止に必要であるという視点でした。報告集への寄稿で、東京経済大学准教授の澁谷知美さんは、「ハラスメントや暴力問題にかかわっている当事者は、被害者や加害者だけではない。第三者が暴力に対して黙っていれば、暴力は容認されたこととなり、さらに蔓延する。反対に第三者が批判の声を上げれば、暴力の抑止力になる」としています。
アンケートからも、「傍観する第三者」、「ハラスメントを積極的に認める第三者」の姿が浮かび上がってきます。前述の集団的セクハラの場面でのはやし立てる傍観者や都議会セクハラヤジでの制止しない議長や一緒に嘲笑する男性議員たちなどがそうです。
次のようなアンケート記述などにおいても、第三者の抑止力のなさが如実です。
“会議後の懇親を兼ねた酒が入った夕食のときに、当時の助役が股間にビールびんを挟み、卑わいな踊りをしたので抗議をすると、他の議員が「まあまあここは余興だから……」といって制止した。”
一方、「抑止力となる第三者」の存在がないわけではないという希望もありました。議員同士の酒席で、腰に手を回したり、抱きつきそうになった男性議員に対し、回答者は振りほどいたのですが、同時に、全員男性である他の議員たちが、「こらー」と加害者を制したというのです。澁谷さんから、まさに第三者の対応として大変理想的なもの、と評されています。
女性議員を増やし、孤立化させない。積極的に男女平等施策や人権問題を取り上げて話題にしていく。何がセクハラか、男性だけでなく女性も敏感になっていく。セクハラ被害の「抑止力となる第三者」を増やす。こんなことが、アンケート調査から見えてきた「組織(議会)の自浄能力」を高めるすべといえます。
女性議員が議会で活躍できるには
私たちは、今回のアンケート結果を受けて、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会(以下「三議長会」という)の各宛てに、「性差別や人権侵害のない、女性が安心して参画できる議会にすることを求める意見書」を提出し、また、各所属議会でも働きかける活動を提起しました。
この意見書では、要求項目のひとつに、会議欠席理由として「産休」を明記し、母体保護のため、産前産後の16週の休暇を認めるよう求めました。
これらの働きかけもあって、2015年5月、三議長会は、女性議員が出産を理由に議会を欠席することができるよう、各議会会議規則のモデルとなる標準議会会議規則を改正しました。大きな一歩です。
また、ハラスメントを防止し、国際基準である「ジェンダーに配慮した議会」への認識を深める研修等の実施も意見書の中で求めたのですが、議会のルールは各議会それぞれなので、これからの取組といえます。各議会で議会改革の取組が進んでいますが、ハラスメント研修の実施をきちんと明文化していく必要があります。
市民に開かれた議会にしていくことも重要です。今回の都議会セクハラヤジ問題が大きな社会問題となった背景には、SNSやテレビ中継を通して、議会でこんなひどいことが行われている、ということを多くの市民が見て、怒りを共有したからです。議会でどんなことが行われているのか、常に市民に対して明らかにしていくなど、議会の透明性を高めていくことが、「組織の自浄能力」を高めることにもなっていきます。
そして、何といっても、議会や政治を男性の聖域にしないで、女性議員を増やしていくことに尽きます。どうやって女性議員を増やしていくかについては、クオータ制(割当制)の導入など、仕組みとしての取組が要です。
私自身、4期目の市議会議員です。立候補の動機は、男女平等、自分たちの暮らしの実感を政策にしていく、という思いからです。所属議会の女性議員比率は25%で、なかなか増えません。そんな中で、セクハラ研修を実施することを提起はしているのですが、「積極的にやる必要はない」といった意見も多く、理解を得るにはまだまだの状況です。しかし、この報告集を各議会等に購入していただき、「これもセクハラなんだ」といった理解から進めていきたいです。
ぜひ、多くの議員並びに市民の方に、この報告集を手にとっていただき、女性議員が安心して仕事のできる議会にするよう、働きかけていただきたいと思います。
●報告集の申込方法
info@afer.jp まで「報告集購入希望」の旨をご連絡ください。
頒価 500円(送料別)