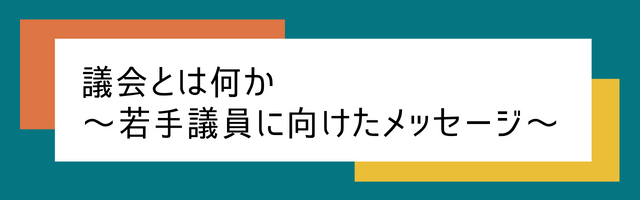継続した地道な活動が大切
地方議員の活動がマスコミで取り上げられることは、残念ながらほとんどない。国会議員はマスコミに登場する機会が地方議員と比べると多い。そのため、最も身近な市町村議員より、テレビの向こうの国会議員の方が、住民からすればマスコミを通じて接する機会が多く、身近に感じるし、投票率も高くなっている。もちろん、国会議員がそのために相当の努力をされていることは認めるところだ。
地方議員の中には、選挙前だけ、活動報告のチラシを発行したり、ホームページやSNSの更新、街頭演説等を行う議員もいる。それでは、「有権者は選挙前の活動だけで、誰に投票するかを決める」と考えているといわれても仕方がない。私は、選挙前も選挙後も、同じ活動をすべきだと考えている。その4年間の活動を見て評価してもらいたいと思う。
また、議員になる前から、議員は毎日、何をしているのか分からなかったので、毎週、週間予定表を作成し、関係者に送付している。私は、住民は、議員の日常の活動を見てくれるし、それをしっかり評価してくれると信じている。
SNSを活用すれば、議員自ら不特定多数の人に情報発信できる環境が整ってきた。議員がどんな思いを持って政治活動をしているのか、どんなことに力を入れているのか、日々どんな活動をしているのかを多くの人に知ってもらうために、SNSを積極的に活用している。また、SNSを通じて、住民からの相談や意見を聞くことにも力を入れている。
最近はSNSを通じての相談が多くなっている。SNSでは本名ではなく、ハンドルネームや匿名での要望も多い。相談から解決まで、一時も会ったり、話をすることなく、誰からの相談か分からないまま解決することもある。
SNSを活用した政治活動は、若手議員の活躍できる可能性の高い分野である。しっかり活用してほしい。
SNSの普及やコロナ禍を経験し、議員活動も大きく変わろうとしている。それは、若手議員にとって大きなチャンスだ。試行錯誤を重ね、自らのスタイルを築き上げてほしい。
街頭演説や市政報告発行、SNSの更新等は、地道な活動だ。いつも住民からの反応があるわけではない。「こんなことをやって意味があるのだろうか?」と不安になるだろう。しかし、地道な活動こそ、継続すれば必ず効果がある大切な活動だ。
コロナ禍だからこそできる活動にチャレンジ
コロナ禍で議員活動は大きく変わらざるを得なくなった。それに加えて、倉敷市は平成30年7月の西日本豪雨災害もあり、大災害、コロナと続き、なおさらだった。
私は、大規模な政治資金パーティーのほか、10人程度の少人数での企画を頻繁に行う活動を続けてきたので、そのほとんどの活動が休止さぜるを得なくなった。
「コロナだからできない」ではなく、「コロナでもできる」ことを見つけなければならない。
その一つが、SNSの活用だ。SNSで積極的に情報を発信した。YouTubeでの市政報告も行った。そして、「LINE何でも相談室」を開設し、住民からの相談を受け付けた。SNSを通じてのコミュニケーションを図り、「SNSの向こうの声に耳を傾ける」ことを目指した。
選挙での投票率が低下している。これは政治不信の表れであり、議員に対する不信感の高まりであり、期待感の低下といえる。議会不要論につながりかねない。
SNSの向こうの名前も顔も知らない人も大切な住民だ。その意見も大切な住民の声だ。そして、その声は年々、大きく、多くなっている。その声を受け止めることは、この時代の議員として必要不可欠なことだと思う。
SNSを通じて、政治に関心を持てなかった層や議員と接点のなかった人たちとつながり、コミュニケーションが図れるようになったことは、政治不信解消に向けて、少なからず明かりが見えてきたといえる。
新しい政治スタイルの確立を目指して、見えづらい目を凝らし、不器用な指を動かし、今日もスマートフォンに向かっている。
若手議員には、若さと行動力で、新しい時代を切り開いてほしい。