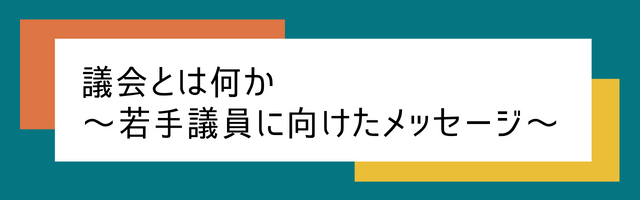はじめは一つの常任委員会で行われていた特定所管事務調査制度であったが、翌年からもう一つの常任委員会でも行われるようになった。これは、すでに行われていた特定所管事務調査が非常に良いものであると、当該常任委員会委員に伝わったものであると感じている。その後、当該議会の任期中に3常任委員会全てが特定所管事務調査制度を導入するに至った。ただ、このときでも、建前は「委員会の活動の中で『特定所管事務調査制度』を運用している」ということであり、議会全体で行っているが議会で決めたことではなかった。全ての常任委員会で行われているにもかかわらず、それぞれの委員会での運用では、議会や行政機関に対しても不都合が生じるおそれがあり(例えば一般質問の取扱いなど)、懸案となっていたとき、改選期を迎えた。
改選を迎え、新人議員が7人(つくばみらい市議会の定数は18人)誕生した。また、私も議長職を拝命した。そこで、特定所管事務調査制度を議会全体の制度とするために、議長着任早々、全常任委員長を集め、各常任委員会で特定所管事務調査制度を正式に議会全体の制度として導入してもらうことを要請し、全委員長に受け入れてもらった。その後、全議員の了解を得て、つくばみらい市議会の正式な制度として定着した。
その際、今まで学んだことを踏まえて制度化することを申合せ事項として文書化した。制度として新たに加えた内容は以下のとおりである。
⑥ 議会として特定所管事務調査制度を定める。
⑦ 最終報告書を議会へ報告したおおよそ半年後に、行政側から進捗状況の報告を求める。
⑧ 一般質問に際して、当該委員は特定所管事務調査事項の質問はしない。
以下、詳細を説明する。
(6)議会として特定所管事務調査制度を定める
先述したように、議会全体の制度として、各委員会で足並みをそろえた。
(7)最終報告書を議会へ報告したおおよそ半年後に、行政側から進捗状況の報告を求める
最終報告書に「提言」を盛り込んでいるため、当該提言等に対する行政の進捗状況、考えについて報告を求めることで、最終報告書が「ただ提出しただけ」に終わることなく、行政側にも真摯に対応してもらうことを期待して制度化した。
(8)一般質問に際して、当該委員は特定所管事務調査事項の質問はしない
特定所管事務調査事項と議員の一般質問との重複が問題となった。特定所管事務調査は、つくばみらい市議会ではおおむね1年で調査研究していくのであるが、その最中に調査部分を一般質問するケースがあった。行政側が当該一般質問に答弁すると、特定所管事務調査で調査している核心部分について先に答弁してしまうことになる。そのため、つくばみらい市議会では「特定所管事務調査については、当該委員は関連する内容を一般質問しない」とした。一般質問は議員の権利であるという議員もいたが、それでもこのようにしたのは、議会全体でこの制度を続けていこうとの意思表示である。