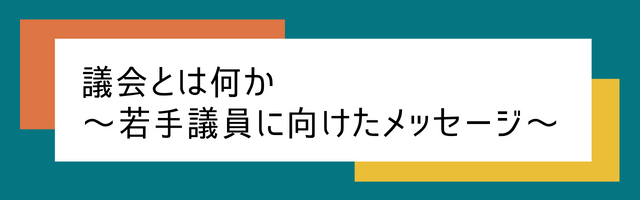(1)委員が自らタイトル、調査事項を決定する
先にも述べたように、「議会で議論、調査研究ができないか?」というところから始まっているので、常任委員会委員が全員で議論、調査研究する内容を、責任を持って定めることで、議論、調査研究が活発化することが期待される。実際の運営についても、タイトル・内容を各議員が提案し、複数の調査事項案が提案された場合には、提案者が提案内容等を説明し、最終的には委員の多数決で決している。
(2)調査について、行政視察等は主に特定所管事務調査事項に費やすものとする
つくばみらい市議会では、年間予算として常任委員会には1人7万円(令和4年度)の行政視察予算が計上されている。この金額だと1泊2日の行程での対応になるかと思うが、主に他県の先進事例の調査研究に費やされる。その際、特定所管事務調査の項目のみを調査対象としている。これは、今までつくばみらい市議会が行っていた行政視察とは違い、「調査項目」に特化したものとなっている。また、近隣の先進事例、特に県内(茨城県)の場合は、行政バス等を用意して、名目上金員を使わないようにした視察も行っている。
(3)閉会中においても調査を行うこととする
以前のつくばみらい市議会では、閉会中の委員会開催は「継続審査」がなされたときだけに行われてきた。しかし、特定所管事務調査を行うには、開会中の委員会開催だけでは時間が足りず、閉会中においても委員会を開催する必要が生じた。それにより、特定所管事務調査以外の所管事務調査も行うことができることとなり、委員会開催のたびに行政報告など、情報提供・共有が図られることとなった。
(4)最終報告書としてとりまとめ、議会に報告する
特定所管事務調査項目をまとめて最終報告書を作成する。完成した最終報告書は定例会で報告する(つくばみらい市議会の場合は、主に12月議会での報告になっている)。この最終報告書には、調査結果はもとより、調査したスケジュール記録や課題、まとめなども記載され、最後に行政への「提言」を盛り込んでいる。後述するが、この提言は、行政側がその後の進捗状況を報告するメルクマールともなり得ている。
(5)調査期間はおおむね1年とする
つくばみらい市議会では議会構成を2年ごとに見直している。そのため、期間中2回の特定所管事務調査事項を定めることがよいのではないかということから、調査期間はおおむね1年とした。