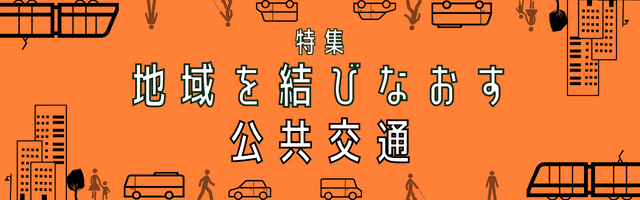(2)具体的な検討の方向性
① 官と民の共創:エリア全体での地域旅客運送サービスの長期安定化
人口減少や高齢化に加え、感染症拡大の影響で交通事業者の経営環境が厳しさを増す中で、新しい生活様式が定着しつつあり、アフターコロナにおいても交通需要の回復が見込めないおそれがある中では、これまでの支援の継続にとどまることなく、交通事業者が自ら積極的にサービス水準の向上や運行の効率化を行うインセンティブ設計の創設や、交通事業者が金融機関からのファイナンスを確保しやすくするための方策など、多様な支援メニューを地域の実情に応じて選択できるようにしていくことが求められる。
既存の運行経費に対する支援は、単年度で系統単位の実績に応じて欠損額の補填を行うものであることから、そのままでは事業改善を行っても赤字欠損の額が減るのみで、交通事業者がサービス水準の向上や運行の効率化等を積極的に行うインセンティブとなりづらい。また、欠損金額が1年間の運行実績に基づいて事後に確定すること、複数年にわたって支払われることが保証されるものではないことから、金融機関から見ると長期的なファイナンスの担保になりづらい。加えて、系統単位の支援制度であることから、ネットワーク全体で官民の各種交通サービスごとに細分化して対応している交通需要を束ね、その上で利便性向上を図りつつ運行を効率化しコストを抑えようとする意識が働きづらい。そこで、一の交通事業者が、又は複数の交通事業者が共同して、自ら積極的にサービス水準の向上や運行の効率化を行うインセンティブ設計の創設や、交通事業者が金融機関からのファイナンスを確保しやすくするための方策など、移動の付加価値向上に向けた投資を喚起する多様な支援メニューを地域の実情に応じて選択できるようにしていくことが求められる。
さらに、エリア単位(可能な限り生活圏の単位とするべき)でのサービスの長期安定化を促すためには、交通事業者への事業改善インセンティブ措置を含めて、系統単位ではなくエリア一括で、かつ、複数年にわたる補助やその概算額確定が事前に行われるような制度を選択肢の一つとして導入すべきである。これにより、単年度欠損の事後補填と比較して、交通事業者の財務状況が明確化かつ安定化され、エリア全体での運行の効率化、設備投資の効率化が可能となり、運転士等の採用計画も立てやすくなるなど、長期安定的な事業運営につなげることができる。また、見込みに比べて利用者が増加した場合、交通事業者の収益改善努力による収益増等を交通事業者に一部還元すること等により、事業改善インセンティブが働く。加えて、複数の交通事業者が交通データを共有できるシステム整備等に取り組む場合は、当該データに基づくマーケティングを通じた収益改善が期待できる。併せて、エリア全体で黒字路線も含めて考慮した想定欠損額に対して、長期安定的な支援を可能にすべきである。
② 交通事業者間の共創:各社やモードの垣根を越えた地域旅客運送サービスの展開
鉄道、バス、タクシー等の交通機関に加え、超小型モビリティ、シェアサイクル等の新たなモビリティサービスも含めて利用者目線であらゆる輸送モードを一体的にとらえ、適材適所で導入しつつ、サービス提供者が相互に連携し共創することで、利便性の向上を図ることが必要である。
加えて、各社の事業の持続可能性を一層高めるためには、サービス面の連携だけではなく、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に資するEV車両、再エネ充填、貯蔵施設等の普及も含め、車両等の共同調達等による規模の経済性、様々な輸送を束ねてコストカットを図る密度の経済性を追求すべきである。また、交通関連データは社会の共有財産であるという側面を持つことから、デジタル化の進んでいない中小・地方部の交通事業者も含め、データ取得のための環境整備を進め、そのオープン化や利活用の一層の促進を図るべきである。
現行の地域公共交通支援制度においても、国は法定協議会の運営に係る経費の一部を補助しているが、乗合バス(コミュニティバス・デマンド交通等含む)以外の輸送モードのあり方について、地域公共交通計画に踏み込んで整理しているものはあまり見受けられないことから、地域交通に関して包括的に議論する場としての機能を十分に果たせていない場合が少なくない。このため、こうした輸送モードのあり方についても未来志向で議論し、共創を図るための環境整備等を推進すべきである。
③ 他分野を含めた共創:くらしのニーズに基づく地域旅客運送サービスの創出
公共交通等の利用を促進するためには、移動の目的を生み出す施設整備などの都市政策との連携や、道路空間など公共交通機関に限らないあらゆる輸送モードに係る施設等との連携など、まちづくり・地域づくりの取組と十分に連携することが必要である。
近年、運賃収入と公的補助だけを原資とする従前のビジネスモデルでは地域交通が成り立たなくなった地域において、まちづくり・地域づくりと連携しつつ、交通サービスの対価という形以外の収入を創出することを含め、必要な交通サービスを住民主体で再構築する兆しが見られている。交通事業者が他分野の事業者を巻き込み、また、移動の目的地となるような他分野の事業者からの提案等を契機として、互いに適切にリスク分担しながら、共創により地域交通をマネジメントすることで得られるメリットは大きい。
国土交通省は今年度、交通を地域のくらしと一体でとらえ、行政や金融機関と連携して取り組む、エネルギー、医療、教育など様々な分野との垣根を越えたプロジェクトの実証事業について、支援措置を創設したところである。実証事業を通じて、事業スキームの構築やファイナンスに係る課題を整理しつつ、各地で必要なくらしのための交通が創出され、持続するよう、今後も同様の支援措置を講ずるべきである。
また、地域交通全体をニーズとシーズの両面からコーディネートできる人材の育成を目指した支援措置を講ずるべきである。その際、地方公共団体の職員、有識者やコンサルタント等はもとより、熱意をもって地域づくりに関わる他分野の人材やその団体に、交通分野でのノウハウを提供し育成することも、創出された地域交通を継続する上で効果的である。
① 官と民の共創:エリア全体での地域旅客運送サービスの長期安定化
人口減少や高齢化に加え、感染症拡大の影響で交通事業者の経営環境が厳しさを増す中で、新しい生活様式が定着しつつあり、アフターコロナにおいても交通需要の回復が見込めないおそれがある中では、これまでの支援の継続にとどまることなく、交通事業者が自ら積極的にサービス水準の向上や運行の効率化を行うインセンティブ設計の創設や、交通事業者が金融機関からのファイナンスを確保しやすくするための方策など、多様な支援メニューを地域の実情に応じて選択できるようにしていくことが求められる。
既存の運行経費に対する支援は、単年度で系統単位の実績に応じて欠損額の補填を行うものであることから、そのままでは事業改善を行っても赤字欠損の額が減るのみで、交通事業者がサービス水準の向上や運行の効率化等を積極的に行うインセンティブとなりづらい。また、欠損金額が1年間の運行実績に基づいて事後に確定すること、複数年にわたって支払われることが保証されるものではないことから、金融機関から見ると長期的なファイナンスの担保になりづらい。加えて、系統単位の支援制度であることから、ネットワーク全体で官民の各種交通サービスごとに細分化して対応している交通需要を束ね、その上で利便性向上を図りつつ運行を効率化しコストを抑えようとする意識が働きづらい。そこで、一の交通事業者が、又は複数の交通事業者が共同して、自ら積極的にサービス水準の向上や運行の効率化を行うインセンティブ設計の創設や、交通事業者が金融機関からのファイナンスを確保しやすくするための方策など、移動の付加価値向上に向けた投資を喚起する多様な支援メニューを地域の実情に応じて選択できるようにしていくことが求められる。
さらに、エリア単位(可能な限り生活圏の単位とするべき)でのサービスの長期安定化を促すためには、交通事業者への事業改善インセンティブ措置を含めて、系統単位ではなくエリア一括で、かつ、複数年にわたる補助やその概算額確定が事前に行われるような制度を選択肢の一つとして導入すべきである。これにより、単年度欠損の事後補填と比較して、交通事業者の財務状況が明確化かつ安定化され、エリア全体での運行の効率化、設備投資の効率化が可能となり、運転士等の採用計画も立てやすくなるなど、長期安定的な事業運営につなげることができる。また、見込みに比べて利用者が増加した場合、交通事業者の収益改善努力による収益増等を交通事業者に一部還元すること等により、事業改善インセンティブが働く。加えて、複数の交通事業者が交通データを共有できるシステム整備等に取り組む場合は、当該データに基づくマーケティングを通じた収益改善が期待できる。併せて、エリア全体で黒字路線も含めて考慮した想定欠損額に対して、長期安定的な支援を可能にすべきである。
② 交通事業者間の共創:各社やモードの垣根を越えた地域旅客運送サービスの展開
鉄道、バス、タクシー等の交通機関に加え、超小型モビリティ、シェアサイクル等の新たなモビリティサービスも含めて利用者目線であらゆる輸送モードを一体的にとらえ、適材適所で導入しつつ、サービス提供者が相互に連携し共創することで、利便性の向上を図ることが必要である。
加えて、各社の事業の持続可能性を一層高めるためには、サービス面の連携だけではなく、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に資するEV車両、再エネ充填、貯蔵施設等の普及も含め、車両等の共同調達等による規模の経済性、様々な輸送を束ねてコストカットを図る密度の経済性を追求すべきである。また、交通関連データは社会の共有財産であるという側面を持つことから、デジタル化の進んでいない中小・地方部の交通事業者も含め、データ取得のための環境整備を進め、そのオープン化や利活用の一層の促進を図るべきである。
現行の地域公共交通支援制度においても、国は法定協議会の運営に係る経費の一部を補助しているが、乗合バス(コミュニティバス・デマンド交通等含む)以外の輸送モードのあり方について、地域公共交通計画に踏み込んで整理しているものはあまり見受けられないことから、地域交通に関して包括的に議論する場としての機能を十分に果たせていない場合が少なくない。このため、こうした輸送モードのあり方についても未来志向で議論し、共創を図るための環境整備等を推進すべきである。
③ 他分野を含めた共創:くらしのニーズに基づく地域旅客運送サービスの創出
公共交通等の利用を促進するためには、移動の目的を生み出す施設整備などの都市政策との連携や、道路空間など公共交通機関に限らないあらゆる輸送モードに係る施設等との連携など、まちづくり・地域づくりの取組と十分に連携することが必要である。
近年、運賃収入と公的補助だけを原資とする従前のビジネスモデルでは地域交通が成り立たなくなった地域において、まちづくり・地域づくりと連携しつつ、交通サービスの対価という形以外の収入を創出することを含め、必要な交通サービスを住民主体で再構築する兆しが見られている。交通事業者が他分野の事業者を巻き込み、また、移動の目的地となるような他分野の事業者からの提案等を契機として、互いに適切にリスク分担しながら、共創により地域交通をマネジメントすることで得られるメリットは大きい。
国土交通省は今年度、交通を地域のくらしと一体でとらえ、行政や金融機関と連携して取り組む、エネルギー、医療、教育など様々な分野との垣根を越えたプロジェクトの実証事業について、支援措置を創設したところである。実証事業を通じて、事業スキームの構築やファイナンスに係る課題を整理しつつ、各地で必要なくらしのための交通が創出され、持続するよう、今後も同様の支援措置を講ずるべきである。
また、地域交通全体をニーズとシーズの両面からコーディネートできる人材の育成を目指した支援措置を講ずるべきである。その際、地方公共団体の職員、有識者やコンサルタント等はもとより、熱意をもって地域づくりに関わる他分野の人材やその団体に、交通分野でのノウハウを提供し育成することも、創出された地域交通を継続する上で効果的である。