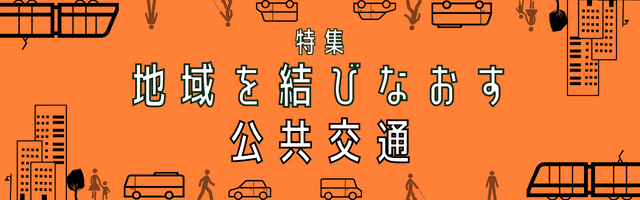国土交通省総合政策局地域交通課
1 はじめに
地域交通は、住民の豊かなくらしの実現や地域の社会経済活動に不可欠であり、くらしやすく魅力あふれる地域をつくり上げるため、そして、地域間の人の流れを創出し、観光客や交流人口の増加を図るために必要な基盤的サービスである。加えて、高齢化の進展に伴い運転免許返納者が近年大幅に増加しており、公共交通による移動手段の確保は重要性を増している。しかしながら、これを取り巻く状況は、長期的な人口構造、地域構造の変化により、厳しさを増す一方であった上、新型コロナウイルス感染症の拡大により、追い打ちをかけられている。具体的には、感染拡大防止のための外出自粛等により、輸送需要が継続的に減少し、交通事業者の経営が悪化、それに伴う路線廃止等のサービス水準の低下により、さらに利用が減少する「負のスパイラル」を避けることが困難な状況にある。このままでは、相次ぐ路線廃止による「交通崩壊」が懸念され、地域社会にも甚大な影響が生じるおそれがある。
こうした状況にあっては、一つの交通事業者が、採算路線と不採算路線との間のいわゆる内部補助により、運賃収入のみによる独立採算を前提に存続することは、これまでにも増して困難である。交通事業者が互いに連携しつつ、経営の安定化を図るため、産業政策として交通事業の維持・活性化を支えることが必要である。
一方で、交通の利用者となる住民の目線では、感染症の拡大を契機としてライフスタイルに変化が見られ、徒歩圏を核とする地域コミュニティの価値が再評価されている。交通事業では移動の目的を生み出す視点が重要であり、交通拠点機能を組み入れた公共施設や生活施設・交流施設の整備や、市民が交流する場づくりなどの都市政策等との連携が不可欠である。
感染症を契機とした、交通事業における上記の課題を緩和する手法の一つとして、日常的なコミュニケーションを前提とした一定の緊張関係の下、地域づくりにおける交通の価値を共有し、相互に能動的でイノベーティブな連携、すなわち「共創」の取組が各地で注目されつつある。
このような現状認識の下、国土交通省では、急速に進展するデジタル技術等の実装を進めつつ、①官と民で、②交通事業者相互間で、③他分野とも、「共創」を推進し、地域交通を持続可能な形で「リ・デザイン」(再構築)するための具体的方策を探るため、学識経験者による「アフターコロナに向けた地域交通の『リ・デザイン』有識者検討会」を本年3月に立ち上げた。
本稿においては、本検討会が8月にとりまとめた提言の内容を紹介することにより、今後の地域交通の方向性を展望することとする。