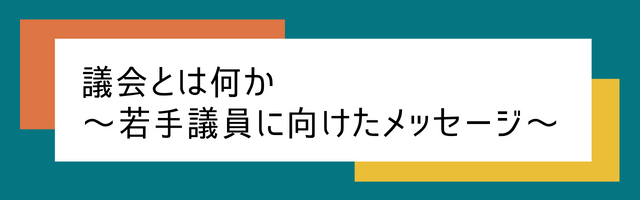(3)議会内の和協
二元代表制の一翼を担う地方議会は、各自治体の最高議決機関であり、その意思は、最終的には多数決により決することになる。もちろん、少数意見をどのようにくみ取るかは、その議会内でのルールによる。
私は、健全な議会とは、「老・壮・青」のバランスが大事であり、若手議員の台頭が、未来につながる施策を具現化できるものと考える。
今でこそ若手議員が数多く誕生するようになってはきたが、地方に行けば行くほど、現在も珍しい存在であり、古参の議員からすれば、若手議員は扱いにくいと感じているのも事実。ただ、何かをきっかけに波長が合えば、若手議員の意見に耳を傾けてくれるので、恐れず嫌がらず、素直に話をしてみよう。
また、ベテラン議員は別だが、若手議員が議会内でのルールを理解せずして、単独で充実した活動をすることは、非常に困難である。まずは会派があれば、会派に所属して経験を積むこと。会派がなければ、分からないことは先輩議員や議会事務局に何でも聞くことが大事。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」。
そして、聞くことから始まるコミュニケーションを大切にし、「若手だが勉強熱心で、将来有望だ」と認められる存在になれば、その後の議会活動はスムーズになるはずだ。
じゃんけんと政治
私が市議・県議・首長を経験して思う「じゃんけんと政治」について、ご笑覧ください。 じゃんけんのグー・チョキ・パーを知らない人はいないだろう。政治の仕組みを子どもたちに分かりやすく教える際、私は「じゃんけん」で説明する。
例えば、政治家(議員・首長)をグー、役所をチョキ、有権者をパーとする。政治家(グー)は役所(チョキ)に対しては強く物事をいえる立場にあるが、有権者(パー)には、選挙があるので弱い。また、役所(チョキ)は、政治家(グー)には弱いが、有権者(パー)には行政の執行権を盾に許認可や徴税等で強く出る傾向がある。そして、有権者(パー)は政治家(グー)には強いが、役所(チョキ)には弱いというものである。
そこで、行政の主体である役所を動かすには、まずは、何といっても政治家が動くのが一番だ。国に対しては国会議員、都道府県に対しては都道府県議会議員、市町村に対しては市町村議会議員が「餅は餅屋で」前面に立つことが大事。その上で、前段でも述べているが、政治家に強い有権者も協働することで、行政が動かざるを得ない状況をつくり出すことが、想いをカタチにするコツである。