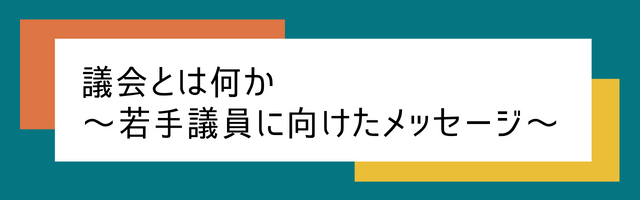委員会中心主義の徹底を
平成12年から本格化した地方分権改革に合わせ、地方制度調査会で議会活性化・機能強化が議論され、「議会のあり方」が第28次地方制度調査会で議論され答申された。それらは地方自治法の改正にも反映され、地方議会は、柔軟な運営ができるようになった。既に、それぞれの議会の工夫とやる気で、十分深掘りすることが可能なのである。
その一つが、「委員会中心主義の徹底」であり、常任委員会の活性化である(特別委員会乱立の弊害については、別の機会に言及したい)。
他自治体での事故、災害等の発生時に、閉会中であっても直ちに委員会を開会し、当該自治体の状況について執行機関に確認・報告させることは、住民の生命・財産を守るために欠かせない。
常任委員会は、基本的に時間の制限や質問回数の制限がない(時間制限や回数制限を申し合わせている議会があるなら直ちに撤廃すべき)。委員の差替えを自由にし、一年中開催しやすい文化を醸成し、質問事項がまとまった委員が開催要求をしたら、自動的に開けるぐらいの機動力が必要である。
常任委員会が頻繁に開かれるメリットは、執行機関にもある。時を待たずに議会に報告できる場が確保され、観測気球的にサウンディングをするための「報告」、「説明」もできるだろう。派生的な効果としては、開会回数が増えるほど、執行機関職員と議員とのコミュニケーション回数も増える。住民の福祉の増大のためには、「3パターンの一般質問」ではなく、委員会活動の充実・活性化は、現行法令の中で最も効果的な議会活動だと考える。
おわりに
当然、議員は、選挙に勝たないことには、議員としての議会活動はできない。しかし、任期4年間、ひたすら自身の次回当選のために活動する議員が、果たして、地方議員に課せられた責任を果たしているといえるだろうか。
昨今、地方議員のなり手不足が問題となり、その原因や対策が各所で議論されているが、筆者は、なり手不足と並行して、人材不足も深刻な問題だと考える。
地方公共団体の二元代表の一翼を担う「議会」がその責任を果たすためには、人材が必要であり、ふさわしい人材を議会に送り込んでこそ、住民は、自らの福祉の増進を達成できるのである。