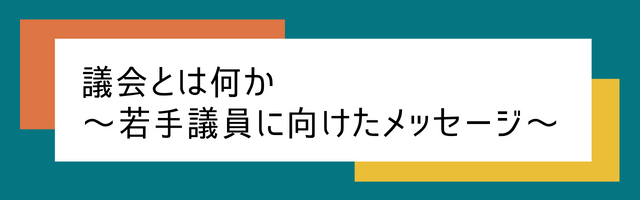過去の会議録を読まずして議会で発言するなかれ
議案審査のためには、そもそも論を頭に置いた上で、中立の位置からスタートすることが必要である。ここでいう「中立」とは、長や補助職員が並べる施策施行の「メリット」を聞いてからではなく、まずは、自身の知見に基づいて、施策評価に着手することである。
その一助となるのが、すべての地方議会に保存されている会議録である。一般質問の対象となる「市の一般事務」は、突き詰めれば、議決に基づいた事務執行であり、過去の議決の際の議論とその会議録が存在する。
しかし、筆者がいた議会でも、この会議録を読まずに議場で発言する議員が実に多かった。過去の議論を全く確認しないまま、過去と全く同じ質疑を行う者がいるのに加え、ひどいものは、自身がかつて発言した内容をまるでなかったかのように、真逆の提案、発言を行い、議場で失笑を買う者もいた。
なお、筆者は、本会議録、委員会記録のほかに、映像録画、音声録音などの記録を全文、全時間保存することを主張している。議論の雰囲気は、文字からは完璧に読み取れない。また、事務事業の開始当時の記録などの公文書も、本来は調査の際に簡単に見られる環境が必要である。
何のための、誰のための一般質問か
さて、冒頭に問題提起した一般質問である。
全国の地方議会の録画や会議録を点検した筆者が、あえて乱暴な定義をすれば、日本の地方議会で、地方議員がその労力の多くを注いでいる一般質問は、
・住民からいわれたことの受け売り
若しくは、
・自分が見ていて気づいた程度の疑問点
若しくは、
・メディアに取り上げられている他地域の社会問題
が大半を占めている。加えて、筆者が極めて問題だと思うのは、担当課長の席へ行けば簡単に解決できる問題について、事前に執行機関と質問内容と答弁のすり合わせを行い、その結果、議員側の考え方、望む方向の答えが導き出せないときは、「◯◯◯〜と要望します」と議員側が一方的に宣言し、答弁を求めないで、質問を終えるケースである。そもそも、要望は、会議規則上「質問」、「通告事項」には該当しない。もし、議会として要望するなら、過半数以上が賛成した「議決」という意思決定が必要である。議員個人の要望など、首長室で個人的にやればよい。
しかも、このような「一般質問」の形をした独演会について、閉会後にSNSやビラ等の議会報告で、「私は、『長』に対してこのように強く求めました」、「これからも私は『長』に対して強く働きかけてまいります」と発信する。自身の支持者向けのパフォーマンスのために、議会と行政の時間が拘束され、経費が浪費されている現実は、「住民福祉の増進を図る」方向とは真逆の誠に憂慮すべき事態である。