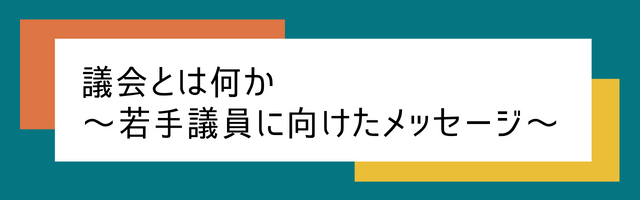議会の本来の役割は、議案審査
当然、本会議における議案質疑も、住民から負託を受けた責任を全うするための審査の一端にすぎない。しかし、当該地方公共団体の住民への影響を考えれば、責任を持ってその可否について最終結論を出すために徹底した調査・研究活動が必要となる議案審査に注力すべきであることは、論を俟(ま)たない。
国の法令改正に伴い提出された議案の場合、調査・研究の過程において、当該地方公共団体の地域特性と矛盾し、問題が見えてくるのは当然のことであり、当該地方公共団体における過去の対応、議会での議論、結論などを精査した上で結論を出すとすれば、議員が議案審査に要する時間は、いくらあっても足りない。
議案に対する意思を示す「議決」のために、提案者以上の調査量に基づいて、住民代表として堂々と住民に説明できるように、態度決定までのプロセスを確立することこそ、議員の本来の活動である。その際、留意すべきは、住民の言いなりになることではなく、住民に行政のあるべき姿について理解を求め、住民に説明できることが議員に求められる姿勢である。
しかし、現在の地方議会では、議案審査に十分な時間を割いて審査している議会がどれだけあるだろうか。
近年の地方自治法改正により、通年開会や年1回開会の議会も増えてきた。また、会期を長めにとり、その会期内で機動的に議案審査ができるようにした地方議会もある。しかし、一方で、依然として、年4回定例会を開き、その会期は1か月足らず、という従前の形式を引きずる議会が大半である。
国会は、議案の上程、質疑、委員会付託、議決日は、当初は決まっていない。一方、地方議会は、議案上程から議決まで、会期当初に決められた審議日程に沿ってほぼ予定調和のように審査・議決が行われる。このことを前提として、執行機関も条例の施行日などをかなり窮屈な日程で提案してくる。国の法令との関係で、施行日が拘束されることを考慮しても、前述した議会の「責任」を考えるなら、議会は、もっと議案に対する十分な審議時間の確保に努めるべきである。
事務事業の棚卸しが必要な時代
昭和22年(1947)4月17日に地方自治法が公布され、日本国憲法と同時に施行された。公布・施行から75年、おおよそ50年後に地方分権改革が始まり、そこから四半世紀。地方公共団体は確実に新たな時代を迎え、人口減少をはじめとする課題を解決するために、事務事業の棚卸しが急務となっている。
事務事業は、節目節目での微調整や時代の変化への対応が必要である。当初の想定・目的を達成した事務事業もあれば、そうでない事務事業もある。全国の地方公共団体では、事務事業の統廃合、再構築、再編成が避けて通れない喫緊の課題として山積状態にある。
平成12年4月の地方分権一括法の施行から地方分権改革が本格的に始まり、地方の権限と責任は大きく変わった。そして、その課題解決のために、地方の自主性を発揮するためのツールも多く用意されてきたが、地方議会がそれらを十分に活用しているとは言い難い。