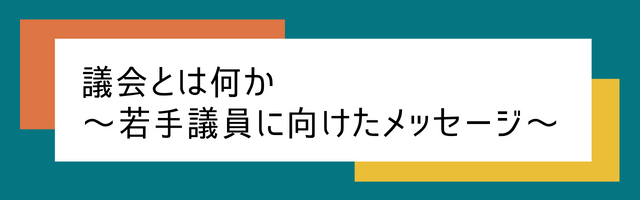前船橋市議会議員 長谷川 大
はじめに
昨今の地方議会での一般質問は、地方議員にとって、まるで会期中の議員活動のクライマックスのようである。国会中継で、国会議員が総理大臣に対して質問するシーンがメディアにのるのを見て、地方議員も、そのような場面に自分を置くことが「議員」の仕事だと大きく勘違いをしているようだ。現在、地方議会の多くが会議の状況をウェブ配信しており、一般質問の場面は、有権者向けの大切なアピールの場なのかもしれない。
果たして、このような本会議の一般質問の場で、首長や執行機関の職員を「追及」することが、住民の福祉の増進につながるのだろうか。
ちなみに、地方自治法で議会に関する条文は89条から138条まで規定され、議会の認定、同意なども含めた議決を必要とする項目は80条以上あるが、「一般質問」なる文言は存在しない。
「一般質問」が規定されているのは、会議規則であり、全国市議会議長会標準市議会会議規則では、62条で「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」と、「できる」規定がなされていることからも、一般質問は、地方自治法が想定した議会の主たる「活動」ではなく、議会の機能を全うするための一手段にすぎないといえる。
地方公共団体の意思決定における議会の責任
地方公共団体は、国と違い、「議員」、「長」いずれも住民に直接選挙で選ばれた者であり、その失職規定は、相互には作用せず、別建ての規定となっている。また、双方の職の権能を見ると、「長」は行政の執行権を持つが、その執行権を行使するための予算、条例はすべて「議会」が決定することになっている。議会を構成する議員一人ひとりが、地方公共団体の重要事項の最高かつ最終の意思決定機関であり、その存在意義を自覚する必要がある。
一般会計予算の規模を見ると、都道府県で最も大きいのは、東京都の約7兆円、市町村では、横浜市が約2兆円となっている。この予算を決定するのも、予算を執行させるための条例を決定するのも議会である。議会が住民から委任されている責任は極めて大きい。
ところが、この責任を果たすための過程(議案の審議)や結論(議決)ではなく、自身が持ち込んだテーマである「一般質問」に多くの時間と労力を割いている議員が少なくない。