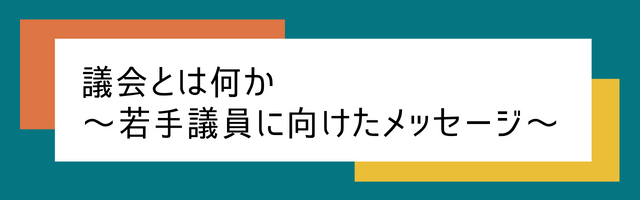前大分市議会議員 三浦由紀
前回から始まった全国若手市議会議員の会OB会のリレー投稿。第1回は豊田市議会議員の岡田耕一OB会会長が寄稿したが、第2回は前会長の私、前大分市議会議員の三浦由紀(よしのり)が務めさせていただく。
“議会改革”。この言葉が頻繁に使われるようになったのは、いつの頃からだろう? 少なくとも私が初当選した平成5年頃は“行政改革”という言葉は使われていたが、“議会改革”は使われていなかった。
行政は変えなければならないが、議会は変える必要がないという雰囲気が主流を占めていたようだ。
これが変わったのが、平成11年に地方分権一括法が公布されてからだ。多くの権限が国から地方へ移管され、地方のことは地方が自ら決めなければならないようになり、おのずと議会も変わらざるをえなくなってきたのである。
このときに先陣を切ったのが、北海道栗山町議会である。平成18年に全国の地方議会で最初に議会基本条例を制定し、これにより“議会改革”の大きな波が一気にでき上がり、栗山町議会に続けと多くの地方議会が議会基本条例の制定を目指し、“議会改革”という言葉が全国に広がっていったのである。
私が所属していた大分市議会もその波に乗り、私が議長のとき、中核市では一番最初に、九州の116市議会中2番目の速さで平成21年に議会基本条例を制定し、それに沿って市民意見交換会の開催や委員会における陳情・請願者への意見陳述の機会を設けるなど様々な新たな取組みを開始した。
さらに“議会改革”を専門に扱う議会活性化推進委員会という組織もつくり、議会基本条例に決められていない案件や、事務事業評価の導入、全国一厳しい政務活動費の使途基準の制定等、次々と“議会改革”を行っていったのである。
これにより、いくつかのシンクタンクから発表されていた議会改革度ランキングでは、前年度はどこにいたのか分からない数百番台であったのが、一気にベスト10内に入るという大躍進を遂げたのはいうまでもない。