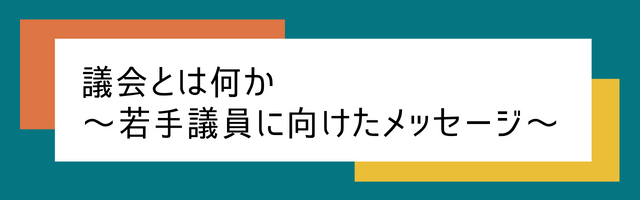豊田市議会において特に「与党意識」を感じるのは、委員会での議案審査における「委員外議員発言の申出」後の正副委員長の対応である。「委員外議員発言の申出」は、豊田市議会における議会の活性化、議会改革の取組みの中で、本会議における議案の質疑は、過去、詳細事項の質疑まで行い、委員会審査との分担が不明確であった反省から、大局的、総括的なものに限定した。その代わり、委員会に籍を置かない会派、諸派の議員の発言機会を確保する方針から近年、認めるようになったものである。
私が議席を得た2000年、2001年頃には、「委員外議員発言の申出」は制度、権利としてはあった。ただし、書類としての「委員外議員発言申出書」を提出しても、実際には、常任委員会の各委員の質疑後に委員長からの「岡田議員の発言申出にご異議ありませんか」との投げかけに対して、所属委員が満場一致で「異議あり」となり、実態としての発言機会はなかった。そうした実態を考えれば相当の進歩といえる。
しかし、その「委員外議員発言の申出」後の実態としては、該当常任委員会開催の2日前の14時までに議案名、質疑の内容を記載した「委員外議員発言申出書」を提出するのだが、その後、正副委員長(予算決算案件に関しては常任委員会単位で分科会となるため、同じ議員が正副分科会長となる)が、議員控室に来て、委員外議員としての質問趣旨を確認する。ここまではいいのだが、よくあるのが、「岡田議員、質問の数が多いのでもう少し少なくならないか」といわれることである。時には「全委員の質問より岡田議員の発言の方が多くなりそうなので、もう少し何とかならないか」といわれたこともある。
私としては、「議案を理解し、市民に聞かれても答えられるように理解しておく必要がある。当然、私自身がその議案に対して、疑義を明らかにし賛成に足ると判断するために必要と思い、これだけの質問項目を提出したのだ」と答える。同時に「私は委員外議員なので、委員の皆さんが先に同趣旨の質問をすれば全く出番はないので、よかったらこれらの質問を皆さんの会派で割り振ってくれればよい」と答える。すると正副委員長は「私たちの立場ではこうした切り口の質問はできないので、岡田議員、よろしく」となる。
この正副委員長の対応こそ、まさしく与党意識丸出しの対応である。こうしたときにも彼らにいうのだが、選挙で市長を応援した立場だとしても二元代表制の一翼を担う立場が議会であり、その構成員が議員である。私自身も反対するための質疑ではなく、疑義を明らかにして賛成するために、また、仮に反対する可能性があるものに対して的確な理論武装、反論するためにもなるのが、委員会での詳細な質疑だと思っている。