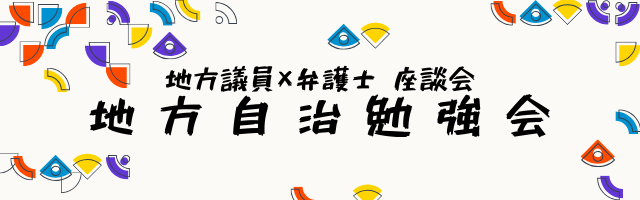予算編成権との関係
滝口〔弁〕 冒頭で「首長提出条例」が普通とのお話がありました。首長と議員との役割分担という観点ではいかがでしょうか。
加藤拓磨〔議〕 首長がやらないところをやるのが大切でしょう。ただ、首長が必要と思えば、首長自ら提出するはずです。裏を返すと、首長としては、そのような条例案は「要らない」と判断しているということです。
滝口〔弁〕 首長が要らないと判断しているとしても、議員が必要と判断したら条例案を提出すればよいとも思うのですが。
加藤〔議〕 首長が要らないと判断したことをやるとなると、予算の問題があります。議員には予算編成権がありません。仮に条例案が制定されても予算が付かなければ、結局何もできません。
尾畠〔弁〕 おっしゃるとおり、予算の観点もとても重要です。ただ突っ走ればいいというものではありません。
縦割りにとらわれない横断的視点・発想
滝口〔弁〕 では、議員提出条例を目指す上で何が重要でしょうか。
尾畠〔弁〕 縦割りにとらわれない横断的視点・発想が大切です。
滝口〔弁〕 それはどうしてですか。
尾畠〔弁〕 住民が議会に求めていることとして、政策の形成や審議の充実が挙げられると思います。その背景には、議員としての日常の活動でくみ取り活動があるはずです。縦割り行政の中では見つけることができない、住民や地域が困っていることを発見することが求められているからです。
滝口〔弁〕 住民や地域が困っていることを発見して条例制定に結びついた具体例を教えてください。
尾畠〔弁〕 私が在籍した古賀市では「古賀市深夜花火規制条例」が議員提出条例で制定されたケースがあります。これは深夜の花火の禁止区域を設けるというものです。地域住民が深夜の騒音に困っていることを議員の方々がくみ取った成果だと思います。
石田〔議〕 なるほど。地道な議員活動あってこそのものと思います。
「原因仮説」を考える
滝口〔弁〕 議員提出条例を実際に練り上げていくには、どのような発想をたどるのがよいのでしょうか。
尾畠〔弁〕 まずは、住民や地域が困っていることを発見することです。「条例の種(シーズ)」とでもいうべきものです。その上で見つけた「条例の種」をどうやって条例化するのかということになります。とてもシンプルですが、以下のプロセスをたどっていくとよいでしょう。
【明確化プロセス】
事実(=問題点) ➡ 原因仮説 ➡ 制度のイメージ案 ➡ 条例化可能性の検討
滝口〔弁〕 「原因仮説」とは、問題が発生している原因を自分なりに分析して、その原因の仮説を立てるということかと思います。
尾畠〔弁〕 「原因仮説」は、切り口というか、腕の見せどころといえるでしょう。この「原因仮説」をかなりシビアに分析しなければなりません。ここが緩いと、たとえ条例化しても問題が解決しません。
滝口〔弁〕 具体的に教えてください。
尾畠〔弁〕 例えば、山林への不法投棄が増加したとします。原因仮説を「監視体制が不十分」だとします。この場合、制度のイメージ案としては「監視員の増員」ということになります。そうであれば、「予算事業で解決可能」ですので、条例化するまでもありません。
阿田川敦史〔弁〕 確かに、条例化すれば直ちに問題が解決するということにはなりませんね。