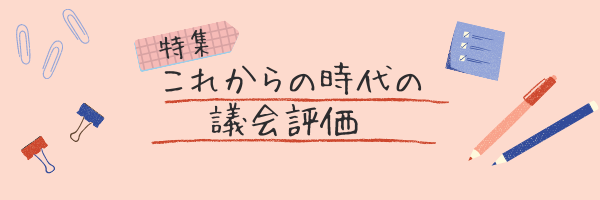8 対話について
基本条例に基づく議員間討議を行っているうちに討論になってしまった経験が何度もある。議会の議事プロセスでは「討論」は議会特有の発言形式であるが、組織変革では、話し合いの変革が必要となるので紹介したい。
① 組織は目的を追求するので、どのように人々を動機付けたらよいのか、どのような雰囲気を心がけたらコミュニケーションが活発になるのかを意識しなければならない。効果的な話し合いは、会議室の中だけではできない。普段から気さくでフランクに話し合える雰囲気をつくり、「笑顔」、「アイ・コンタクト」、「うなずき」、「相づち」の四つを心がけることが必要である。
② 話し合いには次のような種類がある。
・挨拶や世間話のような日常会話(Conversation)
・仮説や意見を出し合ってする議論(Discussion)
・対立し反論し合う討論(Debate)
・アイデアを出し合ったり、提案をし合う対話(Dialogue)
組織変革には、「対話」という話し合い方法が適している。賛成対反対の二項対立を乗り越えて、両方の意見を取り込んだ第三の考え方を導き出すような話し合い方である。
③ 話し合いでは「何をどうするか」を具体的にしなければならない。
・定義 ~ それは何か
・現象の明確化 ~ 何が起こっているのか
・結果の予測 ~ 何が起こるか
・理由・根拠の明確化 ~ なぜそれが起こっているのか、それがなぜ好ましくない(好ましい)のか
・歴史的状況 ~ いつからそうなのか、それ以前はどうだったのか
・地理的状況 ~ どこでそうなのか、他の場ではどうなのか
これらが明らかにされて初めて、「どうすればいいか」の対策が考えられる。
また、議員と議会事務局職員との間で行われる話し合いでは、議員の方から事務局側職員に寄り添うことによって対話が円滑に進むと考えられる。
9 成熟度について
クリス・アージリスによれば、人間の成長過程には七つの人格上の変化がある。個々人が組織に貢献しつつも職場のメンバーとして自分たちの個人的欲求を満たせるような組織状態を目指せば、人々は成熟した行動をとれるようになる。正しく動機付けられれば、人間は仕事の場でも自律的であり、独創的になる。こうした個人の成熟を促す組織は、「成熟度の高い」組織ということになる。

10 結びに
経営品質の考え方を参考にし、「成熟度」を物差しにした議会評価は、他の議会と比べてベストワンを決めるための手段ではない。議会の状態を診断しながら、その過程で得た「気づき」や「学び」を生かしつつ、あるべき状態に向かって永続的な改革改善を続ける、いわばオンリーワンを目指すための手段である。社会環境の変化がますます激しくなる中で議会は、さらなる改革から変革へと大きくシフトし住民福祉の向上を実現していかなければならない。
■参考文献
◇岡本正耿『経営革新の基礎』(経営品質協議会、2007年)