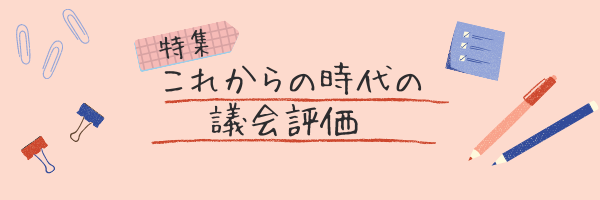日本生産性本部・地方議会改革プロジェクト
1 伝わりにくい議会改革の成果
「議会改革の結果が、住民福祉の向上につながっているのかが分からない」
「議会改革の形だけをつくろうとしているように思う。議員や議会は住民の方を向いているだろうか」
これは、試行的に地方議会評価モデルに取り組んだ地方議員の方々が「気づき」として書きつづった言葉だ。
2000年代以降の地方分権の進展、地方創生の機運の盛り上がりもあり、各地で議会改革が進められてきた。議会基本条例の制定、住民との対話の場づくり、議員間討議の充実、情報公開など改革の試行錯誤は続いている。
しかし、「議会のやっていることが住民に伝わらない」、「議会改革は住民のためになっているのだろうか」という苦悩はそこかしこで聞かれる。
一方で、住民の側からも「議会が何をしているか分からない」という声が上がる。
2 「住民福祉の向上」を評価する試み
地方議会は「地方自治」を象徴し、体現する機関だ。住民の理解や支持は議会の存立基盤である。議会改革は住民の意思をより反映し、住民にとっての価値を実現するための手段に他ならない。
では、改革の取組みの広がりに対して、多くの議会が、住民との関係構築になお困難さを覚えているのは、なぜだろうか。
一つは、長年の慣習や実情によって、住民側に議会への無関心やネガティブなイメージが積み重なっている点があるだろう。また、住民意見を起点とする議会活動─政策サイクルができていないことも考えられる。議会改革の取組みに対しても「制度はできたが、運用ができていない」、「条例数のような数字で分かる成果に捉われてしまう」といった様々な課題が指摘されている。
しかし、より根本的には、議会による価値創造─「住民福祉の向上」が、抽象的・多義的であるからではないだろうか。
日本生産性本部・地方議会改革プロジェクトでは、地方議会が議事機関として持つ、今日的であり、普遍的でもあるこの課題の解決を目指し、住民福祉の向上という観点から、議会を「見える化」し、評価する手法の構築を試みてきた。
北川正恭先生(早稲田大学名誉教授)、江藤俊昭先生(山梨学院大学教授)、早稲田大学マニフェスト研究所、先進議会をはじめ多くの有志議員・事務局職員に支えられ、その一つの到達点として昨年6月に公表したのが、「地方議会評価モデル」(地方議会の成熟度基準)と「議会プロフィール」である。