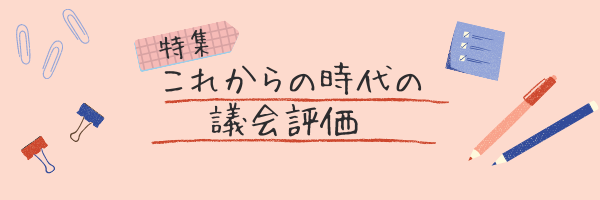組織成熟度による議会評価(経営品質評価)
成熟度議会評価モデルは、議会という組織の成熟度を評価する。議会による評価A、B、議会への評価、議会からの評価は、それぞれこの成熟度評価に内包される。議会による評価A、Bは、組織(経営)が産出するものだからである。また、従来の議会への評価は、組織評価という点で成熟度議会評価と同様とみなされそうであるが、根本的な相違がある。つまり、組織運営を評価することでは同様であるが、従来の議会への評価は静態的、成熟度議会評価は議会からの政策サイクルを評価するという点で動態的である。サイクルを実践するシステムを成熟度という視点から評価する。組織の成熟度評価ではあるが、すでに指摘した議会による評価A、B、議会からの評価を内包したものとなる。したがって、この視点を有して議会への評価(例えば、議会基本条例の評価や改善)は可能であるし、しなければならない。
成熟度議会評価は、五つの視点を有し、それぞれの項目ごとに五つの状態(成熟度)(要約版では三つの状態)で評価する(「地方議会評価モデル」)。この状態が成熟度を測る指標である(状態指標)。この説明は次回以降となる。
成熟度議会評価は、定量指標と定性指標との異同が問われる。定性目標と類似していると思われるが、定量指標を含み込むことも想定している。定性指標の中にも数値化が可能なものもあるが、それも同様である。
数値化により科学的な評価が可能という意見もあるかもしれないが、数値化だけを基準に評価すれば、全体的評価ではなく部分評価になる。例えば、数値化可能な議員提案条例数で評価することになる。成熟度議会評価では、それを念頭に置きつつ議員提案条例策定における議会の行動や議会が持つ能力など、全体的な状態の違いを包括的に評価することを想定している。
また、議会基本条例の条文を評価項目とする場合も、「取り組んでいる」、「成果が上がっている」といった評価者それぞれの思いではなく、成熟度という基準を設定し評価する。
成熟度議会評価の留意点
日本生産性本部が設置した研究会の目的を紹介してきた。詳細は、次回以降に報告される予定である。日本生産性本部(次回)、すでにこの成熟度議会評価を実践している議会や導入を検討する議会、研究会に参加した議員・事務局職員・研究者からの報告が続く。
今回の最後に、留意点を指摘しておきたい(以下の下線は、成熟度議会評価モデルの特徴(ただし、今回は説明していない))。この留意点については、本特集の最後に振り返りたい。
① 成熟度議会評価では、「完成形」の概念がなく、成熟度が高まれば高まるほど、成熟度の段階に応じて、さらに高次元の目標が設定される。つまり、改革改善が永続的に行われる。議会改革は、民主主義と同様に無窮運動が必要である。それを意識しなければ形骸化する。評価参加者(議員、議会事務局職員、第三者、住民等)の討議による「気づき」、それに基づいた改革の連続を目指す。
② 成熟度議会評価モデルを提示するが、地方議会は真空で存在しているわけではない。住民、議会・議員、首長等との三者間関係(信頼度、影響力、投票率、政党化率等)、地域社会の特性(都市化、産業構成等)、といったことも議会改革には影響を与える。また、地域経営の自由度(分権化、財政等)、地域経営が抱える課題(少子高齢化、公共施設の老朽化等)にも影響される。これらを念頭に「議会プロフィール」の中で、今後の戦略が明確になる。要するに、成熟度議会評価モデルは閉じた体系ではない。バックキャスティングや価値創造がキーワードになる。
③ 成熟度議会評価は、すでに指摘したように日本生産性本部の「経営品質」の発想を活用している。「善き政策」には組織プロセスこそが重要であること(経営品質)、価値創造(研究会では「住民自治の推進」)が目的であること、連携・協働(co-production)として把握することを活用している。ただし、住民を顧客(client、consumer、customer)ではなく市民・住民(citizen)(市民の主体性=市民自治)として把握すること、合議制を重視すること(企業や行政のようなトップダウン方式ではなく、合議の重視(気づき、合議体におけるリーダーシップ))、独自の議会改革を推進しつつも競争優位性(卓越した経営)ではなく横への展開(善政競争)を目指すこと、では異なっている。
④ 成熟度議会評価によって議会が変わり、行政も変わるだけではなく、住民も変わることを目指す。一つは、数値化だけではなく、成熟度評価という高度な評価を理解するには、地域経営全体を視野に入れなければならない。また、今後は住民自身が成熟度議会評価を行うことも想定している。住民自治も鍛えられ、主体的に選挙にかかわる。これは、投票だけではなく、自ら候補者となることを含んでいる。
* * *
今回は、地方議会評価の目的、新たな議会評価(成熟度議会評価)の視点を紹介した。次回以降、成熟度議会評価の具体的な内容や実践を報告する。議会からの政策サイクルについては、日本生産性本部『地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会 報告書』(2019年)、江藤俊昭=新川達郎編『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識』(第一法規、2021年)を、地方議会評価モデルについては、江藤俊昭「地方議会評価による地域経営の高度化(上)(下)」地方財務2020年10月号、12月号を、参照していただきたい。
(1) より正確にいえば、大津市議会の議会改革評価は二つの特徴を有する。一つは、議会の機能強化(7項目)、政策立案(7項目)、情報公開(広報)(4項目)、市民参加(広聴)(3項目)、といった広い項目での評価を行っていることである(4分野21項目)。もう一つは、自己評価後に(議員→会派→議会運営委員会(議会としての評価、今後の方向性・改善策の決定))、その評価自体を外部の第三者が検証するという二段階方式を採用していることである。