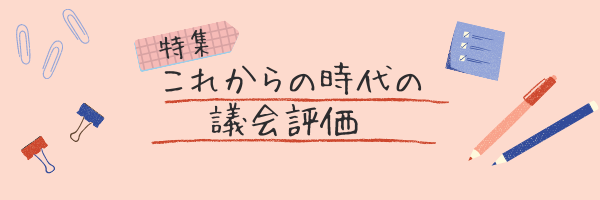従来の多様な議会評価
本特集で解説する地方議会評価(成熟度議会評価)モデルは、日本生産性本部の「経営品質向上プログラム」の考え方から多くの示唆を得ている。善き生産物(市場の商品であれ公共の政策(サービス等)であれ)は、善き経営によって産出されるものである。その経営の品質を評価するという発想である。研究会の成熟度議会評価(今回は全体像を明示できないが本特集で明らかになる)は、従来の(とはいえようやく始まっている)評価とは異なる。
筆者は、今日広がっている議会(議員)の政策法務を考えるに当たって、三つの視点・領域を想定している。議会による政策法務(条例等の監視・提言(議員・委員会提案条例))、議会への政策法務(自治・議会基本条例、会議規則等)、議会からの政策法務(法律等の改正、政府間関係の改革提案等)である。想定できる議会評価に当たって、これら三つの視点・領域を応用できる。
① 議会による評価A(行政の執行に関する議会の評価)
議会による事務事業・施策(・政策)の評価(地域政策評価)。議会・議員は事務事業・行政評価を行い、議会による監視や政策提言に生かすことである。こうした評価を踏まえて、地域経営の本丸である地方財政に議会・議員は主導的にかかわるようになってきた。総合計画へのかかわりも同様である。「議会による評価A」は、議会自体の評価ではないが、「議会評価」という用語からこの視点・領域をイメージする方もいるので、この文脈で説明している(正確には、成熟度議会評価はこの視点・領域を含む)。
② 議会による評価B(行政への監視・提言に関する議会の評価)
条例・財政等に関しての監視や提言の評価(地域政策評価)。議会(そして議員)による政策提言、実質的には政策条例数を評価することも分かりやすい。追認機関化してきた議会を転換させたイメージを広げるには大いに役立つ。
③ 議会への評価(議会の運営に関する議会評価)
自治・議会基本条例、会議規則等の評価(組織政策評価)。従来の議会評価ですぐに想定できるのは、議会改革を進めた議会基本条例の実際を評価することである。国政とは異なる地方自治原則を宣言した自治・議会基本条例が実際に機能しているかを問う。そして、必要があればその条例を改正することを目指す。
④ 議会からの評価(国・地方関係に関する議会評価)
政府間関係(国・地方関係)を評価し、意見書等の提出(地域政策・組織政策評価)。議会による政策監視・提言なので、「議会による評価A、B」と連動する(ここでは、議会による評価に含めて理解しておく)。
従来のこれらの議会評価は、改革を進める上で非常に重要なものであり、住民にとっても分かりやすい(不十分な点は後述)。説明責任を重視する議会にとって、これらの評価は活用できる。しかし、研究会による成熟度議会評価は、これらとは異なる。これらの評価は断片的であり包括的な評価が難しいということもあるが、より重要なことは、住民自治を進めるには議会からの政策サイクルを作動させ、それを評価することが必要ということである。
従来の議会評価の課題
成熟度議会評価モデルは、従来の議会評価を参考にしつつも、従来とは異なるものである。非常に大ざっぱにいえば、善き政策は善き組織(経営)が不可欠である。そのために、善き政策かどうかの評価は重要であるが、より重要なことは、組織(経営)を評価し、その改善を目指すことである。また、その組織(経営)評価に当たっては、事務分掌に当たる議会基本条例も重要であるが、動態的な組織(経営)に関する評価を目指す。日本生産性本部の経営品質向上プログラムを活用することが理解できるであろう。そこで、従来の議会評価と成熟度議会評価の異同を確認しておこう。
議会による評価A(行政の執行に関する議会の評価)は、議会からの政策サイクルにとっても第一級の位置を占める。とはいえ、政治的価値にかかわる。まさにこの評価を行うのが議会の役割であり、最終的には選挙によってその評価は示される。また、議会による評価を行うには、システムが向上しなければ充実しない。そこで、研究会は議会からの政策サイクルを強調している。
議会による評価B(行政への監視・提言に関する議会の評価)も、議会からの政策サイクルにとって第一級の位置を占める。議会が設定した目標、例えば明確な議員提案条例制定数等を設定して、その達成数(率)を評価する。明確な数値が設定されているために、評価は容易に可能である。しかし、アウトプットは容易であるが、アウトカム評価は困難であるというレベルにとどまらず、より評価にとって根本的問題が生じる。数値化される事項(条例数)に焦点が合わされ、数値化できない事項(議案審査等)は無視される。二元的代表制を踏まえた議会のあり方がそもそも確定していない(議員提案条例が賛美される風潮に乗った)評価項目となっている。ここでも、監視・提言を行うシステム評価が重要となっている。
議会への評価(議会の運営に関する議会評価)は、議会基本条例の条文を評価項目として評価を行うものである。地方自治原則は議会基本条例に刻印されている。そこで、条文を評価項目とするのは理解できる。静態的ではなく動態的に(したがって議会からの政策サイクルを)評価する。議会基本条例の条文を素材に評価する場合、到達点(評価基準)が明確ではないために、成果とは関係のない「取り組んでいる」ことが評価基準となることが多い。したがって、自己満足の様相を帯びる。評価基準が明確でないために、第三者評価を行っても同様である。議会からの政策サイクルという動態的視点から成熟度という基準を設定して評価する必要が浮上する。この評価は議会基本条例の改正に役立つ。
こうした従来の評価の問題点を踏まえ、新たな評価が模索されている。
一つは、政策立案と議会改革のそれぞれの目標を明確にしたミッション・ロードマップの作成とその評価である(大津市議会)(1)。これはいわば従来の二つの評価の接合である。目標としての政策立案は従来の評価の条例制定数と関連があり、目標としての議会改革は議会基本条例の条文評価と関連がある。両者の目標を明確にして、これに基づいた評価である。両者を視野に入れたことは重要であるが、すでに指摘した課題を内包することになる。
もう一つは、政策提言・監視の充実を目指して、それを目標に設定するが、それ以上に目標を実現する政策サイクルの構築に力点を置いた上でその評価を行う(飯田市議会、会津若松市議会、可児市議会)。政策提言は重要な役割として理解されているが、それ以上に監視機能が重視される。また、こうしたアウトプット、そしてアウトカムを充実させるシステム(議会からの政策サイクル)の構築と評価に焦点を合わせる。とはいえ、この評価の理論化はされていなかった。
成熟度議会評価モデルは、従来の評価、及び最近の評価の展開を意識して理論化している。
① 運用の評価:議会基本条例の理念と条文を意識する。
② 政策提言・監視の評価:議員提案条例は重要であり目標を設定することも重要であるが、首長提案の審議の充実が必要である。
③ 議会からの政策サイクルの評価:議会からの政策サイクルの水準により議会の政策提言・監視力が確定する。
従来のこうした評価を踏まえている。議会基本条例に明記された議会運営、議員提案条例数、住民参加制度の具体化等は、成熟度基準(「地方議会評価モデル」)を設定する際に活用している。それらを念頭に置きながら組織の行動指針や能力が評価対象になる。地方議会評価モデルは、成熟度によって議会評価を行う。