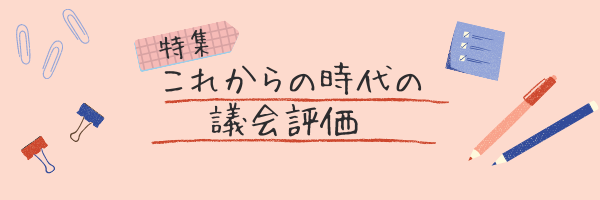地方政治研究者 江藤俊昭
議会評価の意義
人間であれ組織であれ、進化・深化するためには、冷静な評価を踏まえた改革が不可欠である。急展開している議会改革をさらに進めるためにも、その評価が必要である。そうした問題意識から、日本生産性本部「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」(以下「研究会」という)が設置された。その成果の一端を『議員NAVI』の「特集 これからの時代の議会評価」において紹介したい。その理論と実践については次回以降、現場から発信される予定である。
評価に当たっての視点を確認しておきたい。議会改革といっても、それ自体が目的ではない。住民福祉の向上に資することが目的である。そのために「議会からの政策サイクル」の構築を主軸に研究してきた。住民の意見を起点に政策提言する、議会からの政策形成サイクルから出発しながら、そのバージョンを上げたともいえる。通年や通任期、さらには期を超えた作動、政策提言を充実させるためには監視力を前提とすることも必要なこと(監視から政策提言へ)、その際、総合計画を軸に地域経営を考え、監視・政策提言を行う必要性が共有されている。議会は政策過程全体にわたってかかわり、地域経営の軸である総合計画を念頭に政策を考えることになる。議会改革を進めるために研究会では、名称を「議会からの政策形成サイクル」から「政策サイクル」に変更した。
研究会では、このシステムの構築とともに、そのバージョンアップを図るために評価手法の開発を目指した。このように、日本生産性本部に設置された研究会の議会評価の目的は、住民福祉の向上を実現するために、さらなる議会改革を進めることである。もう一つの目的は、住民自治革命ともいってよい。住民はその評価情報を知ることにより、あるいは自ら議会評価を行うことにより、政治参加を充実させることができる。つまり、議会が評価を提示する説明責任を超えて、住民自らが日常的な参加を充実させたり、選挙を意識したりするということを含んでいる。住民は、単なるサービスの対象者(消費者)を超えて住民自治を担う主体(市民)として登場する。
日本生産性本部は、「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」(顧問:北川正恭、座長:江藤俊昭)を設置し、研究を続けてきた(会津若松市議会、飯田市議会、可児市議会、大津市議会等)。第1期(2016年度)、及び第2期(2017年度)の成果を『地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会 報告書』(日本生産性本部、2019年)として上梓した。それを踏まえて、より実践的なモデル構築に取り組んだのが、第3期(2019、2020年度)の研究会である。3期の「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」は、モデルを構想する「議会評価モデル構築PT」(顧問・座長、先駆議会とともに、行政への経営品質向上プログラムに職員とかかわった津軽石昭彦関東学院大学教授(岩手県)、中道俊之早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員(岩手県滝沢村(現滝沢市))によって構成)と、それの提案を議論する「地方議会改革プロジェクト合同会議」によって構成されている。成果は、次の三つである。①議会プロフィール、②地方議会評価モデル(地方議会の成熟度基準)、③地方議会評価モデル(地方議会の成熟度基準)(要約版)。これらは、地方議会、地域社会の診断書(カルテ:①②③)であり、改革の処方箋(主に①)でもある。