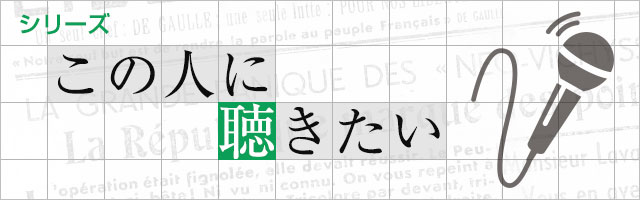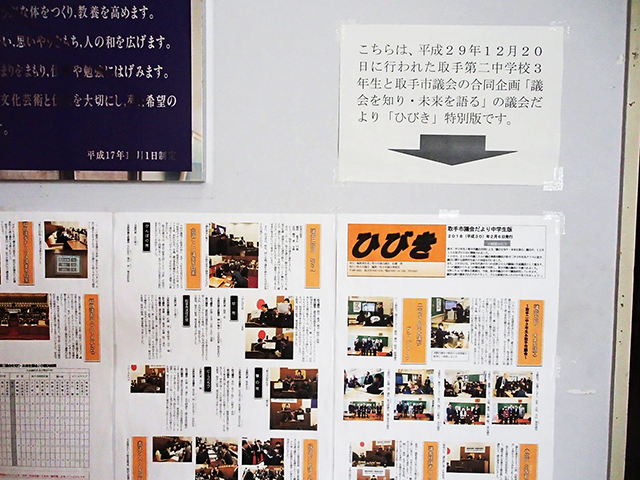──取手市議会は議会基本条例を制定(2011年12月)し、施行(2012年1月)しました。この間、広報広聴課に在籍していた岩﨑さんは2015年4月に、議会事務局に局長補佐として戻ります。このときはどんな心境でしたか。
正直にいいますと、うれしさ半分と悩み半分でした。目の前の状況をどのようにして収拾したらよいか悩みました。議会基本条例の規定にいろいろありまして、市民から「二枚舌ではないか」と批判されていました。
──つまり、事態を収拾するために呼び戻されたのですね。でも、議会事務局に“長”になっての復帰です。以前よりご自身がやりたいと思っていたことができるようになったのではないですか。
はい。私は、住民の皆さんが若いときから議会や議員に触れ合ってほしいと思っていました。「議会や議員なんていらない」という人がたくさんいますが、議会や議員のことを知らないからそういっているのではないでしょうか。子どもの頃から議会や議員のことを知るべきだと思うのです。たまたま市内の中学校の先生と知り合いまして、その方に中学校と議会のコラボレーションを提案しました。議会事務局が準備を全てやるので、社会科公民の時間をくださいとお願いしたのです。それで実現したのが、取手二中(取手第二中学校)の3年生と取手市議会合同による「議会を知り・未来を語る」特別授業です。
──これぞ主権者教育ですね。
私と係長(土谷靖孝さん)の2人が外部講師として中学校に赴き、体育館で3年生全員に議会や議員についての説明をしました。一昨年の12月のことです。後日、各クラスの代表生徒が来庁して議場で「未来への提言」を説明し、採決も行いました。
昨年12月の2回目は総合学習の一環として実施されました。議員22人と議会事務局職員5人が取手二中を訪れ、3年生の5クラスでそれぞれ出前授業を行いました。授業では議員1人ひとりが「なぜ、市議になったのか」を生徒の前で語り、その後、グループに分かれた生徒が「取手市を良くするために、取手の未来に向けた議案」を作成しました。生徒にはグループごとに会派名を付けてもらい、そこに市議と議会事務局職員も加わりました。グループごとに議案をクラス内で発表し、生徒のみならず、先生や議員、議会事務局職員ら全員による投票でクラス代表案を決定しました。そして、12月20日に本物の取手市議会議場で「模擬議会」が開かれました。議長選に始まり、議案の提案理由説明、討論、採決と本番同様に行われました。今年は市内の他の中学校ともコラボレーションしたいと思っています。
──話を聞いているだけで楽しくなりますね。
議員と議会事務局職員の協働の取組みは、互いの信頼関係があってこそのものだと思いました。それからもう1点。取手市の議会事務局職員は、労を惜しまず、自分たちでいろいろなアイデアを出し、かつ、工夫しながら新しい取組みを進めています。ワールドカフェ方式(「女性議員による意見交換会~ジャッジ・タイム&ワールドカフェで深める、誰もが働きやすい議会【取手市議会】」議員NAVI 2018年5月25日号を参照)の活用もその1つですね。
去年5月に岩手県北上市で開かれた議会事務局の研修会に自費で参加しました。そこでワールドカフェ方式による話合いを初めて体験して、これは素晴らしいと思いました。当日いただいた資料をもとに、自分たちもやってみたいと強く思いました。というのも、取手市では2015年に中学生の自死という重大事案が発生しまして、議会としてもいじめをなくすにはどうしたらよいか、真剣な議論を重ねていました。このような不幸な事案は二度とあってはならないと、総務委員会でいじめ対策に取り組んでいたのです。それで、まずは議員だけでワールドカフェ方式による対話を実施したいと思ったのです。取手に戻ってすぐに動きました。