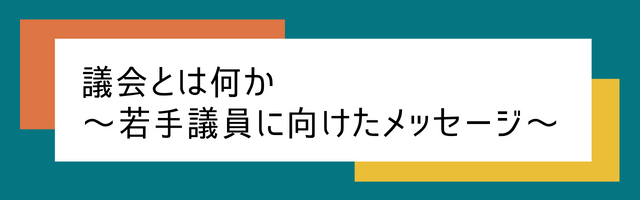全国若手市議会議員の会OB会事務局長/つくばみらい市議会議長 伊藤正実
全国若手市議会議員の会OB会で事務局長を拝命している茨城県つくばみらい市議会議長の伊藤正実です。私が当市議会で体験したことの中で、他の市議会でも導入することで議会の活性化の一助になるのではないかと思われる「特定所管事務調査制度」について紹介します。拙い説明ではありますが、ご拝読いただければ幸いです。
序
つくばみらい市議会では、常任委員会において、委員が所管事務調査事項の中から特定の事項を取り上げて、おおむね1年かけて独自に調査研究を行う「特定所管事務調査」という制度を導入している。他の議会でも同様な制度を導入されているところがあると聞く。つくばみらい市議会では「特定所管事務調査」としているが、例えば宮崎県小林市では、「年間テーマ」と称している。
このように、同様の取組みをされている市議会もあるが、まだまだ多くの市議会が取り組んでいる制度ではない。そこで、つくばみらい市議会の「特定所管事務調査制度」の仕組みと特徴について説明していきたい。
経緯
つくばみらい市議会では、7年前、市議会議員選挙が執行された後の議会から特定所管事務調査制度が導入された。
つくばみらい市議会には三つの常任委員会があるが、3委員会が同時に特定所管事務調査制度を導入したわけではなく、当初は一つの委員会で試験的に導入された。当時、つくばみらい市では小学校の統廃合の議論が展開されており、議会もその問題について議論していこうということになった。すると、委員の中から「それならば、委員会の所管事務調査事項であるから調査はもちろん可能であるが、それに基づいてさらに専門的に深く集中して調査をする『特定所管事務調査』によって調査するのはどうか?」との意見が出され、他の委員がそれに賛成してこの制度が始まった。
このときの特定所管事務調査制度の大まかな内容は下記のとおりである。
① 委員が自らタイトル、調査事項を決定する。
② 調査について、行政視察等は主に特定所管事務調査事項に費やすものとする。
③ 閉会中においても調査を行うこととする。
④ 最終報告書としてとりまとめ、議会に報告する。
⑤ 調査期間はおおむね1年とする。
以下、詳細を説明する。