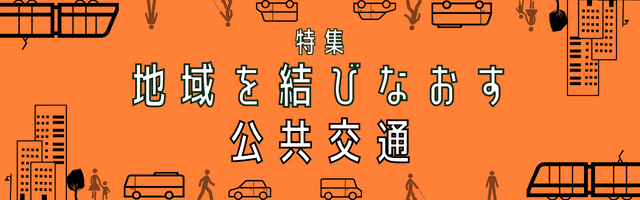國學院大学法学部教授 高橋信行
本格的な人口減少社会が訪れた今、地方だけでなく都市においても公共交通の存続が危ぶまれる事態となっている。いうまでもなく、地域の公共交通を維持することは住民のQOLを高めるためにも地域の経済を守るためにも不可欠である。自家用車での移動が可能である場合には問題は顕在化しないが、高齢者に対する運転免許の更新がますます厳格化しつつあることから、やがては高齢者が移動の手段を失ってしまい、日常的な買物や通院の面で深刻な不利益を受けることになる。さらには、移動手段を失った高齢者はより便利な都市部に移住せざるを得なくなり、地域の衰退に歯止めがかからなくなってしまう。
このような事態を避けるためには、公共交通の再生に急ぎ取り組むことが求められている。国土交通省も「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(以下「再生法」という)を改正することで、公共交通の再生のために従来以上に積極的に取り組んでいる。しかし、再生法の定めるスキームの下では、地方公共団体に中心的な役割が課されており、国はあくまで後方支援に努めることになっている。
また、従来から地域の公共交通は路線バスやタクシーといった民間事業者が担っていたが、人口減少が進む今、民間事業者だけでは公共交通を維持することは不可能となっている。そのため、様々な財政支援が実施されているが、より効率的で抜本的な対策が求められているといえる。
そこで再生法は、公共交通の抜本的な再編を進めるために、地方自治体に「地域公共交通計画」を策定する努力義務を課している。具体的な再編策は地域の実情に応じて様々に異なり得るが、基本的なポリシーは、地域全体の移動ニーズにきめ細かく対応するとともに、そのニーズに応じた交通手段の見直し、場合によっては「ダウンサイジング」を試みることである。