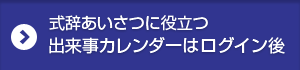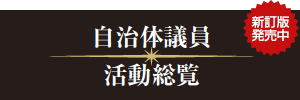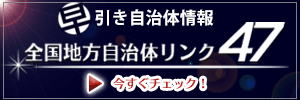滋賀大学客員研究員 提中富和
1 はじめに
今回は、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年3月31日滋賀県条例55号。以下「本条例」という)を取り上げる。本条例は、知事が指定する浸水警戒区域での建築規制を盛り込むことに対し、ダムを含む河川整備を進めれば条例の必要性はないのではないかという議論が巻き起こり、県議会でも継続審議扱いを繰り返した後に成立したという経緯があり、立法事実の検討の観点からは興味深いものがある。
2 条例制定の背景──
水害は社会現象である
(1)気象庁初の「大雨特別警報」で議論が過熱
ここ数年、「これまで経験したことのない大雨」が毎年のように日本各地を襲い、大きな被害が続出している。数多くの天井川が琵琶湖に流れ込む滋賀県においては、過去には多くの水害を経験したが、この50年ほどは大規模な水害はなく、「滋賀県は安全なところ」という観念が定着していた。そうした中、知事当局からの、想定外の大雨による水害が起きても人命を守るために必要だとする本条例の提案の動きに対し、「いつ起きるか分からない大雨のための規制よりも河川整備を先に行うべきだ」という反対論が浸水警戒区域の指定想定地の住民を中心に起きていた。その提案予定の前々日の2013年9月16日に、くしくも台風18号が近畿地方を襲い、気象庁始まって以来初の「大雨特別警報」が滋賀県に発令されるという事態が起き、河川の氾濫が相次ぎ、死者も出るなど大きな被害を受けた。「だから河川整備が先だ」、「いや条例が先だ」と議論を過熱させることになった。
(2)滋賀県の河川の特性
滋賀県は、中央に琵琶湖があり、県境は分水嶺をなす山地で囲まれているため、降った雨はほとんどが琵琶湖に注ぎ、瀬田川、淀川を通じて大阪湾に流出する。琵琶湖に流入する河川のうち80%が、長さ10キロメートル以下と短く急しゅんであり、洪水が起こりやすく渇水被害に見舞われやすいといった特性がある。この特性と水源山地の地質条件が相まって、土砂流出が起きやすく、天井川が多く形成されている。そうした中、人々の営みは琵琶湖からおおむね5キロメートル以内のJR沿線に集中し、これらの小規模河川が人々の生活圏を網の目のように流れている(1)。
なお、かつては琵琶湖自体も洪水であふれることがしばしばあり、そのため琵琶湖周辺の浸水被害と下流の淀川の洪水とを調節する目的で、瀬田川に洗堰が設置されている。大雨時の放流制限など難しい局面に対処している。
(3)氾濫原に住まうという認識の消失
人々の住まない、人々の営みが行われないところに、どんな洪水が起きても、水害は起きない。ところが、日本では、人々の多くは、河川が氾濫を繰り返して形成された沖積平野に住み、営みを続けている。近代科学技術によって洪水を封じ込めようと企図するまでは、人々は、洪水は起きるものとして、洪水と付き合ってきた歴史がある。滋賀県内には、その歴史を示す、自然遊水地、霞堤、二線堤などが数多く残っている。
自然遊水地は、その地域内で最も浸水しやすい低い土地であり、洪水時には遊水機能を果たし、集落内への浸水を防いできた。以前は、周辺住民がこういった遊水機能を認識し、また一部地域では集落の共有地とされ、宅地化されることはなかった。霞堤とは、堤防のある区間にわざと開口部を設け、洪水時には開口部からあふれ出した洪水が上流方向の自然遊水地に逆流するように計画され、その自然遊水地に洪水を氾濫させて湛水させ、下流域に流れる洪水の流量を減少させる構造の堤防をいう。洪水の後には、湛水した水は河川に戻っていく構造となっている。二線堤とは、堤防が決壊した場合などに洪水氾濫の拡大を防ぐため、堤防の背後(堤内地側)につくられた2本目の堤防をいう。このような、水害を最小限に「とどめる」という、先人の知恵が生かされていた。
ところが、土木技術が進歩し、洪水を河道内に閉じ込めることが当然視されるようになり、人々は氾濫原に住まうという認識を消失してしまったかのように、普通の自然遊水地だけでなく霞堤の自然遊水地でも宅地開発が進んだりしてしまっている。二線堤が圃場整備に伴い撤去されることもある(2)。
(4)洪水を封じ込める河川政策と行政依存の助長
1896(明治29)年の河川法制定以降、近代の河川政策は、洪水を河道内に閉じ込めて、水害をなくすることを目標にして、堤防を高く積み上げ、河川を深掘りするという方針をとっていくことになる。その方針は、「何年に1回の大雨」といった表現で流量を表し、その流量を河道内に閉じ込めて流すことができるかという流量計算主義に基づいている。この流量計算主義は、治水と利水の両面から流量調整を行おうとする、1957(昭和32)年制定の特定多目的ダム法による多目的ダム政策や、1964年の河川法改正により確固たるものとなっていく。そこでの「安全度」は、個々の河川施設の「治水安全度」をいうようになり、住民のためというより、河川管理者のための指標となった(3)。そのため、住民の防災意識は衰退し、行政依存の体質を強めることとなる。
そこでは、堤防から洪水があふれ出し、河川が氾濫したときのことは想定されなくなり、水害による被害は「ないこと」が目標であり、被害を最小限に「とどめる」という思考は遠のいてしまう。住民に対し河川が氾濫することのリスクを言い出せば、行政への責任追及となりかねず、行政当局はリスク情報の開示すらできないという状況も生まれる。そうした中で、大雨時には、自治会役員が夜を徹してでも堤防を見回ったり、危険時には半鐘を鳴らし避難を伝えるといった、自治会自らが水害に「そなえる」という伝統も、失われつつある。
なお、滋賀県では、現在、全国で進められている当面の河川整備の目標である10年に1回の大雨(時間雨量50ミリメートル)で0.5メートル浸水する(つまり床上浸水の被害が起きる)のを防ぐための河川整備を計画的に進めているが、現在の進捗率は56%で、河川整備のための予算は毎年縮減されるばかりで、現在の年間45億円の予算規模では、完了するのに今後130年もかかるという。さらに、こうした河川整備が完了したとしても、時間雨量50ミリメートルを超える大雨が降った場合にはあふれてしまう。水害による被害をゼロにすることは、そもそも無理なこととなっている。
(5)「川の外」の政策の必要性
洪水を「川の中」に閉じ込めることが完全にできないのであれば、「川の外」での対策を考えなければならない。アメリカやイギリスでは、都市計画において、洪水ゾーンが設定され、土地利用規制が当然のごとく行われている。日本でも、建築基準法39条により、条例で「出水等による危険の著しい区域」を「災害危険区域」に指定し、当該条例で「住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要な」規制を行うことができる。また都市計画法7条により市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるに当たって、同法施行令8条1項2号ロの規定により溢水や湛水による災害発生のおそれのある土地の区域を市街化区域に含めないことができるとされている。しかし、そうした出水や溢水や湛水のおそれのある土地は、地価が安価なこともあり開発の圧力が高く、その圧力に押されて、こうした法制度を活用することが、一部の自治体を除き、できてこなかった(4)。そこには、出水等のおそれを裏付けるための、水害の記憶の保存や水害リスクに係る基礎的な情報が不足していたことなども原因している。