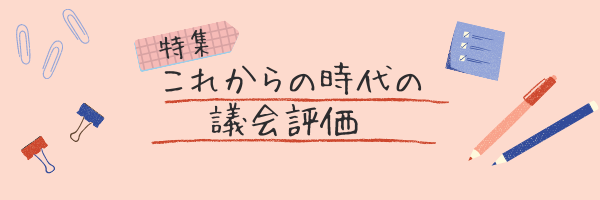日本生産性本部・地方議会改革プロジェクト
前回(2021年3月25日号)の「議会の価値創造を『見える化』する~地方議会評価モデルの挑戦(上)〜」では、議会の「状態」を包括的に点検する「地方議会評価モデル」と、議会の進むべき方向性を明らかにする「議会プロフィール」という二つのツールについて、基本的な考え方の枠組みを述べた。
今回はその開発背景や具体的な使い方、そして現在の取組状況等について紹介したい。
1 高まる評価機運、手法は手探り
2021年3月29日、日本生産性本部・地方議会改革プロジェクトがオンラインで開催した「地方議会評価モデル」の活用法に関する説明会。年度末の日中にもかかわらず、全国50議会から総勢100人近い参加を得た。
議会改革をどのように進めていくべきか。政策サイクルや理想的な姿をどう実現するか。議会評価をどう取り入れるのか。画面越しでも参加者の熱量が伝わってくるほど、皆が一様に真剣な面持ちで聞き入っていた。
「議会を評価しよう」という機運は、議会改革の進展に伴い、昨今、確実に高まっている。すでに自己評価や外部専門家による第三者評価など、取り組む議会も数多くあり、手法や基準は様々展開されている。
だが、ある議会からは、こんな率直な不安の声が聞かれた。
「自分たちの評価のやり方で、本当に住民のためになっているのだろうか」
議会評価の確固たる手法や基準は確立されておらず、皆が手探りを続けているのが現状ではないだろうか。
2 議会版の「経営品質」をつくろう
2020年6月に公開した「地方議会評価モデル」と「議会プロフィール」は、足かけ5年、学識者、先進議会をはじめとする有志の議員・議会事務局職員の力を借りて、開発に取り組んできたものである。
その出発点となったのは、2014年、ある地方議会の事務局長から届いた連絡だった。
「議会に『経営品質』の考え方を取り入れられないだろうか」
日本生産性本部が旗振り役となり、25年にわたって普及に努めてきた組織経営の理論「経営品質の向上」(1)は、顧客価値を中心に据えて経営革新を目指すものだ。その考え方に基づいた、組織におけるプロセスと活動結果の一体的評価は、現在までに、多くの企業組織だけでなく、三重県、岩手県、高知県、京都府、政令指定都市では横浜市、京都市、神戸市、川崎市といった地方自治体の行政経営においても採用されてきた。「その議会版をつくることはできないか」という提案は、事務局長自身が、行政の経営品質の向上に取り組んできての手応えからだった。
日本生産性本部は、生産性向上を通じた社会経済システムの改革という活動目的から、地方自治体の経営の質を高める支援事業にも取り組んでいる。それゆえ、地方議会における長年の慣習や議事機能の形骸化など、課題が山積していることも目の当たりにしていた。地方分権の時代、二元代表制の一翼を担う議会の改革は必要不可欠だ。だが、「現実には難しいのではないか」というのが当時の私たちの偽らざる本音だった。
3 会津若松の衝撃──「議会は変われる」
そんな懐疑論を一掃したのが、福島県会津若松市議会との出合いだ。
現地視察では、新鮮な驚きの連続だった。そこでは、議員たちが会派を超えて、チーム議会として一つになっていた。議員が住民の意見をしっかり聞き、議会として住民の声をまとめ上げ、政策提案する政策サイクルが回っていた。
「すごい議会がある」
「地方議会でもここまでできるのか」
会津若松市議会で受けた衝撃は、「議会は変われる」という確信にすぐに変わった。
地方議会評価モデルと議会プロフィールの開発の土台を担ってきたのは、早稲田大学マニフェスト研究所と2016年より開催している「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」(顧問:北川正恭・早稲田大学名誉教授、座長:江藤俊昭・大正大学教授)である(2)。また、具体的な設問や項目の設計に当たっては、学識者、研究会メンバーからなるプロジェクトチームを結成し、徹底的な議論を重ねた。
研究会における議論の成果は、2019年に発行した「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会報告書」(1冊税込2,000円)に詳しいので、参照してみてほしい(https://www.jpc-net.jp/consulting/mc/pi/local-government/parliament.html)。