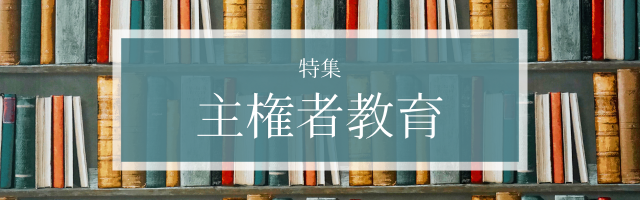9 取組みを振り返って
(1)全体として
授業は、各学校の10月18日の「子供議会」に向けて、準備が本格化する段階での実施だった。そのため、その後の各学校の「議員選出」や「子供議会」での「提案内容」の協議まとめなどに、参考にしてもらえた。
各校の子ども議員は代表2人。どうしても選ばれた子によるという雰囲気になりがちだ。しかし今回の取組みで、議員が全児童に関わったことで、教育委員会や学校側も、「主権者教育」としての意義を大切にしてくれた。例えば、「子供議会」本番も、全校に同時配信を行い、小学6年生・中学3年生は全員傍聴した。議員側の思いや願いをしっかりと受け止め、素早い対応であったと感謝している。
(2)小学6年生
議員の存在を身近に感じてくれた。ふだん「どこかで見た」、「あの人は知っている」そんな人が、議員としてどんな思いでいてくれて、自分や家族が住む「町」のために、どう頑張ってくれているのかを知ってくれた。議員の個人的な質問(家族は、好きなものは、など)にとどまることなく、「町の良さ」、「町の課題」などについても質問が出るなど、一人ひとりが町のことを考える学習になってくれた。また、目の前にいる人が、「選挙」という方法で議員になったという仕組みを知る機会にもなったようだ。
(3)中学3年生
授業の時期として、「子供議会」への実践だけでなく、「公民」という教科で、具体的に地方自治や自分たちとの関わりを学ぶ前だった。そうした点から「公民の授業展開の前に、理解を深められた」、「議員や議会を肌で感じられた」、「これまで議会や政治にあまり興味がなかったが、議員の話を直接聞いて興味が湧いた」等の感想をもらった。地方自治・議員を身近に感じてもらえる大切な機会になってくれた。
「社会科」の授業であったわけだが、教科担任制ということもあり、先生方の姿勢には頭が下がる思いだった。ポイントポイントで、「みんなはこの後、こういう観点で学んでいくのだね」など、適切な議員への質問や確認、今後へのコメントをしてくれた。町の各種計画・指針などを用意・理解してくれていて、生徒に、議員とのやりとりのタイミングを見て提示してくれた教師もいた。生徒たちの「子供議会」後の「発展学習」にも大いに期待できる授業となった。
(4)教育委員会・学校
議会と執行部としての教育委員会・学校は、どうしても「厳しいやりとり」も必要になる。しかし、町の未来を担う子どもたちの育成という点で思いは同じである。今回の実践は、議会側からの一方的な「準備をしてくれ」、「こういう段取りをつけてくれ」という姿勢ではなく、議会側からの「こういう実践をしたい」、「議会自ら動きたい」という思いから実現した。そして教育長・教育委員会・学校は、「子供議会」の準備という大変な作業の中だったが、「子どもたちにとって大切な機会になる」と、議会の思いを受け入れてくれ、日程調整などを行ってくれた。議員の訪問・視察というある面「形式的な訪問」ではなく、授業をともに実践するという姿勢になってくれたことは、大きな実績となった。
(5)議員にとって
準備段階で、議員からの異論等は全く出なかった。「地域に関わりたい」、「地域のことを知りたい」という思いは共通である。さらに「子どもたちを大切にしたい」、「議員として子どもたちの未来を大切にする思いを形にしたい」との思いも一致しているからだろう。
子どもたちからの質疑応答では、選挙費用や支持者との関係、日常の仕事や報酬についてなど多くの質問が出た。また、今の小川町の状況や方向性、進んでいる事業内容や計画についてなど、活発な質問や要望も出た。各議員がそうしたことに、分かりやすく丁寧に答える機会となり、自らの議員としてのあり方や考え方の整理・確認ができ、今後の活動に活かせる貴重な機会となった。
10 今後の課題
「子供議会」とリンクしての実践のため、数年に一度の「子供議会」実行時の「単発的な活動」となってしまった。授業での実践であったことを考えれば、授業(小学校6年生の社会・中学3年生の社会公民)の計画に毎年位置付けてもらうことも、決して無理なことではないように思われる。授業時数の削減や負担を増やさないという観点は大切にしながら、「議会自らもしっかり動き準備する」という基本的な姿勢を持って、教育委員会と改めて検討協議を考えられればと思う。
現在、小川町議会では、月1回の議員意見交換会懇談会の実施を中心に、様々な角度からの「議会改革」、その中核としての「住民との関わり」を本格的に議論している。今回の実践についても、「定期的に実践すべき」との声も出ている。今後、しっかりと協議できればと強く思う。