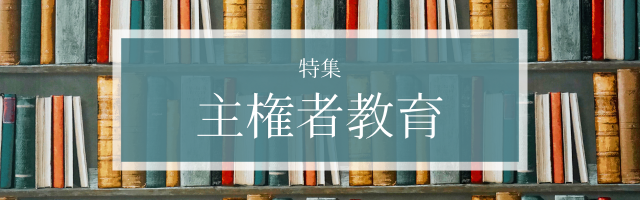地方議会だからこそできること
前述した「学校の取組としての工夫」のように、地方議会議員と中学生・高校生が意見交換を行い、そこで出た意見をきちんと施策に反映しているという事例は多々ある。しかも、中高生に議会に来てもらうだけではなく、議員自ら学校に出向く=アウトリーチを行う、というのが重要である。もちろん、議会側が学校側に働きかけて、学校に出向こうとしても、教育委員会からストップがかけられるという事例があることは承知しているが、有権者ではない中高生であっても、そのまちで生活している一市民であり、主権者である。また、その中高生の保護者は有権者であり、市民である。どうして、市民を代表する議員が、市民であり、主権者である中高生から意見を聴いたり、意見交換をする機会を教育委員会や学校現場に拒否されてしまうのか。この状況に、地方議会はもっと問題意識を持つべきである。
選挙を通じて社会課題に目を向けさせる工夫を行うことは当然であるが、選挙のときだけ主権者教育に取り組めばよいわけではない。日常を過ごしている学校の中で、民主主義を体感し、民主主義とは何かを考え、子どもの声が反映された学校運営がされることが、主権者意識を育むために不可欠なのはいうまでもない。生徒自身が学校を構成する一員と実感することが社会参画の一歩であり、エージェンシーを発揮できるシティズンシップ教育が求められている。
20年以上も前にロジャー・ハートは「子どもたちは、直接に参画してみてはじめて、民主主義というものをしっかり理解し、自分の能力を自覚し、参画しなければいけないという責任感をもつことになる」(8)といっている。2022年4月1日から18歳成年時代を迎え、2023年4月1日からこども基本法が施行となったことを踏まえ、選挙権の行使のみならず、子どもたち自身が一人の主権者としての当事者意識を持ち、主体的に社会・政治に参加することの自覚を深めることが不可欠となる。
もちろん、政治的中立性の視点から、学校現場が政治との距離に戸惑っている事実もある。しかし、生まれたときから(赤ちゃんであっても)私たちは主権者である。子ども時代から、平和で民主的な国家及び社会の形成者としての自覚が意識づく環境にあるのかどうかが、問われている。何よりも、教職員自身が主権者として民主主義に向き合い、実践することが重要である。
10-20代といった若年層の投票行動が選挙結果に影響を及ぼしつつある中、地方議会議員は何をすべきなのか。教育現場が率先して主権者教育に取り組める環境整備を後押しするとともに、地方議会議員としてできる主権者教育とは何かを意識し、地方議会として主権者教育に真剣に向き合うべき時期に来ているのではないだろうか(9)。
(1) 朝日新聞社が衆院選投開票日の10月27日に実施した出口調査に基づき分析した、年代別の比例区投票先より(https://www.asahi.com/articles/ASSBX357QSBXUZPS001M.html)。
(2) 今回の模擬選挙で模擬選挙推進ネットワークに結果が寄せられたのは、中学校7校、高校14校、大学3校、地域1か所の、合計25校/か所で、総計3,736票(うち無効/白票60票)の投票となった。詳しい結果については、「【投票結果】第50回衆議院議員総選挙における模擬選挙の結果(2024/11/07)」参照のこと(http://www.mogisenkyo.com/?p=1039&preview=true)。
(3) 「兵庫県知事選でも影響力増すSNS 識者『若年層へアプローチ成功』」朝日新聞デジタル2024年11月18日(https://www.asahi.com/articles/ASSCK41QBSCKPQIP03XM.html)。
(4) 公職選挙法が改正されるに至った背景については、林大介『「18歳選挙権」で社会はどう変わるか』(集英社新書、2016年)参照。
(5) 総務省・文部科学省『私たちが拓く日本の未来』(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/01.html)。
(6) 「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1366835.htm)。
(7) 文部科学省「主権者教育(政治的教養の教育)実施状況調査」。
〈平成28年度(2016年度)実施〉http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/14/1372377_02_1.pdf
〈令和元年度(2019年度)実施〉https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shukensha/mext_01114.html
〈令和4年度(2022年度)実施〉https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2023/mext_00119.html
(8) ロジャー・ハート(著)、木下勇ほか(監修)『子どもの参画─コミュニティづくりと身近な環境ケアへの参画のための理論と実際』(萌文社、2000年)2頁。
(9) 学校におけるシティズンシップの現状については、林大介「シティズンシップを育む学校教育」末冨芳(編著・監修)、秋田喜代美=宮本みち子(監修)『子ども若者の権利と学び・学校』(明石書店、2024年)第9章、181?207頁参照のこと。