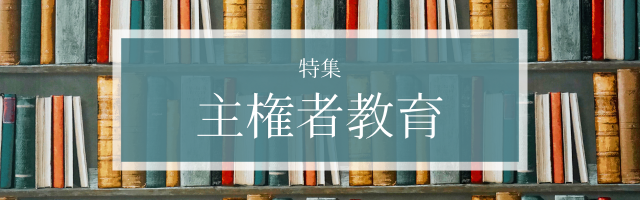主権者教育の改善に向けて
その一方で、同報告書(概要)では、「参考となる具体的な取組例〈学校の取組〉」として、以下のような事例を挙げている(下線部は、報告書(概要)内で太字で強調されている部分)。
〇県外から移住してきた方、町内で働いている外国人研修生など町民を招いて話を聞き、グループで地域の課題の解決につながる提案を考えた。その際、町議会議員に協力を得て、質問内容に関する助言や質問の形式等について指導を受けた。作成した質問通告書を基に、生徒は模擬議会で町長に対して一般質問を行った。質疑内容を受けて、公園のトイレの洋式化などいくつかの施策が実現した。
〇教育委員会が、県議会議員と高校生の意見交換会を開催している。実施校は、生徒との意見交換、地域課題に関する学習成果発表に対する助言など、各校での学びに応じた内容を、教育委員会と協議のうえ決定する。教育委員会から連絡を受けた県議会事務局は、全ての会派に打診し、参加する議員の調整を行う。その際、学校の所在する選挙区以外の議員が対応するよう留意している。
〇選挙期間中に、全学年で実際の選挙を活用した学習活動を行っている。事前学習として、実際の候補者・政党の情報を生徒自らがHPから調べる。その際、生徒には、3つ程度の特に関心の高い分野を選ばせ、各候補者・生徒の主張を比較して整理するようにさせた。なお、学習活動の実施に当たっては、全ての候補者・政党を公平に扱うとともに、様々な政党があることを生徒に伝えている。
〇生徒会長の呼びかけの下、校則や行事のルールの見直しに関心をもつ生徒により委員会が組織された(教師も立候補により参加)。生徒や教師、地域の方々へのインタビューもしながら見直し案を検討。その提案内容は、ホームルーム活動での検討事項としても扱い、全ての生徒が自らの意見をもつとともに、他者の意見を尊重し合意形成を図ろうとする経験を積めるようにした。
「主権者教育に関する課題(例)」を前述したが、このように、
・実際の議員を学校に招いて、生徒と意見交換を行う
・その際の調整を、議会事務局のみならず、教育委員会が担っている
・選挙期間中に、実際の選挙を活用した取組みを実施している
・校則や行事のルール見直し等、身近な民主主義について考え、意見表明し、合意形成する機会を設けている
といった主権者教育に取り組んでいる学校もある。
A先生だからできる、B高校では難しい、C県だからできる、というレベルではなく、その気になればどこでもできるのである。もちろん、各学校や各自治体の事情もあり、同様に取り組むことができるとはいわないが、やろうとするかどうかである。教育現場が「総論賛成・各論反対」で取り組まない言い訳をいっているだけでは何も進展しない。