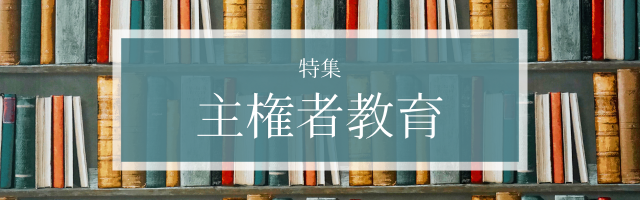「社会参画」が期待される18歳選挙権時代~「民主主義の担い手」に求められる力~
2015年6月に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳に引き下げられた(4)。これを機に総務省・文部科学省は、高校生向け副教材『私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるために』(以下「副教材」という)を2015年9月に作成した(5)。
副教材では、「公共的課題の解決に向けて多様な価値観をもつ他者と議論しつつ協働する国家・社会の形成者」=「民主主義の担い手」と位置づけ、次の四つを「国家・社会の形成者として求められる力」として掲げた。
○論理的思考力(とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力)
○現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に判断する力
○現実社会の諸課題を見出し、協働的に追究し解決(合意形成・意思決定)する力
○公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度
そして〈話し合い活動〉を中心に、〈模擬選挙〉や〈模擬議会〉〈模擬請願〉など、実際の政治的事象を授業の中で取り上げ、社会課題について考え判断することを求めている。特に、これまで“生々しい”といった理由で敬遠されがちだった実際の選挙を題材にした〈模擬選挙〉を含め、実際に国会等で議論となっている法案や、各政党の考え等を授業として扱うことを推奨していることは評価すべきである。
また文科省は、2015年10月に「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(6)を発出した。〈未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請〉されていた時代から、18歳選挙権によって〈国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待〉され、〈自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが重要〉な時代へと移った。子ども時代から社会課題について考え、「賢い有権者」「考える市民」を育てることに文科省は180度方向転換した。