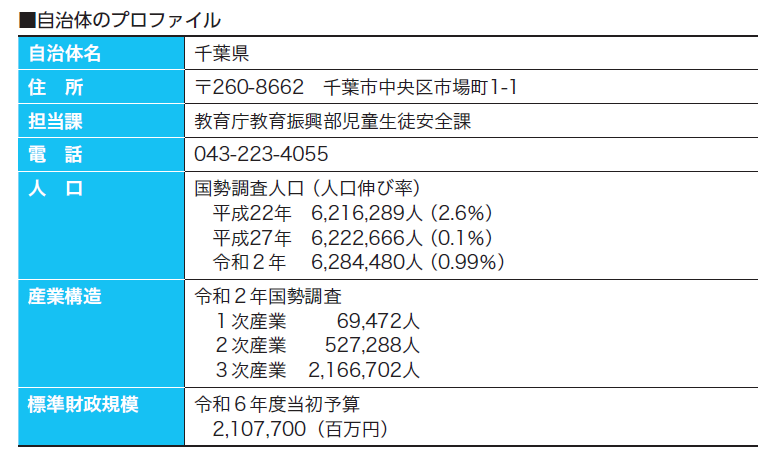2 条例制定による効果
本条例の施行を受け、県教育委員会において、県及び市町村の関係者、小中学校の校長、保護者、フリースクール関係者並びに学識経験者の15人で構成する「千葉県不登校児童生徒支援連絡協議会」(以下「連絡協議会」という)を設置し、本条例に基づく基本方針の策定に向けた議論により、原案をまとめ、パブリックコメントを経て、令和6年3月29日に基本方針を策定しました。
この基本方針は、県内各所の教育支援センターやフリースクール等の民間の団体の活動をはじめとして、これまで多様な教育機会を確保する上で先駆けとなった取組に加え、校内教育支援センターの充実、学びの多様化学校の新設、そして既存の学校自体も必要な改善を加えていくなど、これらを有機的に結びつけて、子どもたちが、その個性を尊重され、自分に合った学びを継続できるよう、その具体的な取組の方針を示すものです。
条例の理念を具現化する効果的な施策を検討するため、令和5年12月から令和6年1月にかけて、不登校児童生徒及びその保護者や、県内で活動するフリースクール等の民間団体・施設を対象とした実態調査を実施しました。
この調査では、不登校となる要因や支援ニーズのほか、フリースクール等の民間団体の活動の実態、学校や家庭との連携状況、運営上の課題などに関する項目について、集計・分析を行いました。
3 今後の課題や運用上の留意点など
今年度は、連絡協議会における議論を踏まえて策定した基本方針と実態調査によって得られた基礎資料を二本柱として、新たな支援に取り組んでいます。
まず、令和6年6月から、不登校児童生徒の状況に合わせた多様な学びの場の充実を図るため、中学生を対象としたオンラインによる授業配信を開始しました。オンライン授業では、チャット等を活用し、生徒からの質問に答えたり、生徒の理解度を確認しながら授業を進めています。
また、学校に通うことのできない児童生徒の社会的自立に向けて、重要な役割を担っているフリースクールについては、学校や市町村教育委員会との協力体制を構築する調査研究事業を新たに実施し、不登校児童生徒の教育機会確保に向けた経済的支援のあり方について検討を行うこととしています。
さらに、子どもや保護者等の困りごとの解決につなげるため、電話やSNSなど様々な方法で実施している教育相談に、新たにオンライン相談を加えるなど、支援体制の整備を図っています。
一方で、不登校児童生徒数が増加するスピードに支援が追いついていないという指摘もあります。今後は、質、量ともに学校以外の教育の場を充実させていく必要があり、そのためには、本条例の基本理念である関係者の密接な連携が重要です。
公的施設である教育支援センターや学びの多様化学校(不登校特例校)の整備を進めるとともに、民間のフリースクール等とも相互に協力・補完することで、不登校児童生徒一人一人の状況に応じた教育機会の確保に努め、本県の不登校児童生徒を誰一人取り残さないという強い決意の下、将来の社会的自立に向けた支援に取り組んでいきます。
〇千葉県不登校児童生徒の教育機会の確保を支援する条例