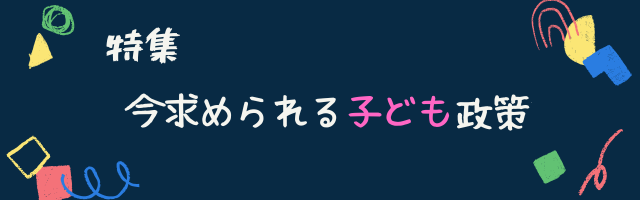6 当事者が声を上げることが「社会参画」につながる
私たち大人は「大人に言っても聞いてくれない」と諦めさせたり、せっかく子どもが自分の意見を伝えても「なに生意気を言っているんだ、小学生のくせに」、「中学生は勉強していればいい」と否定的にすべきではない。校則も含め、子どもが生活している身近な環境において、その環境をよくしていくためにどうしたらよいのか、どのようにルールを変えたらよくなるのか。子どもたちが、安心して自分の思い(Views)を伝え、そして、聞いてもらえる経験を、子どもにとって身近な地域の中でこそ、きちんと保障することが重要である。
住民であり、市民であり、主権者である子どもに対して、一人の人間として子ども時代から地域づくり、社会づくりに関わることが、市民性の意識を醸成することにつながる。子ども・若者の力をまちづくりに生かすことは、民主主義を実践することとなる。まさに、「地方自治は民主主義の学校」(J・ブライス)である。
だからこそ、地方議会議員は、これまで以上にそのまちの市民であり主権者である子どもの声に耳を傾け、子どもの声を施策に反映していくことが求められる。
(1) こども家庭庁「こども基本法」(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/)。
(2) 内閣官房「こども政策の推進(こども家庭庁の設置等)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/index.html)。
(3) 「地方自治と子ども施策 全国自治体調査」は、全国の都道府県・市町村において、子どもに関わる施策の推進状態を把握し、「子どもの権利条約」の視点から今後の課題を明らかにし、次の展開を開くことを目的に実施された。対象は全国の都道府県・市区町村の1,796件、調査時期は2017年1月22日~2月29日、有効回収数は705件で有効回収率は39.2%。調査の詳細は、内田塔子「全国自治体調査にみる『子供にやさしいまち』づくりの特徴と評価・検証の視点」子どもの権利研究28号(2017年)200~215頁参照。
(4) そのほか、早稲田大学卯月盛夫研究室・NPO法人わかもののまち「子ども議会・若者議会 全国自治体調査 報告書」(2019年5月)(https://wakamachi.org/2019/06/11/report/)によると、「子ども議会・若者議会(類似する事業を含む)」について、34.2%(409自治体)の?治体が現在「取り組んでいる」と回答し、「過去に取り組んでいた」は23.6%(282自治体)、「取り組んでいない」は42.2%(505?治体)。子ども・若者からの提案・提言を受けて、実際に自治体の政策に盛り込む、あるいは実現に結びつけているのは25.6%(162自治体)で、半数以上の自治体が子ども議会・若者議会の実施回数「1回のみ」。
(5) 「人口流出・少子化が進み、存続できなくなるおそれがある自治体」のことを指す。民間の有識者らでつくる日本創成会議(座長・増田寛也氏)が2014年に指摘したもので、厳密な定義は「2010年から2040年にかけて、20~39歳の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村」である。
(6) 「子どもにやさしいまち」については、内田塔子「ユニセフ『子どもにやさしいまち』づくりの社会的背景とその特質」ライフデザイン学研究8号(2012年)39~62頁参照。
(7) 内田・前掲注(6)参照。