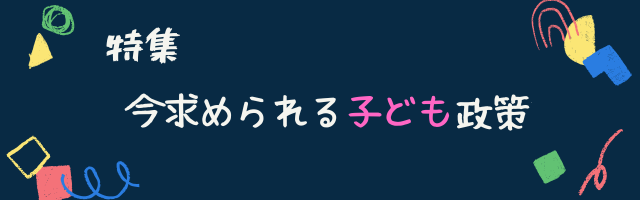2 こども基本法によって自治体が取り組まなければいけないこと
こども家庭庁には、特別の機関として内閣総理大臣をリーダーとする「こども政策推進会議」が置かれ、こどもの意見を取り入れながらこども施策の基本的な方針(こども大綱)をつくることが、9条(こども施策に関する大綱)で定められている。
そして、この基本的な方針を基に、都道府県や市町村が「こども計画」をつくり、社会全体でこども施策に取り組むことが求められている。つまり自治体は、こども基本法の理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の自治体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有し(5条)、都道府県こども計画、市町村こども計画(10条)を策定することが求められる。
とはいえ、こども施策における地方行政計画は、「子ども・子育て支援事業計画」、「子どもの貧困対策についての計画」、「子ども・若者育成支援計画」等が、個別法に基づいて地方行政計画においてつくられてきている。今後は、こども施策の基本理念の下、こどもの権利保障を推進するための計画目標を定め、各計画の終わりがそろう時期等を目途にして、一体として一つの計画にすることが、こども基本法制の意義に即した対応となる。
その際には、当然のことながら、11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)にあるように、当事者であるこどもの意見を反映することに留意する必要がある。
3 自治体における子どもの意見表明・参加の実態
子どもの権利条約総合研究所が2017年1月~2月にかけて実施した「地方自治と子ども施策 全国自治体調査」(3)によると、「子どもを主たる対象にした計画を策定する際、子どもの意見を取り入れている」自治体は11.4%、「取り入れていない」自治体は81.8%であった。「子どもに関わる施策を全庁的に調整する組織がある」自治体は、「各部課が独自に推進する」自治体に比べ、まちづくりへの「子ども参加」の割合が5倍近く高い結果となった。
子ども参加を促進するために必要なこととしては、「学校教育以外でも子どもに関する施策はあるため、必要に応じて子どもの意見を聴く」59.4%、「学校教育などの場面で、子どもの意見を尊重する」54.2%であり、学校教育及び学校教育以外のあらゆる場面において、子どもの意見を尊重することの必要性を感じている自治体が過半数を超えている(4)。
たとえ18歳未満の子どもであっても、権利主体として自分が生活する社会に参加し、自分たちが望むまちのあり方に意見表明し、施策の決定に影響を及ぼすことができることは、参加した子ども自身の成長に大きな影響与えるのである。
だからこそ、“消滅可能性自治体”(5)として指摘され、危機感を抱いた自治体においては、そのまちで暮らす子どもや若者自身に、まちづくりへの参加を積極的に求める取組みに力を入れている。例えば、地方議会議員や行政職員が小学校や中学校にまで出向き、子どもとの意見交換や対話を重ね、子ども会議・子ども議会を開催することで、そのまちが抱えている課題を子ども世代とともに考え、改善につなげようとしている。たとえ進学や就職のために、自分が生まれ育ったまちからその後離れたとしても、子ども時代に主権者としてまちづくりに関わった経験があれば、自分のまちに対する思いを馳(は)せ続けよう。そして、ゆくゆくはそのまちに戻ってきたり、ふるさと納税の対象とするなど、自分が育ったまちの将来を考える人を育てることにつながるのである。