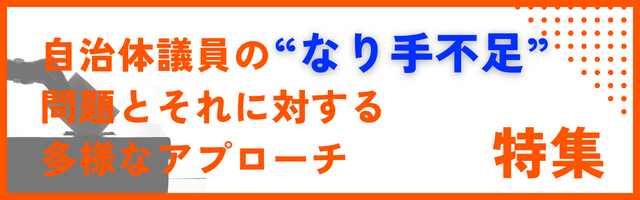第3の候補擁立の可能性も視野に入れた市民マニフェストの策定
最初の市民マニフェストは、公開討論会で納得できる答えをどの候補者からも得られなかった場合には第3の候補を擁立する可能性も含めて、その際の選挙のマニフェストとなるように政策の各分野を網羅したために、百数十項目にわたる大部な政策集になった。
このときの市長選は、初挑戦した泉房穂氏と前市長の3選を阻もうとしていた職員幹部や市議会多数会派が擁立した県の県民局長との対決になり、政党推薦を受けず「市民推薦候補」を自称した泉氏に対して、自・公や民主など大半の政党が推薦し知事が全面支援する県民局長が優勢との見方が大半だった。
ところが、選挙告示日の1か月前に開いた公開討論会には、当初は出席するはずだった県民局長は欠席し、泉氏一人の出席になった。通常の「候補者公開討論会」は、候補者側からの一方的な公約や政策を聞くだけだが、市民マニフェスト選挙は「市民が実現してほしい政策」に対して候補者がどういう姿勢を示すかを明らかにし、市民と意見交換する機会を提供する場だから、出席者が一人でも成立する。討論会では、泉氏は一人で2時間余りの討論をこなし、市民マニフェストには「おおむね賛成だ。実現に努力する」と答えた。
討論会欠席候補に1か月の“落選運動”、奇跡の「69票差」で泉市政が誕生
討論会を終えた後、2日間にわたって結果を分析し対応を議論した。市民マニフェストにおおむね賛成し実現に努力すると答えた候補者を当然支持することになるかと思われたが、同氏を知るメンバーには「口先だけでは信用できない」とする人もかなりいた。他方、欠席した県民局長には「市民との意見交換にも出席しない候補者に、市長の資格はない」と一致し、市民自治を目指す自治基本条例に基づく市長には「県からの“天下り市長”は不適当」となった。「独自候補を擁立すべき」という“主戦論”もあったが、それでは「天下り候補を勝たせる結果を招く」という議論を重ね、結論としては「一人を選ぶ市長選挙は、よりましな人を選ぶ“戦略的”選挙をしないと、結果はより悪くなりかねない」とまとまった。
この結果、告示日前日まで「こんな市長はいらない」という“落選運動”を展開し、「69票差」という30万人都市としては奇跡的な僅差で泉氏の当選が決まった。
是々非々で対応した市長に住民投票の直接請求や「開発許可取り消し」の申し立ても
泉氏については、選挙前には「計画を抜本的に見直す」としていた明石駅前の再開発計画について、市長就任後「規模縮小など大幅な見直しは困難」として用途変更を行っただけで計画を進めることを表明したことから、再開発に反対する運動を再び始動し、「明石駅前の再開発を考える会」が発足、翌年には「駅前再開発・住民投票の会」に発展し、地方自治法による住民投票条例の直接請求署名運動に至った。
直接請求署名運動は法定の4倍を超える2万余りの署名数に達し、再開発計画の可否を住民投票にかけることを請求したが、市長は住民投票には賛成したものの、市議会は19対8の反対多数で否決した。また、翌年には中心市街地の明石港にあった明石~淡路フェリー航路の発着場跡地に高層マンションを建てる計画について「開発許可の取り消し」を求める審査請求を市長に申し立てたが、市は「請求人適格がない」と主張し、市民の請求を却下した。
他方、自治基本条例制定後の課題だった常設型住民投票条例の制定へ向けて2013年に検討委員会を発足させ、1年3か月に及ぶ審議を経て2014年10月には「請求署名数要件を有権者数の8分の1」「署名期間を(政令市や府県並みの)2か月」とした先進的な条例案を答申した。しかし、市長は議会多数派(自・公等)の強い抵抗を配慮し、答申内容を緩和した条例案を提案したが議会は否決。その後2回の再提案も否決されて、いまだに住民投票条例は宙に浮いている。