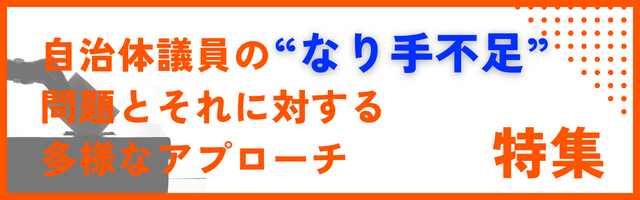政策提言市民団体「市民自治あかし」 松本 誠
政党や政治家が選挙の際に掲げるマニフェストは、旧来の「公約」から一歩踏み込んだ政策目標を具体的に明示した「有権者との約束」でもある。1990年代後半から日本でも始まり、21世紀に入ってからは、自治体選挙でも「ローカルマニフェスト」が提唱されてきた。
「市民主体の市政」とまちづくりを求める運動から出発した1990年代
兵庫県明石市で12年前の2011年市長選から市民団体が始めた「市民マニフェスト選挙」は、いわば市民から政治家(市長選挙候補者)に突き付けた「逆・マニフェスト」選挙といえる。本来、主権者は市民であるにもかかわらず、選挙となると市民は政党や政治家(立候補者)が提示する政策や政治姿勢を評価して投票するだけで、候補者を選別する手段も主体的に持たず、選挙は専ら政党や政治家側からの働きかけ運動だけで、有権者から運動することは一切封じられている。
こんな選挙や政治風土はおかしいと、明石では1990年代に入ってから「市民主体のまちづくり」や「市民主体の市政」「市政や議会への市民参画」を掲げて政策議論を積極的に展開するほか、そうした市民運動の中から市議を次々に送り込んできた。1990年代の後半から「無党派の市民派議員」が少しずつ増えて、21世紀初頭の市長選ではついに「市民の市長をつくる会」が無党派の市長候補を擁立し、新人四つどもえの選挙で次点になる選挙も経験した。
こうした経過の中で、2007年には自治基本条例の検討委員会が市民参画の下で始まり、自治基本条例制定のステークホルダーを自称する「住民自治研究会」が発足し、検討委員会に並走する形で委員会のメンバーとの意見交換や意見書、提言書の提出等を重ねながら、3年がかりで2010年4月に自治基本条例が施行された。
「市民自治の市政」を掲げる自治基本条例の制定と、ふさわしい市長選び
自治基本条例は「市民自治のまちづくり」を掲げ、市民自治の市政を運営するために「市民の市政への参画」「協働のまちづくり」「情報の共有」を「市政運営の原則」と定めた。「市民マニフェスト選挙」を始めたのは翌2011年市長選挙で、「自治基本条例施行後最初の市長は、自治基本条例を遵守し、市民自治の市政運営を明確に担う人物でなければならない」と考えたからだ。
1990年代から2000年代にかけての明石市政は、2001年の大蔵海岸花火大会事件(11人が群衆なだれで死亡した、いわゆる歩道橋事故)で責任を問われた市長が辞任したり、その後、新人4人による選挙を経て就任した市長が3期目の選挙を前に不祥事で退任するなど、2代続けて不祥事で挫折した後だけに、自治基本条例の重みは一段と大きかった。
市民が選挙にも主体的に関わろうと2010年12月には「明日の明石市政をつくる会」が結成され、まず取り組んだのが「市民マニフェスト」づくりだった。「市民がつくる市民の政策」として市長選の候補者に提案し、その実現の意思を確認する。そのために、選挙前に候補者との「公開討論会」を開いて、市民マニフェストに対する意見を求めて市民と意見交換する場をつくった。