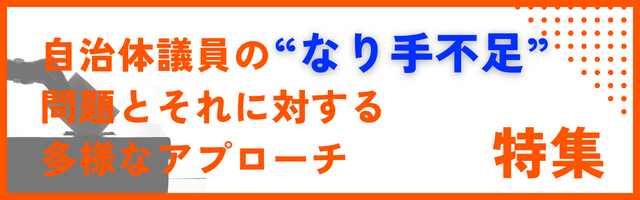9 選挙制度への着目──地方政治の劣化の解消法のもう一歩
(1)統一地方選挙の「統一」を考える:法律改正をしないで可能な改革
統一地方選挙のたびに、マスコミ報道によって地方選挙を考える機会が到来する。統一率は27%にまで低下しているものの、「統一」地方選挙であるためだ。その注目度によって、4年ごとであろうとも、地方選挙を反省することは意味がある。その意味はあるが、実施関数として73%がその時期には選挙にはなっていない(住民の73%が統一地方選挙の際に、選挙がないという意味ではない)。この時期に選挙がない場合、マスコミの注目度の低下もあって、住民の関心も低くなり投票率の低下に拍車がかかる。毎年秋にその年の選挙を統合することなど、統一率の低下問題も今後考えることにしたい。
(2)大選挙区単記非移譲式を考える:法律改正の必要性
市町村議会議員選挙は、世界でも唯一だと思われる大選挙区単記非移譲式を採用している。そろそろ限界にきているのではないだろうか。小規模自治体の議員選挙では、選挙がある場合でも競争率は低い(定数10に対して候補者が11人や12人)。それに対して、大規模自治体の議員選挙では、例えば定員36人に対して56人が立候補している。掲示板に張られた写真等を見て、投票基準にすることは困難である。一体何を基準にすればよいのだろうか。比較の思考を促す意味でも、多様性を増加させる上でも、(制限=不完全)連記(例えば、2票)などの制度改革も議論するべきであろう。
あるいは、政党が根付いている自治体(指定都市など)では、比例代表制の導入などを考えてよい。
(3)被選挙権年齢の引き下げやインターネット投票の導入
選挙権年齢は引き下げられた。しかし、被選挙権年齢はそのままだ。例えば、大学が社会とかかわる中で、政治に関心を持ち、投票だけではなく立候補して政治家になろうとする者もいないわけではない。現状では、大学卒業から被選挙権年齢まで3年間。実際に選挙があるのはそれ以上だ。こうした若い世代が立候補することで、周りの若者も関心を持つ。もちろん、義務教育修了後の16歳で選挙権と被選挙権を得るという原則の方が妥当であろう。まずは、被選挙権年齢を20歳、あるいは22歳から出発することも考えてよい。
ちなみに、世界の下院議会の被選挙権年齢は、17歳:1.0%、18歳:33.3%、20歳:0.5%、21歳:29.2%、23歳:2.6%、25歳:28.2%、28歳:0.5%、30歳:4.6%(国立国会図書館調べ、2020年現在)となっている。ほぼ3分の1が21歳以下である。
また、インターネットを活用した選挙(ホームページ、ブログ、SNS等)が可能となった。ネット選挙も模索されている。慎重さは必要だが、検討すべきである。障害者や高齢者、そして過疎地の有権者には有用だ。ただし、政策論争が前提であることを忘れてはならない。