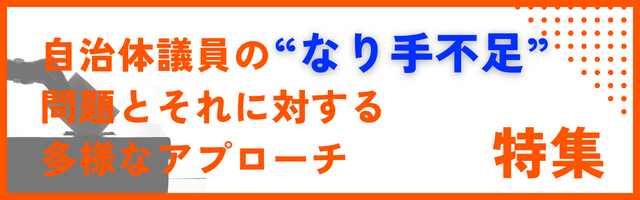取組みの成果が現れた?
その成果が現れたのか、1人定数割れの穴を埋める再選挙が令和4年5月に行われ、4人の立候補がありました。これまで本町においては、政党及び企業関係の議員以外については、住んでいる地区代表の意味合いが強く、それぞれの地区から1人ずつ議員が立候補していました。
ところが、今回の再選挙においては変化がありました。立候補を検討している人への丁寧な説明などもあり、立候補した4人ともが、従来の地区代表ではなく、年齢も30代と40代が3人含まれていました。当時の現職議員の平均年齢が70歳、60歳以下は1人しかいない議会にとって、これまでと大きく変化が感じられる選挙戦となりました。
しかし、逆に立候補した人の「人となり」が町民には分からず、誰に投票したらよいのか判断に迷ったようです。これは今後の課題です。
直近の選挙での状況
12年ぶりの選挙となりましたが、その12年前の平成23年4月の選挙では、定数16人に対し17人の立候補がありました。17人の内訳は、企業関係1人、公明党1人、日本共産党2人、その他13人はそれぞれ住んでいる地区の代表としての立候補でした。地区の代表選びに苦慮しているという声も聞いています。
まだまだ安心できない?
取組みが功を奏したのか、少し風が吹いたとはいえ、令和5年4月23日の町議選では、どのようになるのか不安がありました。結果として、定数16人に対し22人が立候補し、現職11人、新人11人と本町の町議選が始まって以来の激戦となりました。
これまでの12年間、2回選挙が行われませんでしたので、12年ぶりの選挙戦となったわけですが、最後に選挙があった平成23年4月の選挙では投票率68.4%と、投票率の低下が続いていました。
今回の選挙での投票率は、12年前と同じぐらいか、悪くても60%ぐらいはいくとの予想もありましたが、大きく外れました。結果として56.4%と、12年前と比べ12ポイント下回り、過去最低の投票率となりました。
住民に一番身近な町議選ですらこのような結果となり、引き続き議会の様子や議員としての活動を知ってもらう取組みが必要であると改めて実感しています。なお、当選者16人のうち女性が4人と過去最多となりました。地方議員選の候補者は、落選時の経済的な支援がなく「落選時のリスクが大きすぎる」といった問題があります。女性の立候補者が増えることが、「議員のなり手不足解消」のカギを握っているのかもしれません。
今後の展開
本町議会も、令和5年5月9日には初議会を終え、新しい4年間がスタートしました。特に、令和5年6月の定例会では、DXを推進していくに当たり、特別委員会を設置し、調査・研究をしていくことが決まりました。
議会を遠くに感じている住民が多いことは実感しています。議会DXを推進していくことで、議会・議員と住民との距離を一歩一歩確実に縮めていく。それが4年後の選挙に現れてくると信じて、今後も諦めずに議員とともに前進していく決意を新たにしているところです。
(1) 定数割れとなった8町村は、厚真町・興部町・中札内村・浜中町(北海道)、辰野町・山ノ内町(長野県)、幸田町(愛知県)、津奈木町(熊本県)。