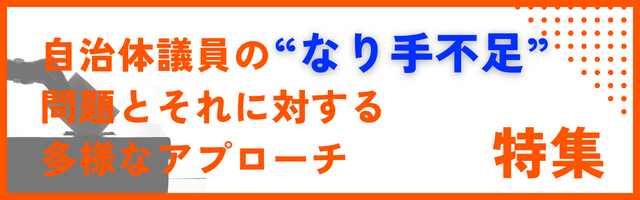大正大学社会共生学部公共政策学科教授 江藤俊昭
|
【目次】(青字が今回の掲載部分) 1 選挙に行かない、選挙に行けない現実──民主主義を「ゆでガエル」に しないために 2 政治の劣化のデメリット 3 議員のなり手不足の要因 4 議員のなり手不足の打開の方途 5 正攻法の豊富化のもう一歩:選挙を意識する 6 なり手不足解消の特効薬:政治分野における男女共同参画推進法 7 選挙を活性化させる新たな自治の動き 8 なり手不足解消の方途の誤解 9 選挙制度への着目──地方政治の劣化の解消法のもう一歩 |
7 選挙を活性化させる新たな自治の動き
政治の劣化という現状を踏まえて、その要因と打開策を議会改革の到達点を踏まえて考えてきた。そこで次に、住民及び議員による打開策の取組みについて紹介したい。これらの活動が選挙を活性化させ、さらには議会改革を大きく進めることになる。
(1)議会の多様性を実現する運動や制度
ア 女性の政治進出の支援
政治的劣化の打開策の「特効薬」として、女性の政治進出の重要性とその推進策について指摘した。「特効薬」という失礼な表現も使ったが、困難であるけれど非常に有用であることを指摘したかったからである。議員のなり手不足の解決策にも、また女性の政治進出によって女性の関心を喚起するだけではなく、議会の存在意義である「多様性」にも有効だからである。
これを推進する方策は、何も自治体(議会、行政)だけで行うものではない。社会がこの役割を担うことも重要だ。
① ネットワークの充実:女性の政治進出の支援の歴史は古い。市川房枝記念会女性と政治センターなど老舗の活動は続いている。同時に、新たなネットワークも生まれている。例えば、愛知県の「女性を議会に!ネットワーク」など、それらの活動によって女性議員が生まれている。「先輩議員」の声を聴くことができ、支援を受けることができる。それらによって立候補や議員活動のイメージが湧く。
通常の生活(男性優位の政治活動ではなく)を継続しつつ、選挙運動、そして議員活動を伝授するネットワークも生まれている。仕事と育児を犠牲にしない、他人のお金に頼らない、既存のやり方にとらわれない、という三つの原則に基づき選挙にチャレンジする支援の動きである。例えば、手法の学びや悩みの相談会である「選挙チェンジチャレンジの会」だ。2022年2月から開設している(オンライン開催)。今回の統一地方選挙でも、それ以前の選挙でも、この会で学んだことを生かして立候補者・当選者が出ている。川久保皆実つくば市議会議員がこの会を主宰している(1)。
② 住民による支援:女性の政治進出だけを目指しているわけではないが、長野県飯綱町議会元議長(寺島渉さん)が主催する「地域政策塾21」は、「住民自治と地域づくり」をテーマに学習会を開催している(2017年設立)。第4回の学習会では「女性の声を地方議会へ 女性議員を増やそう!シンポジウム」が行われた(筆者は、コメンテーターとして参加)。飯綱町では、議会による政策サポーターや議会(だより)モニターの実施などとの相乗効果で女性議員が誕生している。
③ ロールモデルの重要性:自治体を超えた支援ネットワークとともに、自治体内のネットワークも必要であろう。今回、北海道浦幌町では「政治塾」(個人個別研修会)を開催していないが、20代2人、30代1人の女性が立候補して当選した。地道な議会改革が功を奏した。そのほか、20代の「先輩議員」がコミュニケーションをとり、よい意味でのロールモデルとなっていたことが挙げられる。
④ 支援の土壌を豊かにする:立候補にはそれを決意させる土壌が必要だ。女性の政治進出を促すには、意識的にその土壌を耕す施策が必要である。自治体の男女共同参画推進計画の実践が不可欠である。
住民ではなく、自治体が仕掛けた施策だが、社会でその施策を受け入れた事例がある。兵庫県小野市は、着実にその土壌を耕した自治体だ。自治体役員に女性を登用した場合の助成金交付などの施策である。社会が変われば政治も変わるという志向だ。その結果、ゼロだった女性議員が、2011年3人、2015年4人、2019年7人、2023年7人と増加の一途をたどり、5割となっている。地道な努力が実ったといえよう。
イ 若者の政治進出の支援
若者の投票率が低いこと、特に町村では若者世代の立候補者や当選者が極端に少ない。「特効薬」といえば、若者にスポットを当てることは不可欠である。すでに指摘した女性の政治進出の支援は、若者の政治進出の支援と重なる。
住民や議員による支援というわけではないが、選挙管理委員会や議会などで行う主権者教育は、裾野を広げる意味で重要である。
主権者教育については、単に「座学」だけではなく、まちづくりにかかわる重要性を指摘してきた。条例に基づき若者議会を設置した愛知県新城市の実践は有用だ。そこで活動した若者は政治を身近に感じる。その中には議員として活動する者もいる。間(はざま)ひとみ中野区議会議員は、「新城市若者議会」3・4期メンターとしてかかわっている。
ウ 障害者の政治進出の支援
障害者といっても多様である。それぞれに適合した支援が必要だ。最近、NHKが「みんなの選挙」を立ち上げた。これは、「これまで障害があって投票に行けなかった人や行きづらかった人、障害のある人をサポートする人たちに役立つ、選挙の情報を掲載」している(障害者の選挙での投票に役立つ情報まとめ みんなの選挙 NHK)。
立候補というより、選挙の際のハードルを低くするためのものである。記事のほか、「役に立つ情報」(「イチからわかる!投票の基本」、障害の種類による基礎、「『代理投票』とは?」、「『郵便投票』するには?」、「病院や施設で投票は?」、「付きそいの人や補助犬はどこまで入れる?」、「投票所に持ち込んでいいものは?」、「入場券忘れたり体調崩したりしたら?」)が示されている。
投票技術だけではなく、「期日前投票って?」、「候補者の考えを知るには?」、「『ネットで選挙運動』の注意点は?」といった主体的に政策選挙にかかわる際の手法も掲載されている。
これらから、主体的に政策を提言し立候補する主体が登場する。むしろ、障害を持つ議員が増えることが、多様性にとって極めて重要だ。