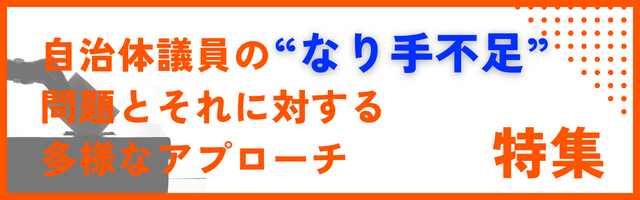2 政治の劣化のデメリット
選挙に行かない、選挙に行けない現実は、まさに政治の劣化だ。その問題(デメリット)について確認しておこう。
(1)地域民主主義の危機
選挙がないことは、議会・議員の正統性に疑問符が付けられることになる。有権者からすれば、政策も出さずに当選するのは……と。無投票で議員となった人は、審判を仰ぎたかったという。投票率の低下とともに、無投票で当選することは、民主主義の機能不全である(1)。それは、住民自治の空洞化も促す深刻な問題となっている。
① 政策競争の欠如。地方分権改革、地方財政危機に伴い地方行政とともに地方政治が重要となっている。地方政治には、政策競争が不可欠である。無投票は、その重要な機会を奪う。
② 有権者意識の危機。有権者にとって政策型選挙ができず、また議員の4年間の活動の評価ができない。住民の主権者意識が侵食される。
③ 議会の危機。無投票当選は、性別(男性優位)、年齢(高年齢化)等の偏りを促す(2)。議会の存在意義は、多様性を踏まえた公開と討議にある。存在意義であるその多様性を侵害する。
なり手不足は、選挙の有無だけの問題ではなく、住民自治にとって大きな問題を生み出す。その解消策は喫緊の課題である。首長選挙でも、無投票当選はまん延している。政策競争の欠如、主権者意識の危機は、共通である。議員選挙の無投票当選の広がりは、議決の正統性、議会の存在意義にかかわることで、より深刻だ。
(2)もう一つの地域民主主義の劣化──国政を侵食する草の根民主主義の衰退
今回の統一地方選挙は、地域民主主義(地方政治)の劣化を示しただけではない。国政を侵食してもいる。
① 政治を身近に感じさせない。最も身近な地方自治体における選挙の無風化は、住民と政治の結びつきを希薄化させる。選挙に行けない無投票当選者率の増加は、主権者意識を希薄化させる。また、投票に行かないことは、政治への無関心の一つの表れである。これらについてはすでに指摘した。
このような「民主主義の学校」である自治体の政治の衰退は、国政(国の政治)を侵食することになる。なぜなら、政治は生活の課題を解決する一手法であり、それにかかわることで政治の威力を実感する。生活に最も身近な自治体選挙が遠くに感じられ、政治との接点が切断とはいわないまでも遠くなれば、国政も空虚になる。
日本の場合、福祉、教育、社会資本、環境保全等、様々な政策は自治体が主となり実行することであっても、基本法等による自治体への計画の(努力)義務付け、補助金による誘導などにより、国政と自治体は密接に関連している。地域民主主義の劣化は、この関係のイメージを切断する。すると、国政は、生活感覚とは切り離され、イデオロギー対立に争点が矮小(わいしょう)化される。
② 政権交代など国政のダイナミズムの減退。すぐ後に指摘するように、無投票当選者率の増加の一つの要因に、政党による地域活動の消極化がある。要するに、自治体での活動を積極的に行わない、いわば地域という政党組織における足腰を鍛えないで、国政における政権交代(あるいは政権維持)を可能にすることはあり得ない。その意味で、地域民主主義の劣化は国政の劣化に連動する。
(1) 投票率の低下も大きな問題である(市議会45.6%、町村議会59.7%:2019年)。地方政治が重要になっているにもかかわらず、政治の衰退が進行している。今日、人口減少社会の進行の中で、新シビルミニマム(社会資本の統廃合等)をめぐる議論を巻き起こすことによって、政治を活性化させる戦略を考えている。
(2) 町村議会の場合、なり手不足問題だけではなく、高年齢(60歳以上77.1%(市議会57.2%))、少ない女性議員(10.0%(同15.2%))、及び少ない「専業」(22.8%(同43.9%))といった特徴がある(総務省「地方議会・議員のあり方に関する研究会」第2回資料(2019年))。