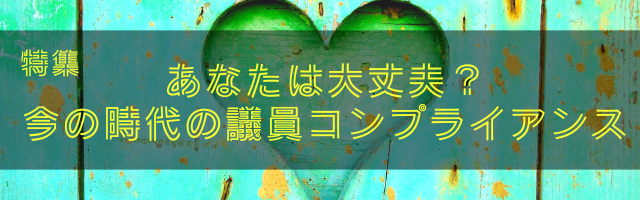弁護士 帖佐直美
近頃、自治体議会でコンプライアンス研修が行われることが増えていると感じますし、自治体議員の皆さまがコンプライアンスについて意識する機会も増えているのではないでしょうか。ここでは、具体的にどのような場面でどのようなコンプライアンス違反が起こるのか、議場と議場の外という二つの場面における事例を紹介することで、皆さまにより具体的にコンプライアンスを意識していただくきっかけになればと思います。
1 議場でのコンプライアンス違反事例
〈事例1〉
|
A市の市議会議員Bは、インターネットで情報収集をしていた際に、A市内で保育所を運営する社会福祉法人Cの理事が法人の金を横領しているとの情報を得ました。 社会福祉法人Cには、保育所の運営に関して市から補助金が出ています。 これは大問題だと考えたB議員は、市議会の一般質問の場で、「市内で保育所を運営する社会福祉法人Cの理事が法人の金を横領しているとの情報がある。Cに補助金を出すに当たり市ではどのような調査を行ったのか」と質問しました。 このB議員の言動に問題はないでしょうか。 |
議場での発言について、地方自治法では132条に規定があります。
|
○地方自治法 第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉 を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 |
活発な議論は必要ですが、感情的になるあまり、相手の人格や行動を直接非難するような「無礼の言葉」を使用してはいけません。また、職務上必要な限度を超えて相手のプライベートの問題に踏み入ることは許されません。無礼な発言や私生活にわたる発言があった場合には、議長に発言の取消しを命じられる場合もあります(地方自治法129条)。
「無礼の言葉」が「侮辱」に当たれば、侮辱された議員から処分(懲罰)を求められることもあります(地方自治法133条)。それだけではなく、刑事罰に問われる可能性もあります。
日本国憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と定めています。したがって、国会議員は議院での発言について刑事罰に問われることはありません。ところが地方議会議員については、「地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についてもいわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」(最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁)という判例があるため、議場での発言について、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に問われるおそれもあります。
無礼の言葉を使用する、侮辱に当たる発言をする、ということは「住民の代表としてどう振る舞うべきか」に気をつけて行動されていれば、なかなかないと思います。しかし、名誉毀損は意識して気をつけておく必要があります。
|
○刑法 (名誉毀(き)損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にか かわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 略 |
条文には「人」と書かれていますが、法人も「人」に含まれます。名誉を毀損、つまり傷つけられるということも、感情的なことのみを指すのではなく、社会的な評価を下げるおそれを発生させることだと考えられています。
〈事例1〉について検討すると、本会議という公の場での発言ですから「公然と」に当たると思われます。また、「社会福祉法人Cの理事が法人の金を横領している」と事実を摘示してもいます。さらに、これによって社会福祉法人Cの社会的な評価は下がるおそれがありますので「名誉を毀損した」といえると考えられます。
国会議員とは異なり市議会議員の議場での発言には名誉毀損罪が成立しますので、B議員の発言について名誉毀損罪が成立すると考えられます。
では、問題のある社会福祉法人があっても何も行動できないのかというと、名誉毀損罪には公共の利害に関する場合の特例というものがあります。
|
○刑法 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が 専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ との証明があったときは、これを罰しない。 2・3 略 |
議員の議場における発言が「公共の利害に関する事実」と全く無関係ということは考えにくいですし、発言の目的も通常は「専ら公益を図ることにあ」ると考えられます。〈事例1〉でも市の補助金が適切に支出されているのかを問題としていますので、公共の利害に関する事実に関係して、公益を図る目的でなされた発言であると判断されると思われます。
問題は「真実であることの証明」ができるかどうかです。〈事例1〉ではインターネットで情報を得ています。インターネット上の情報には情報源が分からないものが多くあります。「インターネットでそのような情報を見た」というだけでは「真実であることの証明」にはなりません。インターネット上で何か情報を得てもそれをすぐに発信してしまわず、得た情報が真実であるのかどうかをよく調べてから使う必要があります。インターネットで得た情報に基づき公の場で発言してしまうと、そんなつもりはなかったのに名誉毀損に当たる発言をしてしまったということにもなりかねません。
〈事例1〉では、B議員が名誉毀損罪で刑事責任を問われるだけではなく、国家賠償法1条によりA市が損害賠償請求をされるおそれもあります。
|
○国家賠償法 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故 意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠 償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団 体は、その公務員に対して求償権を有する。 |
議員が議場で名誉毀損に当たる発言をしてしまった場合、国家賠償法1条1項によって、自治体が賠償責任を負います。ただし、2項があります。意図的に名誉毀損に当たる発言をするということはないと思いますが、重大な過失、少し考えれば避けられたはずなのに、よく考えずに発言した結果、名誉毀損に当たる発言をしてしまったとなると、被害者に損害を賠償した自治体が、発言した議員に求償する、つまり自治体が被害者に支払った金額を議員に請求することができます。名誉毀損に当たらないように、情報は真実か否か、真実であることを証明できるかを、十分に検討した上で使用してください。
また、その情報が公の場で議論することがふさわしいものかどうかの検討も必要です。例えば、情報公開条例に基づく行政文書の開示請求を受けた場合でも、多くの自治体の条例で個人情報や法人等情報は開示しないことができるとされています。A市が不正を行っているというのであれば当然公の場で説明をすべきですが、A市とは別の法人Cの内部の問題については、公の場で発言することにより法人Cに不利益を与えることにならないか、十分に検討した上で発言すべきか否かを考える必要があります。