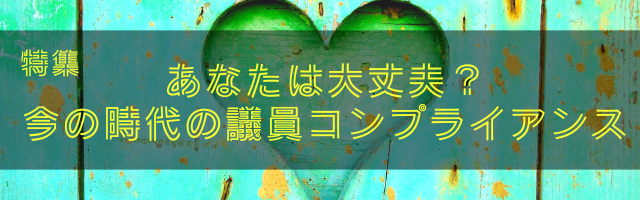3 パワハラの行政規制の導入
(1)概要
パワハラは、前記のとおり、公務災害の原因とされ、不法行為や安全配慮義務違反に基づく賠償の原因となってきたが、行政法的な規制が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の令和元年改正により導入された。事後的な個別の司法救済ではなく、職場における組織的な防止・対処を義務付けるものである。すなわち、事業主に対して、パワハラに関する相談体制の整備、パワハラ事案に対する会社としての懲戒処分等の方針の制定・周知その他パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務を新設するとともに、パワハラの防止に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針の根拠規定を置いた(2022年4月1日に完全施行)。
これに基づいて、厚生労働大臣が、令和2年1月15日に「職場におけるハラスメント関係指針」を制定した。
勘違いする向きもあるかもしれないが、上記の法律改正でパワハラが違法なものとして抽出された……ということではなく、パワハラに対し職場ぐるみで組織的に対処しなさいよと、事業主に義務付けられたということである。さはさりながら、本改正は、そのような組織的な取組みの前提としてパワハラを定義して、職場における人々の自己規律(あっ、こんなことしないように気をつけよ)を促すものでもある。
そして、上記改正法は、一部の規定を除き、地方議員を含む地方公務員について適用される。
(2)パワハラの要件
職場におけるパワハラの3要素について、本法及び指針では、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものとされ、これらの要素を全て満たすものがパワハラであることが示された。
ここで、「職場」とは、議会関係でいうならば、議場、委員会室、控室のほか、庁舎外での活動場所も含まれる(視察先の宿舎における同僚議員に対する言動等)。
①の「優越的な関係」については、職制上の上下関係が典型的であるが、それに限定されない。すなわち、抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものであれば足りる。
議員は、職員の上司である首長と対等に向き合う機関(議会)の構成員であること、そして、何よりも民意によって選出されたという金看板を持っているため、職員にとって、事実上、抵抗又は拒絶することが困難な相手である。したがって、議員と職員の間にも優越的な関係が生じ得る(であるからこそ、各地で、現にパワハラ事案が見られるわけだ)。また、議員相互の間にも、当選回数や所属組織内での地位等によって、優越的な関係が生じる場合がある。一人ひとりが社長、あるいは一人親方のようでもある議員の間にも、親分・子分関係や優越的な関係は生じ得る。
②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」の要件は、指導・監督とパワハラとを限界付ける主な要素である。業務上明らかに必要性のない言動、業務の目的を大きく逸脱した言動、業務を遂行するための手段として不適当な言動、当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動が挙げられることが多い。
執行部に文句をいうとパワハラになるのかとか、過大な資料要求はパワハラではないかという質問を受けることがある。この点、職員を叱りつけることが全て「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」に該当するわけではない。執行部が政策の正当性を主張するために不誠実な根拠付けをしていることが判明したので、担当課長に対し、その不当性を時間をかけて説諭するというのであれば、必要かつ相当な範囲内である。また、資料要求は、行政に説明責任を果たさせるためのものであって、これに関しパワハラ該当性を指摘するというのであれば、よくない萎縮効果をもたらすことになる。
他方で、「指導・監督とパワハラとを限界付ける」と書いたが、指導・監督であればパワハラではないというのは、誤認である。単なる嗜虐(しぎゃく)的なパワハラもあるが、熱血指導が同時にパワハラに該当することもある。「おまえ、こんな徴収率で誠実に納税してくださる住民にどう顔向けするんだ。払ってないやつからは、脅しすかしで、取り立てるんだよ。しつこく、やるんだよ。おまえは税金ドロボーか。まったく、ノータリンだ。豆腐の角に……」。上司は、はっぱをかけているつもりだ。「脅しすかし」、「しつこく」と、それなりにやるべきことを示して指導している。しかし、必要性・相当性を超えている。
③の「労働者の就業環境が害される」とは、その言動のため、労働者が苦痛を受け、職場で萎縮してしまって元気に働けないとか、職場に行くのが嫌になってしまうことをいう。ある人を攻撃対象とした言動で周囲の従業員が鬱になることも、該当する。
(3)議会におけるパワハラ風景
議会におけるパワハラの風景を取り上げるなら、「俺に逆らうなら、仕事をできなくしてやるぞ」、「有権者に土下座して謝れ、この能なし」等の暴言を投げつけるという「脅迫・名誉毀損(きそん)・侮辱」等を典型的なものとして挙げることができる。また、議員間のものでは、気に食わない新人議員を会派内で疎外することや、胸ぐらをつかんで恫喝(どうかつ)するという行為を挙げることができる。
そこまでの暴言暴行でなくとも、経緯や状況次第ではあるが、職員の発言に対し、聞こえよがしに舌打ちをしたり、ため息をついたりすることも、パワハラに該当し得る。例えば、会派の親分や、稽古事のお師匠さんからそのような仕打ちを受けたら、どう感じるかを考えてみるとよい。
4 セクハラ・ソジハラ
セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)には、議員が他の議員や職員に性的な言動で接し(身体に触る、性的な内容の発言をする)、相手方の対応により、次の選挙や日々の業務で妨害や嫌がらせをする旨を告知するというような対価型のものと、控室や視察先の懇親会の席で他の議員や職員に対し性的な言動に及ぶとか、控室にヌードポスターやカレンダーを掲示しているため、議員や職員が議会に当庁しづらくなるというような環境型のものとがある。今、「性的な言動」と書いたが、性的な内容の情報をSNSで意図的に流布することなども含まれる。
また、見出しに「ソジハラ」と記したが、「ソジ(SOGI)」とは、セクシュアルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティの頭文字をとったものだ。性的指向、性自認のことで、これらの事項をめぐるハラスメントも、セクハラに含まれる。例えば、相手のソジについて執拗(しつよう)に尋ねるようなことや、本人の同意なく他人に暴露すること(アウティング)は、ソジハラ、セクハラになる。
職場において、性的な事柄が入り込んで働きづらいという事象が起きれば、それを正当化することはできない。懇親会の場などで、気軽に異性あるいは同性の身体に触ったり、性的な話題で盛り上がってしまうとき、同じことを電車の中で見知らぬ人に対して行ったらどうなるかという視点で考え直すのがよい。
女性の議員や職員に対する「ちゃん付け」の呼び方や、お茶出し等を女性のみにさせることはどうか。「ちゃん付け」は、相手方の人格を尊重した呼び方とはいえない。いずれセクハラに進展する危険性もある。女性だけにお茶出しをさせることは、女性を職場の戦力としてではなく、職場の花、ひいては性的な関心の対象とする考え方の素地である。このようなあり方は、議会から排除していくべきである。