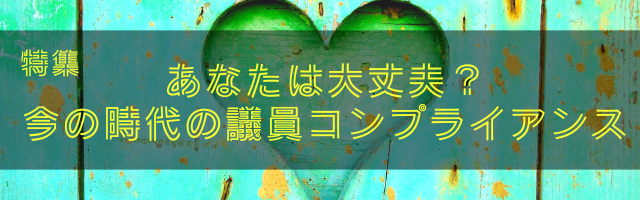さらに、議員が政治倫理に反するかどうかをどこで判断するのかということも、政治倫理を考える上で重要となる。
政治倫理に反するかどうかを判断する機関として政治倫理審査会を設置するのが一般的だが、その構成員によっては政治倫理に反するかどうかについて議会の恣意的な判断を下すことになりかねない。すなわち、政治倫理に反するかどうかを中立公平に判断する機関とするのであれば、当事者である議員をその構成員とすることは極めて問題となる。なぜなら、議会における力関係がそのまま政治倫理審査会にまで持ち込まれ、およそ客観的で中立公平な判断とならないおそれがあるからである。そのようなことから、審査会の構成員としては議員でない学識経験者や住民を構成員とすることが適当であり、弁護士や公認会計士、大学教授等の学識経験者と市民が委員となることが望ましい。
最後に、令和3年6月16日公布・施行の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正により、より一層議会におけるセクハラ・マタハラ等への対応が明確に規定され、さらにこれらの防止に関する研修の実施等が義務付けられた。残念なことではあるが、議員が当事者となるパワハラ・セクハラは決して少なくはなく、その争いが訴訟にまで発展することもある。議員として住民の範たる行為が強く求められる中、パワハラ・セクハラをはじめとするハラスメントを行うことは、当該議員だけでなく議会への住民の不信感につながるおそれが大きいため絶対に行うべきではない。
議員は住民の多種多様な要望や意見を踏まえてそれを実現するために、執行機関の職員に対し議員自身が意図しなくても執行機関の対応によっては厳しい言動をすることにより問題解決を促してしまうことが起きてしまうのは想像に難くない。しかし、それが業務上必要かつ相当な範囲を超えればパワハラとなる。さらに、執行機関をはじめとする職員や議員間での意思疎通等のために、飲食等の機会がある中、その場で相手の意に反する性的な言動により職場環境を悪化させるセクハラも起きてしまう場合がある。
議会・議員は、議会基本条例の制定をはじめとして、議会・議員としてのあるべき姿を模索してここまで様々な取組みをし、徐々にではあるが住民の信頼を勝ち得るよう歩みを進めてきている。それにプラスする形で政治倫理にのっとった行動をすることにより、更なる中立公平で良識のある議会・議員としての職務を全うされることが住民から望まれているといえることから、政治倫理の遵守にはぜひ力を注ぐべき必要があるといえよう。