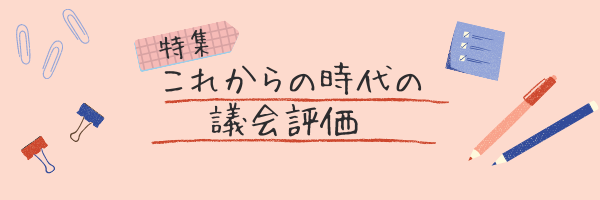3 市民を巻き込んだ政策立案への動き
議会評価は、様々な議会で行われ始めているが、あくまでも議会改革のツールであり、議会改革も「議会からの政策立案」を促進するためのツールである。その意味では、「政策立案」が本丸である。しかも、これまでの「首長vs議会」の「善政競争」から、中長期的には、デジタル化により直接的な政策発信力を具備した「市民」も参戦する「三者による善政競争」もありうる。そうなると、議会が「市民」と協働した政策立案ができるかが重要となる。
ここで、最近のデジタルツールを活用した市民協働型の議会における政策立案として、横浜市議会がパブリックコメントに付した「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例(仮称)」(以下「脱炭素推進条例案」という)の立案プロセスを紹介したい。
政令市や都道府県の議会の場合、規模も大きく、会派制が徹底しており、会派の枠を超えた議会改革や政策提言をしていくことは、事実上難しい面があるが、横浜市議会の中には、課題ごとに議員によるプロジェクトチームを結成し、議員提案の政策条例を活用した政策立案を通して、議会の機能強化を図っている会派がある。これまでも、市と議会の財政に対する責任を明確化させ、持続可能な市の財政運営をチェックする、いわゆる「財政責任条例」(5)などの「行政監視型」(6)の議員提案条例を積極的に制定しているのが、特徴的である。
横浜市議会の脱炭素推進条例案(パブリックコメント案)は、今後の脱炭素社会を見据えた施策の推進を目指すものであるが、特色としては、①市のすべての施策において脱炭素化に配慮することの努力義務化(3条4項)、②関連産業への支援による経済活性化(12条)、③民間建築物への再生可能エネルギー等の導入についての税制優遇(11条)、④他地域との連携による市域外からの再生可能エネルギー等の導入促進(9条)、⑤計画策定と実施状況に対する市民団体等と議会による行政監視(7条3項・4項、14条)などが挙げられる。このうち、①は、行政の縦割りを超えて、市のすべての部局の施策を脱炭素化に誘導するもので、⑤は、そのチェックを市民と議会が行うという「脱炭素施策に関する行政監視型議員提案条例」といえる。
また、条例案のパブリックコメントのプロセスでは、テレビ会議システム(Zoom)を活用したシンポジウムを開催した。シンポジウムには約100人の市民が参加し、学生などの若者の参加も多かったという。2021年5月14日現在、市民からの意見は76の個人・団体から延べ267件寄せられた。一般に、議会提案条例の立案プロセスでは、パブリックコメントも自治体のホームページなどで粛々と手続的に行われることが多いが、この条例案の場合、市民を巻き込んだ、アフターコロナ/ウィズコロナ時代を意識した議員の政策立案プロセスともいえる。

自民党横浜市会議員団主催の「脱炭素推進条例案」に関するオンライン・シンポジウムの様子(2021年4月24日)。
右側写真の画面映像は筆者。(写真提供:横浜自民党の再エネ・省エネプロジェクトチーム)
4 アフターコロナ/ウィズコロナ時代における議会評価と議会改革
コロナ禍を通じて、社会のデジタル化が強く叫ばれている。その先には、「デジタル民主主義」も可能性として考えられる。従来、「デジタル民主主義」という用語自体はあったが、「デジタル空間では熟議ができない」、「衆愚政治につながる」などとして、あまり積極的に評価されてこなかった。しかし、最近は、報道機関もSNS上での発言に注目するなど、デジタルツールを介した世論の動向は無視できないものになっているのではなかろうか。
また、リモートワークなどが進展し、多拠点居住民が増えると、住民概念自体も相対化し、地域との一対一の関係性を求めることが難しくなる局面が出てくるのではないか。そうなると、議会を評価する住民には、他地域と行き来する、いわゆる関係人口も含まれてくる。首長や議会への評価監視は、より厳しくなると想定される。
今後、「デジタル民主主義」的な要素を持つ多様な住民が参戦する三つどもえの善政競争が、議会の評価や改革を加速させる、そのような時代が来る可能性があると筆者は考えている。
(1)2020年6月12日付け朝日新聞夕刊「地方議会も自粛でいいの? 各地で質問・傍聴中止」によると、「早稲田大学マニフェスト研究所が〔2020年〕3月議会での対応を調査したところ、回答のあった141議会のうち『傍聴の自粛・制限・中止』は32.6%、『一般質問・質疑の中止・取り下げ』は19.9%だった」とのことであった。
(2)「地方議会評価モデル」と「議会プロフィール」の詳細については、『議員NAVI』の「特集:これからの時代の議会評価」の一連の記事、津軽石昭彦『生きた議員提案条例をつくろう』(第一法規、2020年)151頁以下を参照されたい。
(3)所沢市議会が2020年度に公表した「議会評価報告書」では、「予算常任委員会」、「政策討論会」などの項目について評価が行われている(https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/gikaikaikaku/kaikakuhyoka/gikaihyoka.files/R2.6gikaihyoka.pdf〔2021年5月9日閲覧〕)。
(4)2019年4月7日付け東京新聞では、淑徳大学の学生が千葉市議会の議員の質問内容等の評価をしたとの記事が掲載されている。また、関東学院大学の学生が、藤沢市議会の議会報告会・意見交換会(カフェトークふじさわ)に参加し、学生から提言書が提出された(http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/g07_shiryo3.asp〔2021年5月9日閲覧〕)。
(5)津軽石・前掲注(2)178~179頁を参照されたい。
(6)「行政監視型議員提案条例」は、二元代表制の地方議会に特徴的な議員立法であり、首長に対して、行政運営に関する議会への実績報告や情報提供等を条例により義務付けることにより、議会や住民による行政監視を強化する機能を有する議員提案条例をいう。詳細については、津軽石・前掲注(2)129頁以下を参照されたい。