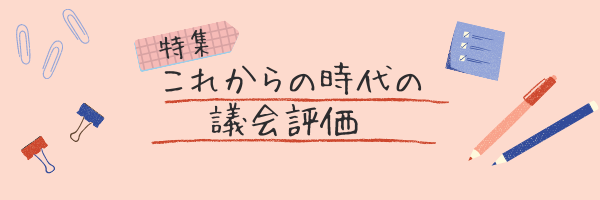2 議会評価の類型
それでは、アフターコロナ/ウィズコロナの時代に、ますます迫られる議会改革はどのように進めるべきか。改革・改善を進めるためには、議会に限らず、その前提として改革・改善すべき事項を定め、目標を絞って効果的に進めることが大切である。現在の議会の活動を検証・評価すること、すなわち「議会評価」を行うことが求められる。いわば、議会の健康診断や人間ドックである。適正な議会の健康診断等を行うためには、診断基準が必要である。しかし、これまでの議会評価の中では、議会の相対的・客観的な診断基準が存在しなかった。
これまでの議会評価の取組みを分類してみると、次のようなものがみられる。
(1)第三者による評価
ア 議会全体の活動や取組みについて、一部の側面に着目した評価
マニフェスト大賞(議会部門)などの、マニフェストや公約などの推進のための取組みを学識経験者等で構成する審査委員会が評価するものである。政策的内容も含めて、実質的な評価が行われるが、数値化等は行われず、取組みの奨励的な側面が強い。
イ 議会全体の活動や取組みについて、全体的な側面に着目した評価
公益財団法人日本生産性本部が公表した「地方議会評価モデル」の基準や「議会プロフィール」を使って、第三者機関が評価する場合などが想定される。これは、自治体の機関としての議会が、自治体全体の政策サイクルをいかに機能させているかに着目した40項目の評価項目を「成熟度」という指標で評価するものである(2)。筆者も、このモデル作成に携わっているが、現時点では、最も客観性・相対性の高い評価方法といえる。今は、議員自身や議会事務局の自己評価による「議会改革への気づき」の促進に重点が置かれており、第三者による評価は行われていない。今後、この評価方法がさらに改善されて全国に普及し、第三者評価が実施されることとなれば、議会改革は大きく進化するであろう。
ウ 個々の議員全員の審議態度等に対する評価
仙台市、相模原市、尼崎市、多摩市、国立市などの市民団体による、いわゆる「議会ウォッチャー」が「議員通信簿」として個々の議員を評価しているものである。これは、任期中の各議員の一般質問の回数や議会への遅刻や欠席の回数、居眠りや私語等の回数など、個々の議員の審議態度等に着目して市民団体が点数化し、改選期に公表して投票の参考とするもので、政策に対する評価の側面は薄い。評価の視点が単純で分かりやすく、いわゆる「トンデモ議員」の出現の予防にはなるが、一面的な評価になりがちで、運営基盤がぜい弱な市民団体もあり、仕組みとしての発展性、持続可能性の点で難しいところもある。
(2)議員による自己評価
ア 議会基本条例の項目についての評価を行うもの
北海道芽室町議会などで行われている、議会基本条例の項目ごとに各議員の活動を自己評価し、公表する取組みが該当する。議会改革を進める上で、議員自身の意識を高めるための効果は期待できるものの、自己評価であり、評価基準が議会基本条例の項目に限定されることから、どうしても「取り組んでいる」又は「取り組んでいない」の二者択一的な評価になりがちである。「どのように取り組んでいるか」などのプロセスに対する評価や評価の客観性の担保が求められる。
イ 特定の事項に対して評価を行うもの
所沢市議会などで、毎年度、議会運営委員会などにより、特定の取組み項目を抽出して評価が行われているものなどが該当する(3)。特定の事項を集中的に評価し、改善できるメリットはあるが、評価項目選定の客観性が明確ではないこと、評価が定性的になりがちであることなどの課題はある。
ウ 議会全体の活動や取組みについて、全体的な側面に着目した評価
前述の日本生産性本部が公表した「地方議会評価モデル」の基準や「議会プロフィール」を使った自己評価が該当する。現時点で、一部の基礎自治体を中心に先進的な地方議会で試行的に行われている。今後の普及が期待される。
(3)市民との協働に基づく評価
千葉市や藤沢市で、議会と大学生などの市民が、議会活動について意見交換したり、評価する試みを行っていることなどが該当する(4)。市民に対して、開かれた議会を目指すという視点から、双方向の意見交換が主目的であり、議会評価は副次的なものとなる。今後、アフターコロナ/ウィズコロナ時代において、デジタルツールによる市民参加や市民協働が容易になり、多くの市民が場を共有し、より客観性、相対性のある評価の視点が導入される方向に進化していくことも想定される。将来的には、前述(1)イの「地方議会評価モデル」や「議会プロフィール」を使った評価の仕組みと市民協働の評価が連動していくことを期待したい。