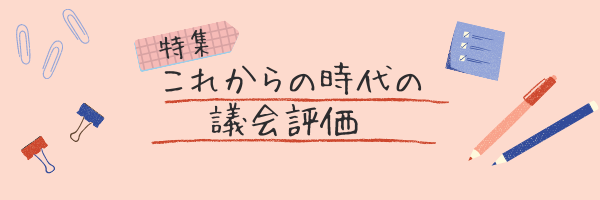関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦
1 アフターコロナ/ウィズコロナ時代では議会の存在意義が問われる
新型コロナウイルス感染症の第4波が日本中を席巻している中、今後、アフターコロナ/ウィズコロナの時代を迎え、地方議会の必要性をめぐって、「議会不要論」が大きくなるのではないかと危惧している。
その理由としては、第1に、昨年の新型コロナの第1波の際に、議会での一般質問の中止等の自粛をした議会がみられたが(1)、これは、結果的に議会で政策を議論する必要性を自ら否定したことになると筆者は考える。確かに、自治体現場の負担を考慮し、自主的に遠慮するという心情は理解できないわけではないが、本当にそれでよかったのか。緊急時には、地方自治法では、首長に専決処分の権限もあり、補正予算が必要であれば対応可能であり、後で議論することまで放棄する必要はなかったものと考える。実際、10年前の東日本大震災の際も、被災地の議会では、数次の補正予算の専決処分が行われたが、その後に議論すること自体を放棄したところはなかったと記憶している。
第2には、今回のコロナ禍を通じて、自治体の首長、なかんずく都道府県知事たちのプレゼンスと評価が高まり(2020年12月30日付け朝日新聞に掲載された同社世論調査では、新型コロナ対応に関する政府の対応について「評価する」が37%、「評価しない」が54%、知事の対応について「評価する」が54%、「評価しない」が37%という結果となり)、相対的に中央政府や地方議会の影が薄れていることである。特に、地方議会に関しては住民の関心がほとんど向けられていないといっても過言ではない。現場を預かる自治体の首長のプレゼンスが高まるのは、「団体自治」の観点からは歓迎すべき点もあるが、「住民自治」とのバランスも重要である。この意味で「住民自治」の中核として位置付けられる議会の存在が大切だが、コロナ禍により、住民からみて、首長と議会の力の差は広がっているように感じられる。
第3に、社会のデジタル化が「議会不要論」を加速化する可能性を内包しているということである。コロナ禍の中で、官民挙げてデジタル化への取組みが行われている。社会のデジタル化により、住民のデジタルに対するリテラシーが高まり、リモートワークによる住民の地域回帰が進むと、意識の高いリモートワーカーたちの中には、生み出された時間と、高まったデジタルスキルを使って、地域の自治体行政に目を向け始め、様々な政策提案を個人レベルで発信する者が現れることも考えられる。デジタル社会では、他地域との比較や、遠く離れた人との議論が容易になる。行政サービスのデジタル化が一層進むことにより、自治体の所有する様々な行政データにも簡単にアクセスすることが可能となる。行政の情報公開は一層進行することになり、自治体間の比較・検証も容易にできることとなる。これは、見方を変えると、代議制をとらなくても、住民が直接、首長と政策的な議論を行い、行政監視することができうる環境となることを意味する。議会が代議制の上にあぐらをかいていると、「議会や議員は不要」との声が高まる可能性が否めない。これまでの地方自治の世界では、議会と首長の二者による機関競争が地方自治の質的向上につながるとされてきたが、これからは、政策発信力を高めた住民も加えた三者による機関競争が現出するとも考えられる。ここでは、議会は、住民をいかに巻き込み、協働していくかがキモになる。
以上、三つの理由から、アフターコロナ/ウィズコロナの時代では、議会はこれまで以上に自己変革していくことが求められるのではないかと考える。