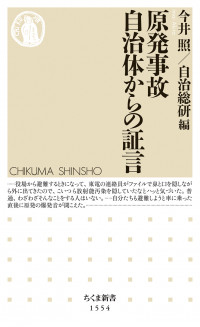震災後の災害検証
震災後こそ議会の役割は重要である。災害は単に自然現象によって起こるものではない。地震、津波、豪雨などが社会的なぜい弱性を突くことによって、自然現象が災害に転化する。例えば、火災が広がりやすい街並み形成とか、防潮堤で海が見えなくなった集落とか、劣化した堤防など、人造物そのものやその瑕疵(かし)を原因として社会的な損失を伴う災害が発生する。もちろん原発災害においては、その構造が一層鮮明である。
このことを前提とすれば、災害後は必ず検証作業を必要とする。しかし、明らかに個人に責任を求められる場合を除けば、人造物やその瑕疵の責任は行政に向けられる。例えば河川管理が適切であったかとか、避難誘導が適切に行われたかなどである。これを行政の立場から見ると、それまでの行政がいかに適切に執行されていたかを説明することになり、結果的に行政の防衛機能が際立つ可能性が高い。要するに行政は、自ら責任を認め難い立場にある。だからこそ議会が先頭に立って災害後の検証作業をする必要があるのだ。
東京電力福島第一原発災害の検証作業において最も画期的だったのは、史上初めて国会による事故検証が行われたことである(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会『国会事故調 報告書』徳間書店、2012年)。原発災害の事故検証はほかにも政府自身によるものや民間組織によるもの、あるいは東京電力によるものなどがあるが、国会による事故検証には事故原因の追究などに一定の独自性が見られる。
国会による検証作業が実現した経緯などは、塩崎恭久『「国会原発事故調査委員会」立法府からの挑戦状』(出版共同流通、2011年)に詳しいが、残念ながら国会事故調報告書に結論付けられていた継続的な検証作業はその後行われていない。なぜなら政権交代が起き、この報告書を主導した政治家たちが内閣を形成するようになってしまったからである。これに対して日本の自治体は二元的代表制をとっており、国会とは違った意味で自治体議会による災害検証が機能しやすい環境にあるといえる。
検討委員会の役割
では、自治体議会はどのように災害検証を進めたらよいのか、具体的に考えてみたい。まず議会内に災害検証に関する特別委員会を置くとともに、議会の附属機関として災害検証検討委員会を設置することは必須だろう。かつて自治体議会には附属機関を置けないという通説があったが、今はほとんど耳にしない。議会がその意思として附属機関を設置することを決定すれば、関連する予算を確保するのが行政の務めである。
検討委員会は、研究者などの学識経験者と市民から構成される。災害の性質にもよるが、学識経験者の選任には、工学系、社会学系、政治・行政学系、福祉系など、専門分野に配慮するとともに、社会的に争点がありうるとすれば、代表的な意見のバランスにも配慮する必要がある。市民については、通常の審議会のように業界団体や地域団体の代表者というよりは、被災当事者やその関係団体、あるいは支援組織などから選任するのが適切だろう。一定の公募枠も必要であり、公募状況に応じて検討委員会のサブ組織を設けるような工夫もありうる。
検討委員会における最大のミッションは、災害を引き起こした社会的ぜい弱性の検証である。自然現象がいつ、どこで、どのようにして災害に転化したのかという構造を明らかにするということだ。その上で、何が問題でどこに責任があるのか、今後どのように改善するのかを提言することになる。短期間で終わらないようであれば、定期的に中間報告を出しながら進めることも重要だ。どこまで明らかにできて、これから何をしようとしているのかということは、常に住民にオープンにしておくべきであろう。
もちろん、少人数の検討委員の知見だけでこれらの作業ができるわけではない。特に行政組織の附属機関とは異なり、よほどの大都市ではない限り議会事務局職員に検証作業の実務を頼ることができない。検証作業に当たっては幅広い人たちに協力を得ながら、検討委員会としての聞き取り、現地や先進地などへの視察、社会調査の実施などが求められるだろう。場合によっては専門部会等のサブ組織が必要になる。さらに、地元系のシンクタンクなどに委員会の運営や進行管理を委託することもありうる。重要なことは、あくまでも前述のような検討委員会のミッションを議会が手放さないことだ。
どこからどこまでを検証対象とするかも問題になる。最も狭くとれば発災直後の災害対応になり、もちろんそれも重要ではあるが、それだけでは手際の悪さ程度の総括にしかならない可能性がある。可能な限り時間の幅を長くとって、問題の根本から見直すべきだろう。検証対象の終期についても同様で、「復旧・復興」のあり方まで射程に捉える必要がある。ただし、このようにすると、議会と行政との見解の相違や対立が生まれるかもしれない。当然ながら行政には行政の流れがあり立場があるので、そのことは尊重しつつも住民の立場から見てどうなのかということを議会の総意としてまとめるべきである。
震災遺構
東日本大震災では震災遺構をめぐる地域の議論が紛糾したところもあった。遺族の心情に配慮しながら、時間をかけて震災遺構の意義を共有化していくことが大事になる。遺族の同意が得られるまでは凍結でもかまわないが、後世への継承に際しては適切な震災遺構の存在がシンボル的にも必要不可欠である。
その震災遺構に併せて災害検証を的確に表現した展示と学習施設が必要になる。災害検証は、前述のように議会で取り組まれたものが唯一無二ではなく、行政自身によるものや市民活動団体によるものなど多様に存在する可能性がある。後世の人たちや他地域の人たちがここに来ればそのすべてを理解できるような研究機関も併設されるべきだろう。兵庫県にある「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」はそうした施設の先駆として学ぶべき存在といえよう。もちろん、あれだけ大規模なものになれば県庁が関わらなければ設置も運営もできないが、小規模市町村でも小規模なりに同じ趣旨の機関が必要である。現時点で東日本大震災の被災地でこのような動きはない。特に原発災害については、福島県庁の決断が求められる。
全3回のまとめを簡潔にしておきたい。まず災害には「備え」が必要であることは誰もが認めることだろう。防災計画、避難計画、事前復興計画などの計画から、災害が広がらないまちづくりや救援物資の備蓄に至るまで、備えておくべきことは多々ある。ただし、そのすべてが必要かということは精査しておくべきで、特にインフラ整備には誰も反対しづらいがゆえに、規模が過剰にならないように注意を払うべきだろう。
さらに、災害は常に予想を超える。これに対する最大の防御は、どのような事態になっても柔軟な対応ができる組織風土を形成しておくことである。災害時は現場で決断することが求められる。上下左右の組織的情報が遮断される中で、自分たちだけで情報を集め、それを理解し、判断する能力が必要だからである。これは日常の仕事のあり方とも深く関係する。行政は得てして国や県庁などからの通知に依存する体質があるが、日常においてもその一つひとつに対して問題意識を持って対応するという組織風土を形成しておかなくてはならない。行政の宿痾(しゅくあ)に対し、議会こそが市民生活や地域社会からの視点を持てる可能性がある。そういう意味でも大震災に対する議会の役割は重要である。
〔編集部〕本記事は2017年9月25日『議員NAVI』掲載記事の再掲です。
***
<著者近刊書籍>