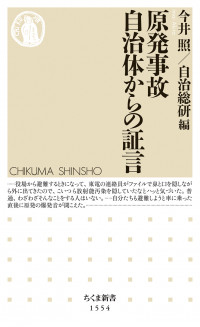「小さな自治」づくり
一般に自然災害であれば、どんなに大きな被害が出たとしても、24時間から48時間で緊急期を脱する。救援活動の山場も、生命維持の限界ともいわれる72時間がめどになる。一方、原発事故に伴う災害は時間を経るにつれて災害が拡大し、また避難指示対象も拡大していくことがある。いずれにしても、こうした初動期の後に来るのが避難期間である。
避難にも段階があり、まずは緊急時の避難所がある。その後、仮設住宅や東日本大震災で広く活用されるようになった「みなし仮設」と呼ばれる貸家やアパートでの避難生活がある。また、今回の原発災害においては、避難所と仮設住宅との間に「2次避難所」と呼ばれる旅館やホテルなどを借り上げた避難期間があった。現在の制度では、仮設住宅の次に災害公営住宅と呼ばれる避難生活が想定されている。
ただし、災害規模が大きければ大きいほど、これらの単線的な避難生活とは異なるバリエーションが避難者の数ほど存在することになる。特に東日本大震災で問題になったのは、被災地以外の地域で避難生活を送らざるを得ないことである(写真2)。例えば津波で地域が丸ごと被災すると、別の地域の避難所などで避難生活を送らなくてはならなくなる。まして原発事故に伴う避難の場合は、自治体の区域を越えて全国各地に避難生活が拡散した。さらに放射能という見えないリスクから自らや家族の身を守るために、避難指示が出ていない周辺地域からの避難者も多かった。この結果、避難所は顔見知りの特定の地域居住者で構成されるのではなく、各地からの避難者の混成になる一方、個々で避難行動をした人たちについては誰も全体像を掌握できないという事態に陥った。つまり、被災地自治体の目が届く範囲を質的にも量的にも大きく超えたのである。ここに議会と議員とに固有の役割が存在する。
 写真2 様々な地域から着の身着のままの避難者が異郷の地の避難所に集まる
写真2 様々な地域から着の身着のままの避難者が異郷の地の避難所に集まる
(2011年3月13日)
福島県浪江町議会は震災後初めての定例会を目前とした2011年6月に、議員が手分けして避難所等を回ることにした。3つの常任委員会ごとにグループを組み、延べ13か所の避難所や、2次避難所になっている旅館などを回り、懇談会を開いた。多いところで200人、少ないところでも20人の住民が集まり、合わせると約850人の住民が集まった。その後も年内に、9月、10月、11月と場所を変えて住民との懇談会を実施した。4回目には、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、新潟県などの県外でも実施している。
これらの避難先には役所も来ていないことがほとんどだ。仮に役所職員が行っているとしても、物資を持っていくか、何かの手続の説明をするだけだった。特に県外では現在でも役所の職員が行くことはほとんどない。そこを議会が回るということには格別の意味がある。ひとつは、広範囲に拡散した住民の存在を役場に知らしめる効果がある。そのことで支援の網からこぼれる住民を救うことが可能になる。何よりも当該の住民にとっては見捨てられていないという実感をもたらすことにつながる。
避難所にいる住民はある程度、役所からも見える存在である。しかし、これからも多用されるであろう「みなし仮設」の避難者は役所から見えにくく、支援も遅れがちになる。さらに避難所にも行かない地域内避難者の存在はほとんど見えない。津波などで1階が破壊されて2階のわずかなスペースで避難生活をしている人たちには支援が行き届かないことが多い。また地域外に避難している人や避難指示区域以外からの避難者を自治体行政はほとんど把握していない。災害前の地域事情を熟知した議員ならではのネットワークが必要になる。
避難生活の質を上げるためには、無数の「小さな自治」が生まれなくてはならない。避難所はもちろん、地域内の「みなし仮設」避難者間で、あるいは年代別、学校別、集落別、業種別など多様な「小さな自治」が被災者相互を救済する。もちろん自治体行政はこうした網の目からこぼれる人たちや意思的にそこから抜ける人たちに対しては直接的に支援をする責務を負うが、「小さな自治」は住民自身の力に依拠するものなので、緊急時だからといって役所が「上から」つくらせようとしてもできるものではない。地域の政治的能力にたけた議会と議員こそが、「小さな自治」づくりの触媒のひとつとなりうる。
〔編集部〕本記事は2017年8月25日『議員NAVI』掲載記事の再掲です。
***
<著者近刊書籍>