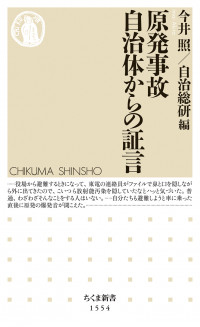議会と議員に対する住民の不満
もちろん議会としては何もしていなくても、個々の議員はもともと地域のまとめ役でもあったので、避難所の世話役などで活躍をしていた人は少なくない。しかし、住民から議員に対する不満や批判の声を聞くことが多々あった。例えば、議員個人が避難所でボランティアのような活動をしているのを見た人からは、そこは誰かに任せて議員は議員ならではの活動をするべきではないのか、という声があった。議員本人としては地域の世話役として、あるいは消防団の一員として避難所で活動をしていたのだと思うが、周囲はそれ以上の役割を期待しているということだろう。
また、ことの真偽は別として、避難所にいる住民を差し置いて、あの議員は家族ごと遠方で避難生活をしているという批判もよく聞いた。津波避難では「てんでんこ」という言葉があるように、まずは自分の生命の安全を確保するため、避難できる人からめいめいに避難をすることが被害を最小にする方法だといわれている。原因物質が目に見えない原発災害避難も同じで、まずはリスクを避けるために個々でできる限り遠方に避難をするということは当然のことだ。議員であっても同様である。だが、住民の感情はそうではない。議員は最も厳しい状態にある住民に寄り添うべきだと期待されているのだろう。
一方、役所の職員からは、議員はこの非常時に役所へ姿も見せないくせに、電話で「あいつをあそこの仮設住宅に入れてやってくれ」といった口利きだけはしてくるという話も聞いた。
私が見聞したこれらのエピソードは、その大部分が誤解に基づいているような気がする。逆にいうと、日頃から議会や議員に対する信頼感がないからこんなふうにいわれてしまうのかもしれない。そういう意味では意外に根が深い。これを解決するには、災害時だけではなく日常的な議会活動のあり方から変えていく必要がある。しかし、まずは大震災に備え、議会としてどのように準備しておくかという問題を考えてみたい。
大震災に備えて
非常時には予期しないことが起こる。だからといって事前の準備を怠れば、ますます混乱が生じる。つまり、あらかじめ様々な想定で備えておくことはもちろんだが、その上で予期しないことも同じくらい起こるということを常に頭に入れておく必要がある。
大震災に備え、自治体として、防災計画、避難計画、業務継続計画を立てておくことは今や必須の標準装備となっているが、これに対して議会がどう関与していくかがまず問われる。例えば防災計画は防災会議で策定される。ただし防災会議というのは、地域内の諸団体の代表者を集めるので、どうしても大規模な会議になる。実質的に中身まで踏み込んだ議論ができるような会議にはならない。むしろ諸団体を集めて合意を調達する最後の儀式のようなものになりがちだ。もしそうだとしたら、事前に様々なレベルで内容の調整を行う必要がある。中には非公式の折衝もあるかもしれない。
問題は、これに対して議会がどう関与するかである。防災会議の一員として議会の議長が出席する例も多いだろう。もし出席するとしたら、その前に防災計画に対する議会としての意見を集約して、事前に反映させておかなければならない。防災会議に議会の議長として参加する以上、その決定にも議会がコミットしたことになるからだ。
これに対し、防災会議での防災計画策定後にその計画を議会の議決事件として審議するという方法もある。この場合には防災会議への議長参加は見送るべきだろう。その代わり、議会では委員会審議などを通じて防災計画の内容について細かく見ていく必要がある。法律で防災計画は防災会議で策定するとあるので、議会の議決事件に加えることはできないと判断している議会もあるようだが、このあたりの法解釈は定まっているとはいえないので、今のところはいずれの方法も許容されるだろう。
防災計画に対する議会としての評価のポイントは、現実的で実効性のある計画になっているかどうかである。しばしばこのような計画は「こうあるべし」という視点から書かれるために、現実的にはうまくいかないだろうと思えることが記述されている場合がある。例えば避難計画をとってみても、複合的な災害が起これば道路や鉄道などが遮断される可能性は高く、複数の避難経路が示されていなければならないはずだ。机上の計算だけでは避難計画としての実効性がない。タテマエに走りがちな行動計画を現実的な視点からチェックするのは議会の重要な役割のひとつである。
こうした行政計画のほかに、議会としての業務継続計画も立てておく必要がある。一例を挙げれば、例えば庁舎の議場が使えなくなったときに、どこの建物のどの部屋を使って議会を開会するのか、そのときに必要な資材は何か、そのための備蓄や運搬はどうするか、個々の議員にはどのように連絡するのか、公示はどうするのかなど、キリがない。災害の規模や性質などを考え合わせて、可能な限り複線型の計画を立てておくべきだ。例えば他の自治体に議会が避難するということもありうる話だし、現実に起きている。
これらの計画は文書の体裁にしておくのは当然だが、もうひとつ重要なことは、災害時にその文書を探し出して参照することはできないということである(写真2)。事前に計画を作成しておいても、それが頭に入っていなければすぐには行動できない。しかし、計画の隅から隅まで頭に入れておくということは事実上不可能である。したがって必要なことは、事前に訓練を重ねて体で覚えるということしかない。訓練はそのためにある。
最近では議場で防災訓練をする議会も増えてきた。だが、ヘルメットをかぶって議場の机の下に潜り込むだけでは十分ではない。議会の業務継続計画に基づき、予定している議会の避難先で議会を開会するくらいの訓練はしておく必要があるのではないか。
〔編集部〕本記事は2017年7月25日『議員NAVI』掲載記事の再掲です。
***
<著者近刊書籍>