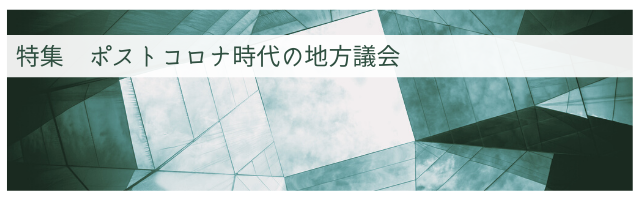自治体人口規模の違いとありうる議員像・議会像
では、そのような議会をつくり出すことは可能なのだろうか。ここでもやはり、都道府県議会・政令市議会・特別区議会とその他市町村議会とで分けて考える必要があるだろう。というのも、議会内で政党・会派のもつメリット・デメリットは、議員定数によって異なるからである。議員定数の多い前者では、まずは政党・会派の中で意見集約を図り、統一された意思を明確にすることで、有権者にとっても議員にとっても議会過程の予測を可能にすることが望まれる。しかし、数限られた議員によって構成される後者の議会では、政党・会派間の意見対立が議会への多様な意見の反映を阻害するおそれがある。
またこの両者の違いは、アンケートの回答内容にも明瞭に表れている。市町村議員は、都市部の議員よりも議会の存在意義を否定的にとらえる傾向にある。議員報酬が少額であるためになり手を見つけることが難しく、政務活動費を用いて与えられた機能を果たすことにも否定的である。それに対して都市部の議員は、政党からの呼び掛けによって若い時分から選挙に出馬することが比較的多く、たとえ選挙に金がかかっても政務活動費を活用しながら議員を長く続けたいと考える傾向にある。政党に所属する議員の割合が高い、都道府県議会・政令市議会・特別区議会の方が、議員として活躍できる状況にあることが、本書のアンケート結果から示唆されているのである。
とすると、一人ひとりの議員のもつ個性や多様性を認め、立場の違いを超えて解決策を導き出す議会が望ましいとする本書のスタンスは、比較的高い満足度を感じている議員が多い都市部の議会の実態とズレているように思われる。逆にいえば、規模の小さな議会でこそ、本書の最後に述べられている理想的なあり方が実現可能なのではないだろうか。都市部では、政党化が進展し、たとえ議会内が多数派・少数派に割れていても、あるいは会派内で上下関係のしがらみがあったとしても、それを前提として議員活動ができる状況にある。しかし、小規模自治体では、議員報酬も少なく政務活動費も不十分であり、議会そのものの魅力が限られるからこそ、なり手不足を招いている。政党化は進んでいないが地域の推薦によって立候補を余儀なくされ、他方で後継者が見つからないとするのが、本書で改めて浮かび上がった、苦境にさいなまれる農村部の地方議員像である。
地方議員や地方議会への不信を払拭するために
結局のところ、本書のタイトルである『地方議員は必要か』と有権者が考える理由は、すべての地方議会において同一ではなく、都道府県議会・政令市議会・特別区議会と、それ以外の市町村議会とで異なるものと考えるべきなのだろう。地域代表としての色彩が濃い後者の議員と、政党のリクルートメントによって着任する前者の議員とでは、それぞれ議員として果たすべき役割は異なる。市町村議会では代表する「地域」に利益をもたらすことが必要な一方で、政策的な違いはさほど重視されないだろうから、議会としてまとまりやすい。だが、財政状況が厳しい小規模自治体では、議員報酬の引き上げが難しく、政務活動費もゼロか少額であるために、議会活動に期待をもてない議員像が本書のアンケート回答から明らかになっている。よって、これら自治体の地方議員・地方議会不信を払拭するために必要な処方箋とは、議員報酬や政務活動費の引き上げであるが、決して簡単に実行できる策ではない。
他方で、都道府県や都市部の議会では、議員の数も多く政党ありきの議会運営になるために、一方で会派内での意見集約による凝集性強化が生ずるとともに、他方で会派間の政策的相違が浮き彫りになる。また、首長との支持関係の有無も、政党色が見えにくい小規模自治体議会に比べ、より明瞭なものとして議会過程に現れてくる。結果、これらの議会では、総体として一つにまとまって首長に対抗することが難しくなる。また、会派として統一的に行動することが効率的な議会運営のためにも必要であるため、たとえ内部で上下関係やしがらみがあったとしても、各議員は会派の決定に従うことが第一義に求められる。よって、本書が理想とするような、それぞれの経歴や社会的出自を背景に能動的に活動する議員像はこれら議会には合致しないように思われる。たとえ会派の方針に唯々諾々と従って議案への賛否を表明するだけの議員が多数見受けられても、政党規律の強い日本では、当然のなりゆきと考えざるをえない。
有権者は、首長提出議案の否決率・修正可決率の低さから、地方議会や地方議員の必要性を疑っていると考えられるが、それは議会や議員に非があるからというよりも、議会の権限が限られているからと見るべきであろう。首長が予算調製・提出権を独占しているため、各議員は、その求める政策を実現するためには、首長に予算要望を行い、その協力を得て予算案に盛り込んでもらう必要がある。さらに、各議員が当該予算案に賛成して可決しないと、執行可能な状況とはならない。このように見ると、地方議会・議員不信を取り除くために大規模自治体の議会で求められるのは、議会に予算調製・提出権を与え、議会における議員の調査・研究を補佐する体制を強化するといった、議会総体としての権限強化を図ることであるが、そのためには地方自治法の改正が必要になるし、議会事務局機能の強化には財政的負担も見込まれるため、やはり簡単に解決できる問題ではないだろう。
現在のコロナ禍において、どのような政策が盛り込まれた補正予算が編成されるかが重要な問題となっているが、そこで注目を浴びるのは首長ばかりであり、議会の対応に視線が集まることはほぼない。この状況が地方自治法上の制度設計に由来することを、ここで考えるべきではないだろうか。