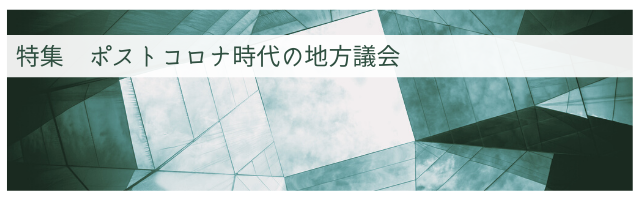本書の概要
では、上記アンケート調査から明らかになったのは何であろうか。「第1章 地方議会の役割は?」や「第2章 なれ合い議会」では、個々の「議員」の実像というよりは、「議会」の仕組みや活動実態について記述されている。アンケートの回答結果は第2章から触れられていて、やりがいを感じる議員活動の項目として、「議会・委員会での質問」や「現場視察」、「政策立案」が挙がる一方、「冠婚葬祭への対応」や「対立する利害の調整」には否定的な意見をもつ議員が半数以上を占めることが明らかになっている。また、「議会は本当に必要かと思うときがある」かについて、回答を寄せた市町村議員(政令市や特別区を除く)のうち4分の1以上が「そう思う」と答えており、議員インタビューによって予算・人事の提案権をもつ首長の権限が強いことがその背景にあると示唆されている。そして、議会での議決と住民投票との関係についても考察されており、「重要課題は住民投票で決めるべき」かどうかについて、3分の1強が「そう思う」と答えた一方で、約5分の3が「そう思わない」と答え、議員の間で見解が割れていることも示される。
他方、「第3章 トンデモ議員列伝」の冒頭で紹介されているのは、窃盗事件で逮捕された議員や酒気帯び運転で検挙された議員、贈収賄で逮捕された議員など、「議員」としてふさわしくないとされる人物像である。だが、ここから本書が焦点を当てるのは、「議員」そのものというよりは、「議会」の機能に直結すると考えられる政務活動費である。政務活動費は、当該自治体住民の福利厚生を向上するために、各議員や会派が研究・調査を行い、あるいは国等に陳情するために使われるものであり、首長に対し、よき政策提案を行うための道具であると考えられる。しかしながら、本書では、政務活動費を使い切れないために、領収書を使った水増しや、駆け込み議員視察といった実態があるとの県議の話が紹介され、町村議の4割ほどが「政務活動費はそもそもいらない」という見解をもつことを明らかにしている。この後再び「議員」の質の問題に議論が戻り、開会中に居眠りする議員の存在も暴露され、約7割の議員が「なぜこの人が、という同僚議員がいる」と考えている一方で、「議員になって羽目を外せなくなった」議員も約6割に上っている実態が明らかになった。
「第4章 地方議会 女性議員は今」と「第5章 なり手不足 その背景は」では、「議員」が何を代表しているかがデータとして示されるとともに、「議会」として機能を果たせる状況にあるかどうかが問われているといえよう。第4章では、女性議員が少ない理由として、有権者や同僚議員、職員によるハラスメントが横行しているとの自由記述が本文中で紹介され、「別の議員のセクハラ・パワハラがある」と回答した議員が、男性議員では1割強にとどまるのに対して、女性議員は3割に上ることが明らかになっている。また、「女性議員が活躍しやすい環境が整っている」と考えない議員も、男性議員では半数強であるのに対して、女性議員では4分の3近くに上り、男性議員も含めた意識改革が必要であるとの感想が述べられている。
第5章では、議員のなり手不足の背景にある議員報酬の低さの問題が検討され、特別区・政令市を除く市町村議の4分の3以上が「地方議員のなり手不足の解消に、議員報酬の引き上げが必要」と考えていることが明らかになっている(他方で、政令市議の4割以上は不要と回答している)。また、小規模自治体の議会を中心に「後継者」探しが難航しているとの自由記述回答が紹介され、結果的に議員が高齢化していることが本書で問題視されているといえよう。さらに、議員のなり手不足解消策として、「議員の仕事の周知と理解促進」が9割、「子育て世代が参加可能な設備の整備」が8割強肯定的な意見として寄せられた一方で、「被選挙権年齢の引き下げ」、「定数の削減」そして「夜間・休日等参加しやすい議会日程」については否定的な意見が肯定的な意見を上回っていることが明らかにされた。「生まれ変わっても議員になりたい」と回答する議員は3割弱にとどまる一方、「そう思わない」とした議員は7割近くに上り、身分が不安定であり生活を維持するだけで精一杯で、住民からの理解も得られておらず議員なんてやってられないという議員自身の嘆息まじりの思いも紹介されている。
「第6章 『ドン』が語る東京」では、自民都連最高顧問である元都議らへのインタビューから、議員と都知事・都庁との関係に焦点が当てられ、議員としての都政の動かし方や、与党議員と野党議員とで対応を分ける都庁の姿勢が明らかにされる。この章は、「議員」の仕事もさることながら、「議会」や会派と首長との関係についての記述が中心である。
そして「第7章 バッジのために何をしている?」は、再び「議員」に焦点が当てられ、選挙活動に関するアンケート結果が紹介されている。町村議については50代以上で初めて立候補する人が多く、政党・政治団体からの要請よりも友人・知人からの依頼に基づく場合が多いのに対し、都道府県議・政令市議・特別区議では40代までに立候補する人が約8割を占め、都道府県議を除き、政党・政治団体からの要請による立候補が友人・知人からの依頼に基づく立候補を上回る。また、特別区議や政令市議の約半数が、選挙区と出身地が異なると答えており、都道府県議も含めて「選挙には金がかかる」と答える議員が7割を超えており、これらの点でも都市部と農村部の間で違いがあることが確認される。
「第8章 地方議会 議員の未来は」では、一方で障がいをもつ議員や外国出身の「議員」それぞれの活動と、他方で住民を巻き込んでの「議会」活動の取組事例が、それぞれ期待感をもって紹介されている。また、「議員の活動にやりがいを感じない」議員のタイプとして、二つのタイプがあると本書は述べている。一つは志をもって議員になったものの限界を感じてむなしさや諦めに転じてしまった議員であり、もう一つは今の利益が損なわれないように前例を守るだけの議員である。そして、そのような議員を生み出した理由の一端が住民の無関心にあることを指摘して本書を終えている。
本書における議員と議会の理想像(?)
本書が理想とする議員像や議会像は、第8章から類推することができる。まず、議員を選出する手立てについて見てみよう。有権者は、議会で居眠りしない議員を選出できるよう、世間に関心をもつ必要がある。そして、政策について議論をしてそれを議員に伝え、場合によっては自らの声を行政に伝えるために議員に立候補することも考えるべきであり、そうすれば、自治体をよくしてくれる議員が選出されてくるだろう、というのが本書のスタンスであるように読み取れる。
ただ、議員によって求める政策は異なる。だがそれは、望ましき議会を実現するために必要である。各議員が多様性をもつことで、それぞれの経験を生かし、所属の違いを超えて議論をし、解決策を模索することが、「議会」の機能として求められるべきである。議会内の多数派であれ少数派であれ、しがらみや上下関係といった軛(くびき)から解き放たれ、志をもった能動的な議員が結集し、政策実現のために首長と正面から向き合うのが、理想的な議会である、とするのが、本書の考えなのだろう。
ここから読み取れるのは、本書が考えているあるべき議会像が、拙著『日本の地方議会』(中公新書、2019年)で論じた、「内からの改革」が目指す議会像だということである。「内からの改革」とは、各議員が互いに切磋琢磨(せっさたくま)しながら専門知識を蓄え、議会総体として首長に対抗できるだけの政策提案を行える体制を整えようとする、議員主体で起こされている改革である。そしてこの改革では、議員間あるいは政党・会派間の違いを乗り超えることが重要視されている。逆にいえば、本書では政党・会派が果たす政策集団としての機能や意見集約の機能、あるいは国会議員を通じて国に要望を伝える機能などは軽視されているようにうかがえる。